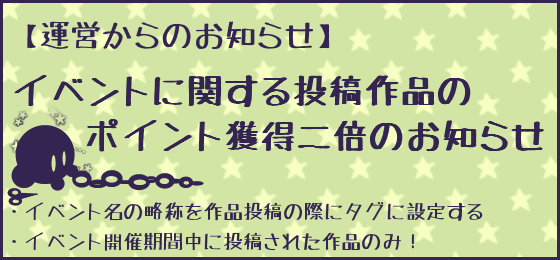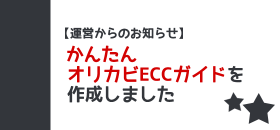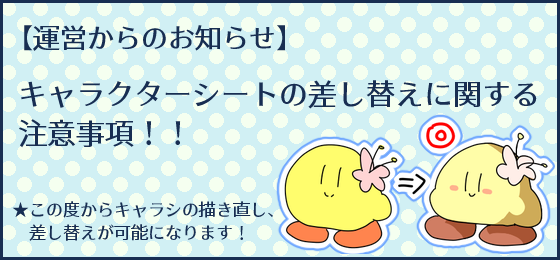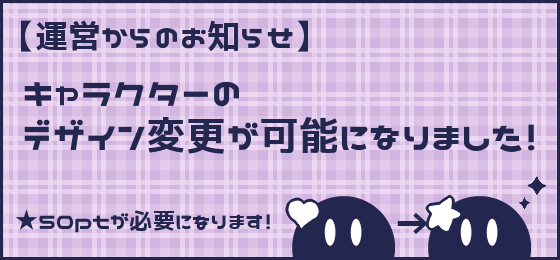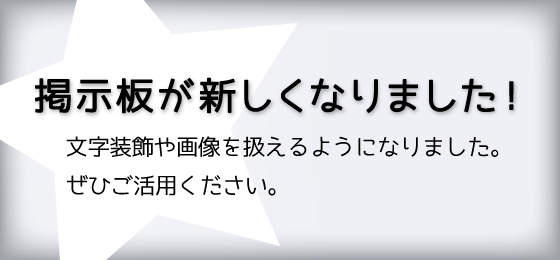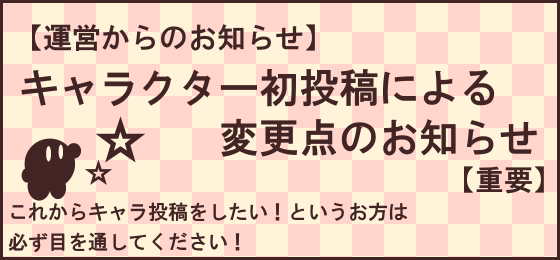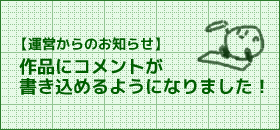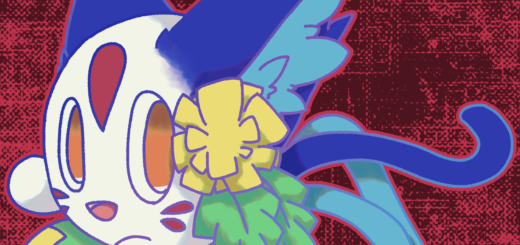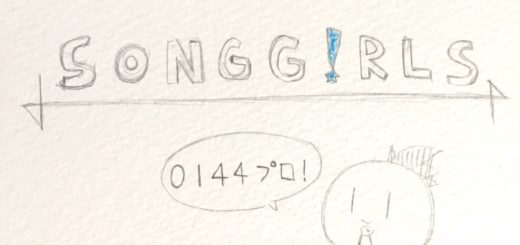途中で挫折したり会話文だけだったりする、小説というには半端なものをまとめました。
【煙を摑むような会話】登場キャラ:マーニー、ノッポ
「俺は煙になるかな」
緩やかな道中、他愛ない世間話の流れに突如として挟まれた言葉に、マーニーは反射的に相槌を打ちかけた。
しかし、それ以前に話していた内容と全く繋がらない発言を頭に浮かべて確かめると、小石に躓いたように息を詰まらせた。
「うっ、……うん? えっ、ごめん。何だって?」
マーニーは彼の相棒である巨大な芋虫・ドーラの背の上から、双子のウィリーをタイヤにしたバイクで隣を並走している青年に思わず聞き返した。
青年の被っている奇妙な縦長の帽子が、正面からの煽り風を受け、生き物のように左右にぐいんぐいんと揺れ動いている。
「俺は煙になるかな」
「……なるほどごめん、ノッポさん。全然分からないよ」
思わず聞き返したマーニーに、バイクに跨る青年・ノッポは何を考えているのか分からない真黒い双眸で前を見つめたまま、抑揚のあるようなないような声でゆっくりと同じ言葉を繰り返した。しかし、何度同じ言葉を繰り返されたところで困惑が深まるばかりで、発言の意図を汲み取るまでには至らない。
何かヒントはないかと縋るようにノッポのウィリーにじっと目をやる。視線に気づいたウィリーは一瞬マーニーの方を見たが、心なしか困ったような顔をしてすぐに目をそらしてしまった。
――あぁ、考えていても埒が明かないやつだな、これ。と察したマーニーは早々に思考を放棄した。
長年、ホシガタエリアの端から端まで幅広く商売をしてきたマーニーは、あまりひとの立ち寄らない場所にあるスタビレッジのような小さな村にも度々行商に赴いている。そのため、生まれがスタビレッジであるノッポとは、彼がスタビレッジを離れる以前からそれなりに付き合いがあった。ノッポに帽子やバイクを売りつけたのは、何を隠そう、マーニー本人なのだ。だから、マーニーはノッポのマイペースな性格についてもよく知っている。
ところが、そのひとの性格を知っているということと、そのひとの考えていることが理解できるか、ということとは全く別の問題だった。
そしておそらく、ノッポの独特な思考回路をマーニーが理解できる日は永久に来ないのだろう。
改めてその認識を確かめたところで、マーニーはノッポに率直に尋ねることにした。
「ねえノッポさん、『俺は煙になるかな』ってどういう意味だい?」
ノッポはバイクの爆音の中で、困惑顔のマーニーを輝かない黒い双眸で見上げてまったりと笑った。
【午前0時、ムーンホールにて 月の穴から月を見る】登場キャラ:エーリ、シアル
夜闇に沈んだ町の中、一軒の小さな工房に光が灯った。工房の辺りは住居が並んでおり、飲食店が多く並ぶ場所からは離れているため、動物や虫の声が時おりする以外はとても静かだ。
「悪いな、夜に押し掛けて」
「……それもそうですけど、前から言ってますが、僕は細工師であって鑑定士ではないんですよ? ……でも、ご飯おごってくれたので、良いです」
工房の入り口でシアルから鑑定を頼まれた石の入った袋を受け取りながら、エーリは呆れと諦めの中に親しみを滲ませ苦笑する。
「ありがとう、助かるよ」
少し疲れたように笑うシアルにエーリは静かに頷くと、工房の年季の入った木机の上に石と道具を並べて早速鑑定を始めた。
それから暫くの後、おおよその鑑定を終えたエーリはそう離れた場所にいない知り合いに聞こえないように、小さく息を吐いた。今回もはずれだと、これはあなたの探しものではないと告げるのは、もう何度目か。結果を告げたときの反応を考えてエーリの心は少し落ち込んだ。
「……ちょっと、おかしな感じだな」
「……え? なにがですか?」
不意にかけられた言葉に、エーリは手元の石からシアルに目を移した。シアルは開け放たれたままの工房の扉に背を凭れながら外を眺めていて、エーリの座っている場所から表情を窺うことはできない。
「ムーンホールは、たしか“月の穴”という意味だろう? 月の穴から月を見上げる、というのは、少し変な感じがすると思ってな」
もちろん、変とは言っても悪い意味じゃないぞ、とわざわざ生真面目な声でシアルが付け加えるので、エーリも思わず真面目にもちろん、と返した。
「僕はずっとここにいるので、よく分かりませんが……言われてみれば確かに、そんな気もします」
「ふうん、そういうものか?」
「近すぎると、案外分からないものなのかもしれませんね」
そうかとシアルが頷くと、言葉が途切れ、穏やかな静寂が戻る。
「……少し変だが、私はそれが好きだ」
「……僕もです」
シアルは町の真上に浮かぶ満月を見上げ、エーリは手元の石を見下ろし、会話の間ふたりの目が合うことは一度もなかった。
しかし、そんなふたりの顔には、同じように柔らかな微笑が浮かんでいた。
そしてそれきり会話もなく、エーリの作業が完全に終わるのを待って、シアルは夜明け前にムーンホールを後にした。
ありふれた、ある夜の話だ。
【狼探し】登場キャラ:ノーチェ、(ロッソ・スカルラット)
エドゥティット・ルムの大通りを、隣り合って歩く女と少年がいた。
少年は道の左右に建ち並ぶ様々な店や品々を物珍しそうに忙しなく見回し、跳ねるような声で女に話しかけていたが、女は少年の話を聞いているのかいないのか、ここ数十分は疲れたように顔をしかめ、我関せずとばかりに無言を貫いていた。
「ノーチェさんってば!僕の話、ちゃんと聞いてます?」
「あ? あぁ、聞いてない」
「えぇっ?! 正直なのは良いことですけど、酷いですよ! これじゃあ、僕が独り言の大きいひとみたいじゃないですか」
頬を膨らませてそっぽを向き、怒ってますオーラを出す少年を横目に見て、女――ノーチェは深々と溜め息をついた。
体質上暑さに弱いノーチェは、灼熱の日射しの中を長時間歩き続けるという状況に辟易としていた。そして、普通なら怖気づきそうなノーチェのぶっきらぼうな態度にもめげずに明るく親しげに接してくる少年の相手をすることにも、うんざりとしていた。
「そんなことより、アンタの親探しは止めたのか? そんなら私はもう帰っ――」
苛々と口をついて出たノーチェの言葉に、少年は一瞬何を言っているのか分からないという顔をした。しかし、徐々に言葉の意味を理解してきたのか、見る見るうちにその猫のような大きな黒目を涙で潤ませていく。ついにはふるふるとその身を小さく震わせ始めた少年に、しまったと密かに顔を引き攣らせ、ノーチェは慌てて少年の気を逸らそうと頭を巡らせる。
「おい、待て。泣くな。……あぁっ、そうだ、さっきアンタが私に聞きたがってたことは何だ? 答えてやるから泣くのは止せ」
言い終えた直後、もっとマシな方法があっただろう、とノーチェは内心舌を打った。しかし、別の方法を考えようとしていたノーチェとは反対に、意外にも少年は震えを止めると期待を込めた眼差しでノーチェを上目遣いに見上げた。
「本当ですか? だったら、あの、噂で聞いたんですけど――エドゥティット・ルムには、狼男がいるんですよね?」
ノーチェは茹だる熱の中で、瞬きもせず爛々と輝く瞳を静かに見下ろした。
「――あぁ、確かそんな噂もあったな」
表情ひとつ変えず、ノーチェは退屈そうに少年に答えて前を向いた。回答としては明らかに不足した言葉に、少年は僅かに不満そうな顔をしたが、すぐに親の話が出る前と同じ、無邪気な笑顔に変わった。
「それで、本当にいるんですか? 僕も会ってみたいです、狼男さん」
「……さぁな。私が知ってるのは噂だけだ」
数秒の間の後、ノーチェは先程と同様、ただ曖昧な言葉のみを告げた。またしても要領を得ない返事をしたノーチェに、再び騒ぎ出すかに思われた少年は、しかし奇妙なほどに静かだった。そのとき、ひやりとした冷気を側から感じ、ノーチェは咄嗟に少年を見下ろした。
「そうですか、残念です」
少年はノーチェの突然の動きに驚いた様子もなく、ニッコリと、礼儀正しく微笑んだ。
その姿に何か引っ掛かるものを感じ、ノーチェは何を言うつもりかも定まらないうちに口を開けた。しかし、すぐにそれは少年の声によって遮られた。
「――あっ、パパ、ママ! ごめんなさい、親が見つかったので戻らないと……付き合ってくれてありがとうございました、ノーチェさん!」
引き留める間もなく(元からそのつもりはなかったが)少年はひらひらと手を振りながら駆けていき、大通りの混雑した人波の中へ消えた。
ノーチェは思わず立ち止まっていたが、じりじりと肌を焼く熱で自分が今いる場所を思い出し、踵を返した。
元来た道を足早に戻りながら先ほどの出来事を思い返していたノーチェは、はたと不思議なことに気づいて顔を顰めた。
新鮮な記憶の中、あの少年だけが蜃気楼の姿をしていた。
【入れ替わる昼夜】登場キャラ:タルト
別の人格に変わっている間の記憶を持っているひとはそう珍しくない。
私はたまにそれがとても羨ましいと思う。だって、夜の間のことが知れたなら、この謎に満ちて興味深い、大好きな街のことがきっともっと分かるはずだから。だけど、この街の誰も夜の私について知らないらしい。
他の住民たちの夜の姿についての噂なら、手帳三冊分が埋まるほどには集まったのに。多分、夜の私は寝るのが好きなのだ。そうだ、だから夜の間の記憶もないのかもしれない。
その証拠に、夜に変わる瞬間まで外を飛び回っていたとしても、私が朝目を覚ますときには自宅のソファーやベッドの中にいるから。
そう、それがたとえ、インタビュー中に突然血相を変えて襲いかかってきた追っ手から逃げる最中だとしても。
――そして、それがたとえ運悪く飛行中だったとしても。
(ごめん! 後は任せた、夜の私)
(……いい加減にしろ、昼の俺)
意識が浮上すると同時、不快なほどに慣れ親しんだ浮遊感に目を細める。
動揺もなく、日課をこなすように素早く淡々と、ミニマムで体をスーパーボールほどの大きさに縮める。地面に衝突する前に頭から生える黒い触覚を伸ばし、視界に捉えた建物の外階段の手摺を的確に掴んで体を引き寄せた。
手摺を握る触角に力を込め、体をぐいと持ち上げて手摺に乗る。息をつき、そっと後方の路地を見下ろすと、追っ手であっただろう男が先ほどまで俺がいた場所を怪訝そうに見上げていた。奴が俺の姿を完全に見失ったと判断すると、手摺から飛び降りて、外階段から建物内部に繋がる非常口の鍵を触手でこじ開け、静かに中に入る。幸い、廊下には誰も居らず、ミニマムを解除して元の姿に戻った。
ナンバープレートが掛けられた客室が廊下の左右に並んでいるのを見るに、この建物はホテルらしい。もし誰かに見つかっても、ホテルの客を装えば問題ないだろう。
昼夜が入れ変わった直後、住民の大半は再び“目を覚ます”。そして、そこにある現実を取り込み適応するのに、少しばかり時を要する。
しかし、俺はその時間が他者よりも短い。だからこそ、俺は追っ手が反応する前に逃げることができるわけだが、それもこれも昼の俺の無鉄砲さが原因の副産物だと思えば、誇らしさよりも疲労感の方が圧倒的に強い。
頭の痛くなることを考えながら廊下を抜け、階段を降り、何食わぬ顔でホテルの入り口から堂々と出ていく。
昼とは様変わりした街の雑踏の中に先ほどの追っ手の姿を見つけ気づかれぬように身を固めたが、向こうは俺と目が合っても何の反応もなく、目の前を通り過ぎていった。顔を覚えられていないことを確信し、安堵する。もし奴が昼と夜で記憶を共有していて俺と昼の俺を紐づけられでもすれば、この上なく厄介なことになる。
とはいえ、一旦追っ手が撒けたところで昼の俺の問題が解決するわけではないが、元々あいつの撒いた種だ。一心同体と言えど、俺がそこまで面倒を見てやる義理はない。
飲み屋街に向けて足を進めながら、俺は帽子の中から真新しい手帳を取り出した。裏表紙の隅に小さく『タルト』とサインされたシンプルな茶革の手帳だ。
俺の物ではないが、俺の物でもある。遠慮することなく手帳を開き、中身を読む。住民や外の客から聞いたであろう噂が、注釈や考察付きで何ページにも渡って記されている。奇妙なことだが、性別も性格もまるで異なる昼の俺と俺の書く文字は、よく似ていた。
昼の俺がせっせとかき集めた噂話と俺の持つ情報を脳内で照らし合わせながら、触手を使いページを捲っていく。大半は妄想や誇張でできた話の種になるしか役に立たないものだが、中にはただの噂と片付けられないものもあった。
溜息を吐き、俺は後者のページを開いたまま、帽子からペンを取り出した。
ああ、そうだ。俺は、俺を知らない昼の俺を知っている。
昼の俺が知りたくて堪らない、大好きな街の秘密を知っている。
――決して知るべきではないことまでも。
「……お前は知らないままでいろ」
入れ替わったものに気づくまではと言い訳をして、まだ悪あがきを続ける自分を嗤った。