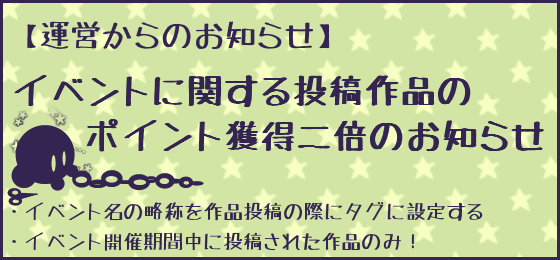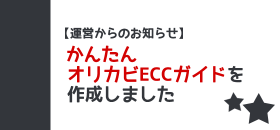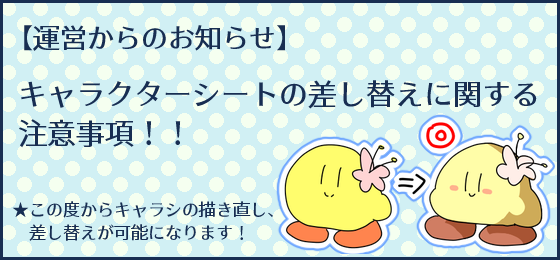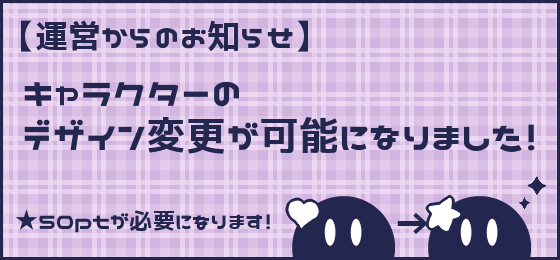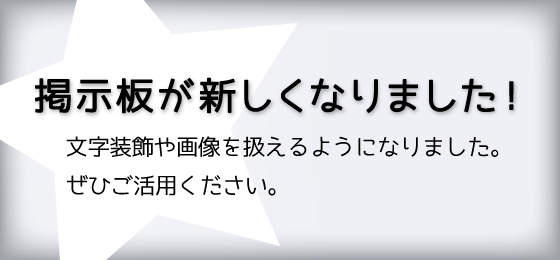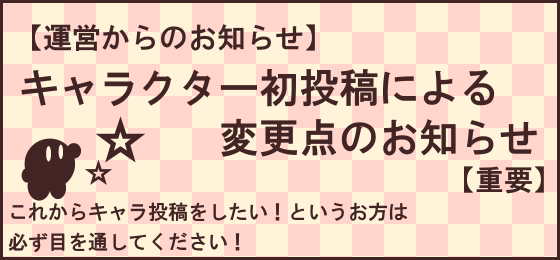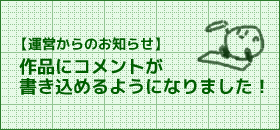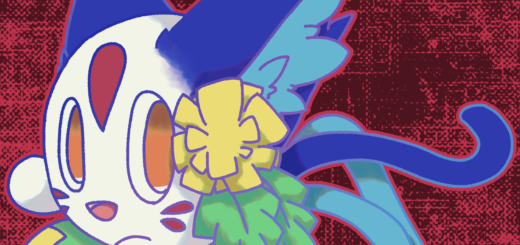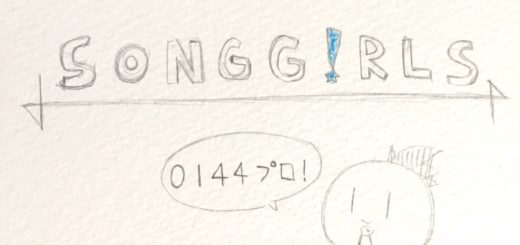目に映るものほとんど全てがお菓子で作られたお伽噺のような国、スイートストリート。
その国に続く唯一の扉は、望むか望まぬかに関係なく、いつの間にかどこかに現れ、誰にでも分け隔てなく開かれる――というのは嘘ではないが、完全な真実とも言いがたい。何故なら、扉が誰にでも開かれるからといって、誰でも国に入ることができる、というわけではないからだ。そう、残念ながら、どこの世界にも悪いことを企む悪党は存在する。だから誰にでもほいほいと入国許可を与えていては、国の安全が脅かされてしまうのだ。そこで、危険分子を判別し、排除する役割を持った存在がいる。それが、扉が開いた先でメルヘンかつ紳士然とした姿で微笑む白うさぎの球体・レフベルである。
レフベルは、スイートストリートに続く扉を城から決められた時間に開閉し、外からの訪問客に入国許可を出し、国に害をなすものを取り除くのが役目という、スイートストリートでも少々特別な存在だ。その役目ゆえに、レフベルは泰然と微笑んでいるものの、常に懐中時計を片手に忙しくしている。
特に先週は、不思議と普段よりもひとの出入りが多く、ひっきりなしにやって来る訪問者を出迎えたり観光客に街の観光案内をしたり、とまさに目の回るような忙しさが続いていた。さらには、疲労困憊寸前の状態のレフベルに追い打ちをかけるように、つい先日、彼の目を潜り抜けて入国した悪党たちが街で騒動を引き起こした。それは城の騎士や国民たちをも総動員する大事となった。最終的には、容赦なくお仕置きを下され壊滅状態に陥った悪党たちを、レフベルが文字通りその身を投げ打ってとどめを刺し、扉からどことも知らない場所へ追放したことで事態は収束した。国民たちも安堵と喜びの歓声を上げたが、それで全てがすぐに元通り、というわけにはいかなかった。連日のお祭り騒ぎに悪党退治で国民の疲労はピーク、街は悪党たちにところどころ壊されたままの状態で、不幸中の幸いか皆軽傷で済んだが、怪我人も少なからずいた。いや、それだけだったなら、いつも賑やかなスイートストリートの国民たちのことである、まだお疲れ会でも開けるくらいの元気はあっただろう。しかし、その日は金平糖の星がきらめく夜が、赤い悪夢に変わった。日々、愛情と幸福とともに見上げる街の異様で歪んだ姿に、国民たちの顔は暗く沈んだ。
そこで、城は特別なお達しを出した。『国休め』――国民たちの休息と街の修復などのため、数日間、外出に必要とする者がいるとき以外は、扉を締め切ることになったのだ。
『国休め』最初の二日間、レフベルは扉のそばで待機したり、ハイジャンプで街を見て回ったりする他に、悪党たちに破壊された物の修復を手伝うなど、通常通りかそれ以上の忙しさでせっせと働いていた。
ところが、三日目の今日。レフベルは、国への入り口の扉の前で、うろうろと右往左往していた。
「見回りは、先ほど一通り終えましたし……扉は……今日開ける予定はありませんし」
うさぎらしい長い両耳を垂れ下げ、常なら微笑を湛えている口を逆さにへこませながら、レフベルは思い悩んだ様子で黙々と扉の端から端を往復していた。住民たちはと言えば、特に注意するでも話しかけるでもなく、難しい顔で時おり何か呟きながら扉の前を歩き回るレフベルの様子を生温かく見守っていた。そして、そのまま三十分が過ぎたころ、ようやく何かの決着がついたようで、レフベルは扉の中央で立ち止まると、明るく顔を上げた。
「そう、そうですよね。やはり、私にもまだ何か、お手伝いできることがあるはずです! さあ、そうと決まればさっそく見回りへ――」
「ちょっと待ったー!」
「――とっ」
両足に力を入れてハイジャンプする直前で声をかけられたために崩れた態勢を、さり気なく整えながら、レフベルは声のした方へ体を向けた。
「おや、これはエドワード様、こんにちは。何か私にご用でしょうか?」
「こんにちは、レフベルさん。うん、まあ、そんなところ」
レフベルに手を振りながら駆け寄ってきたのは、スイートストリートの城に仕える騎士のひとり・エドワードだった。エドワードはその若い青年の外見とは想像もつかないほど古くから城に仕えている忠実で立派な騎士だが、人懐こく気の良い性格をしており、国民たちからも慕われている。その気さくさは、国の中で少々特殊な位置づけにあるレフベルに対しても変わらず、街中で出会えば立ち話をするほどには仲が良かった。
エドワードの言葉を聞いたレフベルは、喜色を小さく顔に浮かべて頷いた。
「ああ、そうですか。私も、ちょうど時間が空いていたところなのです。どのようなご用事でしょう? 私でも手伝えることであれば良いのですが……」
「あーいや、用事って言っても俺はただ、一緒にお出かけしないかってお誘いしにきただけだよ」
「……ええ、そう、お出かけ、ですか」
戸惑った顔をするレフベルに、エドワードは苦笑しながら続ける。
「まあ、そうがっかりしないでくれよ。これは、休みなく働いている君を心配しているひとたちからのお願いでもあるんだからな」
もちろん、俺がただ君と出かけてみたかった、ってのもある。とエドワードは犬のような耳と尻尾を揺らして笑った。しかし、エドワードの様子とは対照的に、彼の言葉を聞いたレフベルの顔には困惑と悔恨の色が深まった。
「私を心配? ……それは、先日の騒動が理由でしょうか? たしかに、ご心配をおかけしてしまうのも仕方のないことかもしれませんね。あのような下郎を国に入れるなどというミスを犯した揚句、このような事態を引き起こしてしまったのですから。……エドワード様、お誘いはありがたいのですが、やはり私は街の修復をお手伝いしに行かせていただこうかと――」
「ああ、レフベルさん。ちなみに、俺にお願いしてきたひとの中には、修復作業をしているひとも入っているからな」
レフベルの言葉を、まるで最初から予想していたかのように途中で遮ると、エドワードはしれっとそう言い放った。レフベルは目を広くし、両耳をピンと空に伸ばした。しかし、すぐにペタリと耳を垂らした。
「そ、そうでしたか……」
「君、あの連日のお祭り騒ぎでただでさえいつもよりも忙しかったのに、あの事件の最中も違反者たちを追い出すために、誰よりも頑張って動いていただろ? なのに、せっかくの国休めの日にもずっと街の中を飛び回って修復作業の手伝いとかしているんだもんなあ、レフベルさん。そりゃ、誰だって心配するさ」
「いえ、今回の件の責任は私にあるのですから、当然のことです」
心配と何か複雑なものを声に滲ませてやんわりと説くエドワードに、レフベルは当然のことだと心から信じているように、真っ直ぐな瞳で断言した。その頑なな姿勢に、エドワードは困ったように耳を僅かに曲げて、少し沈黙した。
「うーん……あのさ、レフベルさん。あの事件はレフベルさんだけじゃなく、街で警備をしていた俺たちにも、事前にあいつらを止められなかった責任があるんだよ」
異議を唱えようと口を開きかけたレフベルを、エドワードは彼の目を正面から見つめることで静かに制した。
「だから、俺たち明日からは上のひとたちも交えて、街の警備体制の見直しをすることになったんだ。俺たちだけじゃない。街のみんなも、それぞれ違反者への対策を練ったり新しいお菓子の開発をしたりして、スイートストリートを元通り以上に良くしようと張り切ってるよ。それなのに、レフベルさんが責任をひとり占めするのは、ずるいと思わないか? ――だって、スイートストリートは俺たちみんなの国なんだから」
そうだろ?とエドワードは街の子どもたちから頼られるお兄さんの笑顔で、レフベルの両手を握った。レフベルは思わずといった様子でコクリと頷くと、「そう、ですね」とすこし幼く見える顔で、紅茶にひと匙の砂糖が溶けるように、ふわりと微笑んだ。
「よし! それじゃあ、レフベルさん、どこか行きたいところとかある?」
「えっ? いえ、私は――ああ、ええと……申し訳ありません。私は、特に行きたい場所というのは思いつきませんね」
「そっか、分かった! うーん、そうしたらどこが良いかなー。俺も扉の外までは行けないし、やっぱり街の中になるよな。それでいてレフベルさんの好きそうなところは――」
レフベルの微笑みをお出かけに対する了承と取ったらしいエドワードは、パッと手を放して、楽しげにお出かけ先を思案し始めた。レフベルはそんなエドワードの様子を見て、出かかった断りの言葉を今日だけは呑みこむことにした。
「エドワード様のお好きなところで構いませんよ」
「俺の好きなところ? 遠慮してるわけじゃない?」
「ええ、していませんよ。ご存じの通り、私はこの街のどの場所にどのようなお店があり、どういった商品が売られているのかはよく知っています。ですが、お恥ずかしい話、実際にお店で飲食をしたことはあまりないんです。ですから、街のどこへ行っても、良い勉強になると思います。観光客の方への案内に役に立つかもしれません。……それに、久しぶりに街をゆっくり見られますから。きっと楽しい」
貴方の案内もありますしね。とレフベルはエドワードを横目に見て、悪戯っぽく笑った。エドワードは一瞬驚いた顔をしたものの、すぐに回復すると満面の笑みを浮かべて尻尾を左右に振った。
「ははっ、君にそんなに期待されたんじゃあ応えないわけにはいかないな! そうと決まれば、さあ、日が沈む前に出かけよう。俺のとっておきのお店に連れて行くよ」
大好きな散歩が待ちきれない犬のように先を行くエドワードの後を、レフベルは能力を使わずにゆったりと歩きだした。
三日前、ところどころ破損が目立っていた街は、住民たちの手と街の自己修復の魔法によってほとんど修復され、メルヘンで目にも賑やかな元通りの光景が戻ってきていた。レフベルとエドワードは、時おり住民たちや街を巡回している騎士たちに声をかけられたり返したりしながら、のんびりと通りを歩いていた。
「エドワード! また、食べよう、パンケーキ! いっしょ!」
「ピアット! 元気そうだな。ああ、もちろん良いよ! でもそうだな、せっかくだから今度の休みは友だちと一緒にパンケーキを作るっていうのはどうだ?」
「わぁあ! 好き! ありがとう、うれしい、大好き!」
ぴょんぴょんと跳ねて喜びを全身で表す淡いピンクと青の色合いをした少女に、すっかりお兄さんの顔で頷くエドワード。その光景を少し離れたところから微笑ましく眺めていたレフベルは、後ろからかけられた凛とした声に振り返った。
「レフベル様」
「シャトール様、こんにちは。扉の外に出られたとき以来でしょうか?」
「こんにちは。はい、その節はありがとうございました。……その、国の警備体制の見直しが済んだら、またお願いすることになると思います。私の個人的なことでレフベル様には何度も面倒をおかけして申し訳ありませんが……」
「いいえ、面倒などと思ったことは一度もありませんよ。シャトール様のお役に立てるのであれば幸いなことです」
その実直さと生真面目さがきっちりと身に付けた鎧姿からも滲み出るような騎士は、レフベルの言葉にほっと笑みをこぼすと、自然な形で正しく礼をとった。そして、近くで少女と何か楽しげに打ち合わせをしているエドワードを不思議そうに見た。
「ありがとうございます。ところで、レフベル様は、今日はエドワードとお出かけですか?」
「ええ。どうやら私は気づかぬうちに皆さまにご心配をおかけしていたようで、たまには休息も必要だと」
「ああ、なるほど、そういうことでしたか。エドワードも良いことを考えましたね。お任せください。城と街の警備は万全、扉の開扉申請もうちの者が代わりに受けつけています。どうぞゆっくりとお休みください」
ひとり納得して頷くと、騎士はレフベルに頼もしい笑みを見せた。レフベルは騎士の言葉に疑問符を浮かべながらも、ひとまず了解して頷いた。
「……はい。ありがとうございます」
「いえ、お礼でしたら私ではなく、どうぞエドワードに。……ああ、あちらも話が終わったようですね。では、私はこれで失礼します」
丁寧に礼をして足音もなく静かに立ち去った騎士の後ろ姿を見送るレフベルの隣に、少女と別れてきたエドワードが駆け足で寄った。
「ごめん、レフベルさん。お出かけの途中なのについ話しこんで――どうかしたか?」
「いえ、なんでもありませんよ。私も先ほどまで立ち話をしていたので、お互い様です。さあ、そろそろ行きましょう。このままでは、辿りつくころには夜になってしまうかもしれませんよ?」
「うん? じゃあ、ちょっとスピードアップするか! こっちこっち、ついてきてレフベルさん!」
誤魔化すように先を促すレフベルに少し戸惑ったエドワードだが、深く突っ込むことはせず、レフベルの言葉に従って道を前に進みだした。
二人はその後、中央の大通りを左に進み、小さい通りを城の方へ真っ直ぐ奥へ進んだ。箱庭のような国の最奥、城壁に対するように建てられた小さな喫茶店は、ほとんどが同色のチョコレートで作られており、スイートストリートにしては落ち着いた見た目だった。店内では数人の常連客だけが、午後の光が差し込む穏やかな雰囲気の中、読書や談笑を楽しんでいた。初めてスイートストリートに訪れた観光客におすすめするほどの派手さはないが、隠れた名所、といった風情が漂う場所だ。
店主に軽く挨拶をして、ふたりは窓際から少し離れた二人用のテーブル席に座った。
「ここは確か、チョコレートケーキが名物のお店でしたね」
「そのとおり! さすがレフベルさんだな」
「ふふ、まあ、実際に訪れるのは初めてなのですけどね」
「それは良かった。ここはもちろんチョコレートケーキもおいしいんだけどさ、俺のおすすめは――これなんだ」
シンプルなメニュー表を開いて、エドワードが手で示したところを覗きこむと、レフベルは傍目に分からないくらいに小さく耳を折った。
「チョコレートプリン、ですか?」
「そう。店主の最新作だから、レフベルさんも知らなかっただろ? このプリン、どうしてもレフベルさんに食べてほしくてさ」
「ええ、ありがとうございます」
レフベルはスイートストリートでは珍しいことに、甘いものが好きではなく、誰かにすすめられてもやんわりと断ってきた。しかし、今回はエドワードの気持ちを気遣うと、拒否することはできなかった。エドワードは黙ってひとつ頷くと、メニュー表を見直した。
「あっ、そうだ。ちなみに、ここコーヒーもおいしいんだ。しかもプレザさんのお墨付き」
「おや、そうなのですか? この頃はプレザ様にお会いする機会もありませんでしたからね……」
「今度、街に行く予定があるって行っていたから、そのときに会えると思うよ」
「それは楽しみですね」
ふたりはコーヒーとチョコレートプリンのセットをふたつ店主に頼むと、一息をついた。少し薄暗い照明の店内と対照的に、外はまだ柔らかな明るさに包まれ、遠く賑やかな声がぼやけて届いた。心地の良い沈黙の時が続いた。綿を優しくそっと開くように、レフベルは口を開いた。
「それで、いつから計画をしていたんですか?」
「うんんっ?」
慌てて窓の向こうから視線を正面に戻したエドワードは、レフベルの横顔を凝視したが、レフベルは先ほどと同じように窓の向こうを眺めながら続けた。
「シャトール様にお聞きしたのです。『城と街の警備は万全、扉の開扉申請もうちの者が代わりに受けつけています』と。今日計画してすぐに実行できることではないでしょう?」
エドワードは言い訳をしようかどうかと迷って口を開閉していたが、すぐに諦めて罰の悪そうな顔で両耳を垂らした。
「気を悪くしたらごめん。街のひとに頼まれたっていうのも本当のことだけど、計画自体は俺が勝手にやったことなんだ。他のひとは責めないでやってくれないか?」
飼い主に怒られるのを察知して伏せをする犬のように上目づかいでレフベルを窺っていたエドワードに、堪え切れないといったような笑い声が降ってきた。
「ふふっ! いいえ、いいえ。責めませんよ、誰も」
目尻にうっすらと浮かべた涙を拭って、レフベルはエドワードを見つめて微笑んだ。
「私のために貴方がしてくださった様々なこと、嬉しく思います。ありがとうございました、エドワード様」
呆けた顔でレフベルの顔を見上げていたエドワードは、やがて緊張をそっと解いて、両手を広げた。
「もちろん、君のためなら。どういたしまして」
コーヒーとチョコレートプリンを載せたトレイがふたりの席に運ばれると、内心店主には申し訳ないが、コーヒーで誤魔化しながら食べようかと画策しているレフベルを、エドワードは悪戯っぽく見た。
「レフベルさんはさっきお礼を言ってくれたけれど、実は、俺の計画にはまだ続きがあるんだ」
「おや、なんでしょう?」
「ヒントは君の目の前にある、俺の大好物!」
挑戦的な視線を受けて、レフベルはトレイの上を見直した。ふたりの前にあるのは、出来たての豊かな香りを立てるコーヒーと、陶器のカップに入った、ホイップクリームなどのデコレーションは一切ない、素朴な見た目のチョコレートプリンだ。
「貴方の好きなもの――つまり、チョコレートプリンですね」
「正解! 食べてみてくれ。そしたら分かるはずだから」
目を輝かせているエドワードを前に、レフベルは苦笑しつつも頷いた。金のスプーンでそっと掬い、恐る恐ると口に含んだ。いつの間にか垂れ下がっていた耳は、プリンを味わっていくうちに立ちあがっていった。
「甘くない……?」
「うん。……味はどう?」
「ええ、とてもおいしいです。もしかして、エドワード様は――」
隠れた質問を読みとって、エドワードは頷いた。
「レフベルさんって、甘いものは苦手だろ? だから、店主と協力して考えて作ったんだ。甘くなくて、それでいて当然おいしいプリン!」
そう宣言して、自分の分のプリンを頬張った。レフベルは、プリンを幸せそうに頬張るエドワードをぼんやりと眺めていた。そして、もう一口。まるでとても貴重なものを味わうように、時間をかけて。
喫茶店からふたりが分かれる城門までの帰り道。上機嫌なエドワードは、隣を歩くレフベルに問いかけた。
「そういえば、今日のお出かけは君の役に立ちそうだったか?」
「役に? ……ああ、あのことですか」
お出かけの前に、自分が観光客への案内に役に立つかもしれない、と語っていたことを思い出したレフベルは、ちょっと考えて「いいえ」と言った。予想外の返しだったのか、驚愕するエドワードに、レフベルは続けた。
「私はどうやら、大切なものはなるべく秘密にしておきたい性格のようでして」
わがままですね、と苦笑交じりに。エドワードは尻尾でレフベルの背をぽん、と打って嬉しそうに笑った。
「たまにはそれも良いさ」
ふたりで見上げた茜色の空のなか、金平糖の一番星が静かにきらめいた。