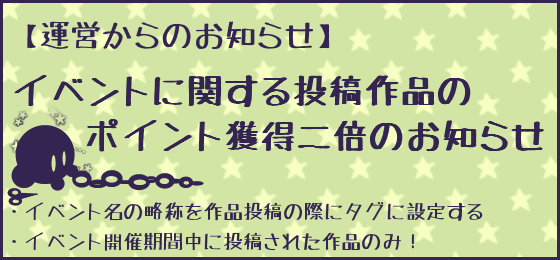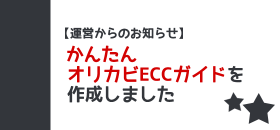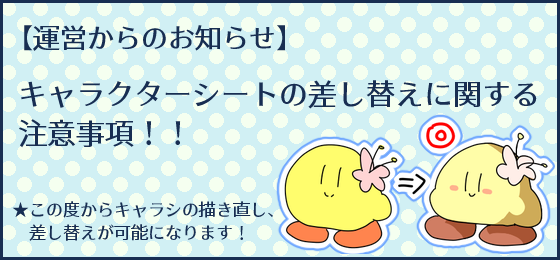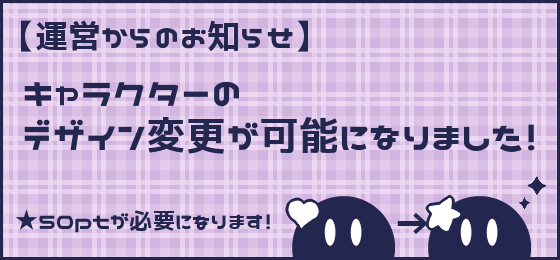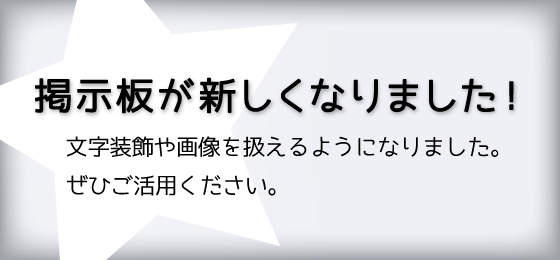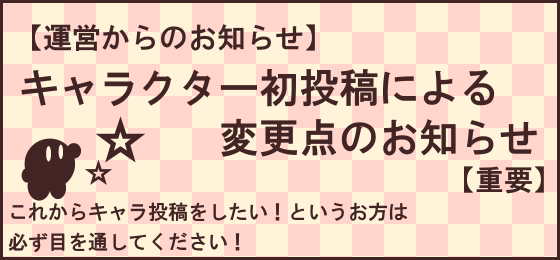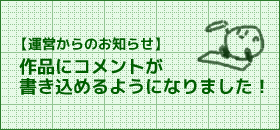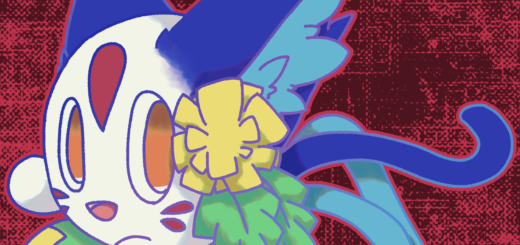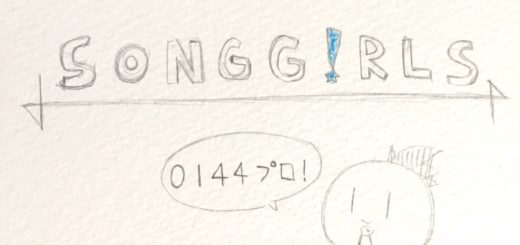変な夢を見た。
乾いた目をうっすらと開き、瞼の重さにまた目を閉じる。
どのくらい寝たのだろう。
目を閉じたまま潤いを求めてあくびをする。
滲んだ涙が目に痛い。しかしまだ目は潤いを求めていたので、もうひとつあくびをして目に水をやった。
ぼやけた世界が僕を包んだ。
どのくらい寝たかな?
口に出すのも億劫なので頭の中でそう呟いてみる。なんだか全身がだるい。頭もガンガンする。もう少し寝ようか。
ほんの少しでさえ動きたくないほどの倦怠感に抵抗もせず屈した僕はまた目を閉じた。
やっぱりだるさが僕を襲うのに飽きたら少しだけ起きよう。
まどろみの奥ですぐに砕け散る弱い決意をした。
夢の内容は、いつの間にか記憶の彼方へと消えていた。
しばらくすると倦怠感は体からすうっと抜けてゆき、代わりに軽い脱力感が全身を支配した。このくらいなら動けるだろう。
動きたくないと主張する体を無視してゆっくりと起き上がった。今は何時頃だろう。
あまり時計が好きではないので正確な時間を知る術はない。空を見よう。
「あ…れぇ…夜かぁ…えーと…もうすぐ満月かぁ、お月様まんまるだ。んー…あの辺に出てるから…夜の七時くらいか…」
そういえばなんやかんやで徹夜して寝たのは昼過ぎだった。夜に起きるのも仕方ない。
「うぅぅ…さむっ…」
春が近いとはいえまだ夜は冷える。
右手を体に巻き付けて暖を取ってみる。温い。
しかし満月に近いと夜道もよく見えていいな。ちょっと夜の散歩にでも行ってみようか。
そんな考えに抗議するように体は脱力し、眠気が押し寄せてきた。
「ん、まぁ、夜だし寝るか」
さっきまで寝ていただろうなんて言葉は聞こえない。眠くなったら寝て、眠り飽きたら目を覚ます。それだけでいいと思う。
明日は目が覚めませんように。
そう願ってまた布団潜り込んだ。
この感じ…さっきも…?
光があるようでない空間。絶望と諦観の先に見えるような世界。ここはどこだろう。
ひとりの気配。振り向く先に誰もいない。
誰もいない。でも、気配はある。
声が聞こえる。寂しい。寂しい。どうして?どうしてみんな離れて行くの?寂しい。
この声は…誰…?そこに誰か、気配が、顔が見えない、表情がない、隠れないで、諦め………
「ん……寒…」
全身から温度を奪い取る冷気が世界を覆っていた。
「えっ…なに?なにこの寒さ…ふざけてるでしょ…あっ…」
目を開けて息が漏れた。この辺り一帯が夢の中のようで、手を伸ばせば飲み込まれてしまうような白が広がっていた。
「う…わ…霧だぁ…」
霧は嫌いではない。一歩踏み出せば僕を包み込んで白に溶けて消えられるような気がするから。
特に今日は用事もやりたいことも無かったからまた一日中寝ていようと思ったけれど、予定変更だ。霧に呑まれに行こう。
僕は右半身を虚しさと楽しさで染めた。
とりあえず歩こう。目的地も意味もなにも無い。それでもただ歩いているだけで楽しいものだ。
「こういう霧の中歩いてたら異世界に着いてたとかそういうの僕にも起きないかなぁ」
ほんの数メートル先すら見えなくなった世界をアテもなく歩きながら呟いた。
「まぁそんな都合の良いこと僕に起こるわけないよなぁ…」
僕は今まで特に不思議体験をした覚えがない。だから半ば諦めているのだ。
…幽霊に会っただろって?あれは別でしょう。
それにいざ異世界に迷い込んでも色々とたいへんそうだしな。なんてあまり危機感のないことを考える。
「異世界に行けなくても行った気分になればいいんじゃないかな…あれ、霧晴れちゃっ…た……?え…?」
目の前に広がる見知らぬ土地。振り返ると濃霧が広がっている。なるほど。
「ほぅ…来てしまいましたか」
初異世界体験だな、と少し緊張が走る。しかし緊張を上回る気分の高揚が広がる。
「と、とりあえずここはどこなんだろ…」
来てしまったからには楽しもうと思い辺りを見渡す。
田んぼと畑が多いな…遠くに山も見える。田舎なのか。ちょっと散策してみよう。
しばらく農作物を眺めながら道になっていそうな所を適当に進む。
「川もあるのか…まぁそりゃあるか」
覗き込むと透き通った水が柔らかくさらさらと流れていて、環境の良さを感じさせた。
「水が綺麗なとこはだいたい良いとこだ。うん」
しみじみとそう思いながらひとりで頷く。
川に沿って歩いていくと居住区のようなものが見えた。
「ここ人住んでるのかぁ…住んでないと作物育たないか…」
こんな綺麗な土地に住んでるんだから心も綺麗な人々だといいなぁ。
ぼんやりとそんなことを考えながら家に近づいてみる。木造でしっかりした家だ。他の家も似たようなものだな。
家を見るとその土地の文明がなんとなくわかる気がする。気がするだけなんだけどね。
ここには電波塔も電線も見当たらないからきっと自然と共にそれなりにいい暮らしをしているのだろう。
建ち並ぶ家を眺めながら適当に歩く。異世界よりもタイムスリップしたような気分だ。
しかし本当に田舎だなぁ。なんだか懐かしい気持ちになる。
ほんのりと暖かいものが注がれたような気がして、心が暖色に染まる。
「ん?あっちになにかあるみたいだな…」
陽を浴びてキラキラと幻想的に光が揺らめいている大きなものが見えた。
近くに来てみると澄んだ水の池を囲むようにして公園のような場所になっていた。
「こんなとこもあるのかぁ…まぁあるかぁ…」
当たり前のことを当たり前と思えていないような感想がポロポロと出てくる。
「お、向こうになんか…鳥居?ってことは神社があるのか。御参りでもしておこうかな」
朱色のそれを目印に、池を回り込んで鳥居に向かった。
鳥居の前に立ち、ふと思い出す。
「たしか色々と作法があったっけ?あんまり覚えてないんだよなぁ…」
とりあえず鳥居をくぐる。真ん中は神様が通るから歩いちゃいけなかったはずだ…けどこれ右側通行なのかな?左かな?
どっちなのかわからないのでなんとなく左側を歩いた。
目の前には石段。ここも真ん中さえ通らなければ特に問題はなかったかな?でもこれ登るのは面倒だなぁ…結構段数あるよ…
なんとなく周りをキョロキョロとする。誰も見てないな?
「よし、おっけー」
右手を石段の一番上…は登りきって見られたら困るのでなるべく上の方に伸ばす。
石段をがっちりと掴んだら準備完了!レッツジャンプ。
「せーの…よいしょおーっ!」
掛け声と共に地面を蹴り、石段を引き寄せる。
最上段まであと数段というところまで一気に登ることに成功した。この罰当たりが。
残りの石段をひょいひょいと登りきり、神社が目の前に現れる。
「ふー…階段疲れたね!」
楽したくせによく言うよ。と心の中で自分に突っ込む。
えーと、まずは手を洗って口をすすぐんだったかな?
柄杓を手に取り水を汲む。指先にちょろちょろとかけてから残った水を口に含んで吐き出す。
「うぅ〜…冷たい…」
ひんやりとした水が外気に触れて僕の体温を奪う。
「えーと、次になんだっけ、とりあえず御賽銭箱の所に行くかな」
神社でやることを思い出しながら賽銭箱の前に立つ。
とりあえず一回お辞儀しておこう。
ぺこりと頭をさげて、お賽銭を投げる。五円でいいよね。
あとは…二回お辞儀して二回手を叩いて一回お辞儀だったかな?
ぺこりぺこりとして、手を叩く。これ、下心はありませんよって神様にアピールしてるんだっけね?最後にもう一度頭を下げて大きな鈴を鳴らす。
静かな土地に似合わない大きな音色の余韻を聞いて、これからどうしようかなぁとぼんやりと考える。
「あれ?見ない顔だね、旅人さんかな?」
突然少年のような声が聞こえた。
驚いて声の聞こえた方向に目をやると胸の前に三日月の鏡を付けた雅色の和服を着ている、大きな兎の耳の青年がこちらに歩いてきていた。
神主さんかな?でも、なんだか見覚えがあるような…いや、気のせいだろう。
それよりも僕のわかる言葉話してるからここは異世界ではないのか…
「えーと、初めまして。霧の中歩いてたらここに来ちゃいまして。それで歩いてたら神社が見えたから御参りでもしておこうかなー…なんて思ったんです」
とりあえず経緯を伝えてみる。
「あ、それと、ここってどこなんですか?あとあなたは…?」
聞き忘れるところだった。ここはどこなんだ。
「うーん、そうだなぁ。その前にひとついいかな?きみはカミサマって信じる?」
え?なにこの人。ヤバイ宗教の人かな…ヤバイ宗教に捕まって洗脳されるのだろうか…困るなぁ…
「神様…?いや、まぁ見たことはないからどうとも言えないですけど…居てもいいんじゃないですかね。実際に見たら信じますよ」
よくわからないが思ったことを口にする。
別に居てもいいが居なくてもいい。どっちにしても僕のことは救ってはくれないだろうから。
「おお!それじゃあ僕のこと信じてくれるってことでいいんだね!嬉しいなー!」
え?なに言ってるのこの人。怖いなー怖いなー…
どこかの怪談師みたいな怖がり方をしながらどう逃げるかを考えていた。
僕がそんなことを考えているのに対して、彼は満面の笑みを浮かべていた。
「そうだ、自己紹介が遅れちゃったね!僕は月の神様の月読様でーす!よろしくねー!」
なーんだ。ただの神様か。ならさっきの話も繋がるね。うん…うん?
「えっ…神様…?アナタ、カミサマ、デスカ?」
いや、まぁ居てもいいんだよ。いいんだけどさ。こんな、軽い感じなの…?
そういえば前に会った王様も軽かったなぁ…
「なんでカタコトになるのさー!さては信じてないな!」
そりゃ出会ってすぐ神様ですって言われて信じられるほど能天気じゃないよ僕は。
「じゃあ僕がどんな神様なのかを教えてあげよう!」
そう言って彼は世界の朝と夜のうち、夜を照らす役目を与えられたこと、神社の中の鏡が御霊代になっていることなんかを簡単に教えてくれた。
「つまりえーと、月読様?は月…?月の光…?あ、月の神様か…」
「だからそう言ってるじゃーん!」
まったくもーと言いながらも、彼はまるで怒っていないようにニコニコとしていた。
「あ、そうだ。きみはここに迷い込んだんだよね?よかったらしばらくうちに泊まっていかない?」
突然見ず知らずの人に寝床を提供してくれるとは…この人すごいな…よくあることなのだろうか。
「いやぁこの間ここに住んでた子がしばらく出かける用事できちゃってねー、寂しいんだよ」
うさぎさんかよ…うさぎさんだね、うん。
まぁ、泊まれるところがあるのは嬉しい。
「じゃあ、その人が帰ってくるまでお邪魔させていただきます」
よろしくお願いします、とお辞儀をする。今日はペコペコしてばかりだな。
未だ距離感を掴めていない僕に反して彼は嬉しそうにちょっとの間だけどよろしくねー!なんて言ってくる。
ただなんとなく、どこか違和感を覚えるのはきっと気のせいだろう。
「あ、そういえばここどこなんですか?」
聞いておいてすっかり忘れていたことを思い出して聞く。
「そういえば答えてなかったね!ここはツキミカガミ!神様の住まう土地だと思ってくれればだいたいおっけー!ずっと霧に包まれてるから隠れ里なんて呼ばれることもあるよ」
隠れ里ツキミカガミ…うん、知らないな。
そもそも神様しか住んでないなら知ってる方がおかしい。
「現代社会の中にこんないい所ってあるんですねぇ…」
来てから間もないがこの何にも縛られていないような緑溢れる空間は、なんとなくいい所だと思えた。
「そういえばこんなに朝早…そうな時間になにをしていたんですか?」
正確な時間はわからないが霧が出て空はうっすらと明るい程度。結構な明朝だろう。
「あっ、そうそう!境内の掃除でもしようかと思ってね!きみも手伝う?」
強制ではない。だがこっちはしばらく床を借りる身、断ることはできないな。
それに掃除は嫌いじゃないから断ることでもない。ものが綺麗になると少しだけ軽くなる気がする。
「えっと、じゃあどこ掃除しましょう?」
そう言って彼に指示を貰い掃除を始めた。
「そろそろお昼にしよっかー!」
汚れが付いた所をひたすら擦り綺麗に磨き続けていると明るく声をかけられた。
周りに目を向けると影は短くなっていて空は青が深まり、緑は生命を輝かせていた。
集中が切れたのか、胃がキリキリと痛んでいることに気付く。たぶんお腹がすいたのだろう。
思い返すと起きてからなにも食べていない。まぁ、よくあることだけど。
わかりましたーと出し方を忘れかけていた声を絞り出し彼の後ろについて歩いた。
神社の部屋に入る時、なんとなくお邪魔しますと呟き彼に促されて食卓に着く。
「お餅とごはんがあるけどどっちがいいー?」
彼は台所へ向かいながら朗らかにそう聞いてきた。
「あ、ごはんでお願いします」
月の神様だから丸餅普段からストックしてるのかな…となんとなく思った。
しばらく彼の鼻歌を聞いていると、台所からぴょこぴょこと歩いてきて、にっこりとしながらみっつずつおにぎりを食卓に広げた。
「さー!月読様特製のおにぎり!召し上がれ!いただきまーす!」
「それじゃあ、いただきます」
元気だなぁと思いくすくすと笑ってから、艶があり湯気を立ち上らせるおにぎりに手を伸ばした。
ひとくち齧ると少し多めの塩が米の甘さを引き立てて、空っぽの胃袋と疲れによく沁みた。
「ん〜!月読様特製おにぎりおいしいです!」
思わず笑顔が零れて心がほんのり暖まった。
「そうでしょ〜!月読様はすごいんだぞ〜!」
そう言いながらキリッとした表情を見せる彼に僕はまた笑った。
それに釣られたのか彼も笑った、けれどやはりどこか違和感があった。
違和感もあったが、既視感もあった…どこで?
直後、二日立て続けに見た夢のシーンが脳内に溢れた。
「あっ…!あの、月読様、もしかして僕の夢…出てきました…?」
「えっ?なんのこと?僕知らないよ?」
きょとんとした顔をされる。
突然そんなこと聞かれたらその反応は間違っていない。
それに他人の夢に自分が出たかなんて普通わかるはずない。僕が馬鹿だった。
「いや、夢の中で月読様に…似たような人?と逢った気がするんですよ」
突然口走ってしまったことに気まずさを感じて、確信はあるのになんだか曖昧な言い方になる。
「なんていうか、月読様の微笑い方…ちょっと違和感があるような気がして。それで夢の中で逢った人が、月読様の本当の姿だったんじゃないかなぁ…って思ったんです」
彼は少し考えるように俯いて、表情が薄くなった。
それでも彼はなにも言わないので、なんだか気まずくなりおにぎりをひとくち齧った。さっきまでの美味しさは嘘のように消えていた。
「僕はきみの夢に入った覚えはないけど…もしかしたらたまたま僕のナニカと繋がっちゃったのかもしれないね」
そう言った彼の表情は夢と重なった。
「やっぱり…作り笑いだったんですか?」
「きみだってするでしょ?作り笑い」
確かにする。でも、他の人が無理してまで微笑うのは…なんだか心苦しい。
「どうして…無理して微笑ってるんですか?」
「寂しいから。微笑ってれば大体の人は仲良くしてくれるでしょ?」
「でも本当は…色々と、諦めてますよね?」
夢で僕を包んだ感情を思い出した。虚しさや、諦め。そんな想いを感じた。
「だって僕、この世界に朝と夜が生まれたときには居たんだよ?どんなに僕と一緒に居るって言ってくれても、人には寿命があるし僕からしたらそれはほんの一瞬。何度も出逢って別れてを繰り返したよ。それに人々は殺し合いもするから。いつ誰が居なくなるかなんてわからないんだよ」
いつ誰が居なくなるかわからない。その言葉に少し胸が痛んだ。
「そう…ですよね…誰だって死ぬし、永遠に一緒とか…無いですよね」
なんとなく、無理に微笑ってみる。
僕も作り笑い、してるじゃないか。
「さっ!暗いお話は終わりっ!ごはんは美味しく食べましょう!」
彼がそう言ってニッと笑う。
「そうですね、美味しくいただきます」
煮え切らない気持ちもあったが、ごはんは美味しく食べないと申し訳ない。
気持ちは切り替えたつもりだったが、やっぱりごはんの味は少しだけ薄くなっていた。
昼食を終えて少し休憩をしてから掃除を再開することになった。
休憩している間はなんだか話かけ難く、俯いてお茶を啜っていた。
「さぁ!そろそろお掃除を再開するよ!」
元気にそう言ってきた彼は気持ちの切り替えが早いのか、それとも感情が欠如しているのか。
どちらにせよ今の僕に関係はないかな、と割り切って汚れ落としを再開した。
一通り終えて綺麗になったものを眺めて見ると、そこから伸びる影が随分と長くなっていることに気付いた。
「もう夕方になるのか…一日経つの早いなぁ」
ぐっと背中を伸ばして大きく息を吐いた。
「おお〜!綺麗になったねー!手伝ってくれてありがとー!」
彼は隣にちょこんと腰を掛けて笑顔を見せた。
「いえいえ、寝床を貸りるんですからこのくらいは」
掃除の後はスッキリしていいですよねーなんて言ってもう一度伸びをした。
「そういえばきみ、僕が夢に出てきたんだよね?どんな夢だったの?」
「んぇ?あー、あの夢ですか」
忘れかけていたことを聞かれ素っ頓狂な声が出る。
「えーっと、たしか月読様の姿は見えてなかったんですよね。でもなんだか仮面を被ってるような、無理して笑ってるような、そんな気配はあったんです。それに周りになんていうか…寂しさとか諦めとかそういう感情?が漂ってる感じで。あとは寂しいって声が聞こえたかな…あとはよく覚えてないです」
ぼやけた記憶をかき集めてなんとか言葉として紡いでみる。
「なるほどねー、なんでそれが僕だと思ったの?」
確かに普通ならそんなこと思うはずがない。でも、どこか確信めいたものがあった。
「うーん…雰囲気…ですかねぇ…」
その割には大した答えは出なかった。
そもそも自分でもなんでなのかよくわかっていない。
「雰囲気かぁ〜、僕そんな雰囲気出てるかな?」
やっぱり隠しきれないものってあるのかなーとか言いながらやっぱりニコニコとしている。
「あの、僕別に笑ってないと離れるってわけじゃないので…無理して笑ってなくても大丈夫ですよ…?」
そもそもしばらくしたら出ていくのだからあんまり関係ないよな、と心の隅で思う。
「うーん…本当にそれでいいと思ってる?常に無表情での対応ってされたらつらいでしょ」
少し厳しい目を向けられ一瞬怯む。
「…笑ってても無表情でも、本心が笑ってないのなら笑っても…その笑顔に本当の価値はないと思います。それだったら、本心に近いほうがいいんじゃないかな、って思います」
素直な気持ちをぶつける。
言ったことは確かに本当に思っていることだが、それ以上に無理してる人をあまり見たくないだけだ。僕のちょっとした偽善とエゴだ。
「なるほどね、じゃあちょっと気を抜いちゃおうかな」
そう言って彼は表情筋を緩めた。独りで居る時の僕みたいな表情だな、と遠くで思った。
「月読様って、どんなことを見てきてどんなことを考えたんですか?…昔は諦めてなかったんですか?」
なんとなく、知りたくなった。この寂しがりの神様のことを。
「うーん、そうだね。色々と見てきたよ。たくさんの人が生まれてたくさんの人が死んでいった。戦争もたくさん起きた。命のじゃれあいで大怪我をした人、謎の病に侵された人、昔は助けようとしたこともあったんだよ?でもね、みんな死んじゃうんだ。」
哀しげな言葉の奥と、それを語る顔には一切の哀れ気を感じない。
それどころか、人の死にあまり関心がないようにも見えた。僕も人のこと言えるような人じゃないけど。
「手を貸しても、運を与えても、みんな死んで僕から離れて行っちゃうんだよ。だからいつからかな?きっと無駄なんだなって…本当は薄々気付いてたけど気付かないようにしてたのに無視できなくなってね。それから僕は、きみたちを見てるだけにすることにした。きみたちも僕を見てるだけでいい」
その瞬間だけ、少し哀しげな表情をした気がした。
「でも悩んでる人が居たら導いてあげたりもするんだよ。最近は文明が発達しちゃったから悩みもなんとかなることが多いし、夜も明るくなって僕を見る人も少なくなったから…ちょっと寂しいんだ」
彼はふぅ、と息を吐き今はきみが聞いてくれるからちょっとは紛れるかな。と小声で付け加えた。
「僕は…お月様よく見ますよ。あんまり騒がしい光って得意じゃないんです。だから僕は生きてる間だけですけど、月読様のこと忘れないようにします。夜は空を見上げます。月の光で道を歩きます」
だから、今は寂しがらなくていいですよ。最後に言いたかったこの言葉は、声にならず息となって夕闇に溶けた。
「そっか、嬉しいな」
あんまり嬉しそうには見えませんよ。そう思ったけれど、少しだけ微笑んでる気がしたのでその思いは湿った空気と一緒に飲み込んだ。
「そろそろ陽が沈みますね。明日は晴れかな?」
綺麗な橙に染まる雲と空を眺めながら呟く。
「そうだね、そろそろ僕の出番かな」
彼はそう言って立ち上がり息を吐いた。
「夜はお月様としてなにかするんですか?」
何やることがあるのかと思い彼の顔を見る。
「さっき言ったでしょ。僕はきみたちを見てるだけって」
「特にすることはないんですね」
少し笑ってそう返す。
「そうだ、今夜は満月だよ。鏡池で宴があるんじゃないかな?一緒に行く?」
鏡池?あの大きな池のことかな。
「お酒弱いですけど大丈夫ですか?」
宴はなんとなく行く気になったので心配なことを聞いてみる。
「うーん…酒豪がいるからなぁ…僕から注意しておくよ」
ありがとうございます。とお礼を言って僕も立ち上がる。
「それじゃー今夜は宴だー!しゅっぱーつ!」
「今日は気を抜くんじゃなかったんですか?」
「宴だからね!元気にいかなきゃ!ほらきみも笑って笑って!」
まぁ楽しそうだからいいかな、なんて思いながら彼を見て笑う。
「適当に食べ物持っていくからきみも手伝って〜!」
そう言って彼は台所から酒の肴になるようなものを幾つも持ってくる。呑ませる気かな?
「それじゃ行こっか!」
彼があまりに元気に笑うものだから釣られて笑った。
今は心から笑っていてくれたらいいな、そう思いながら鼻歌を歌っている彼の背中を追いかけた。
〜Fin〜