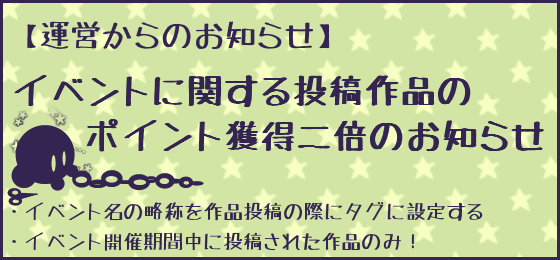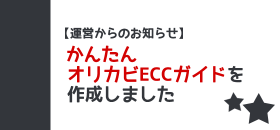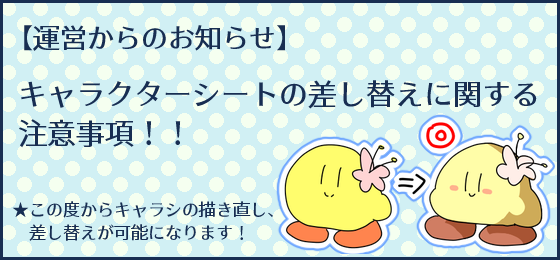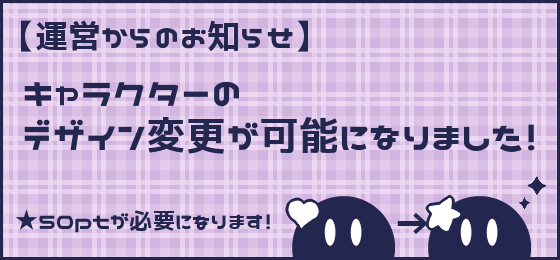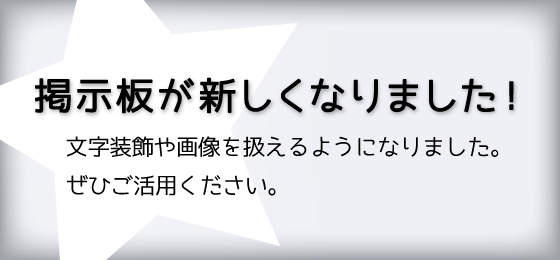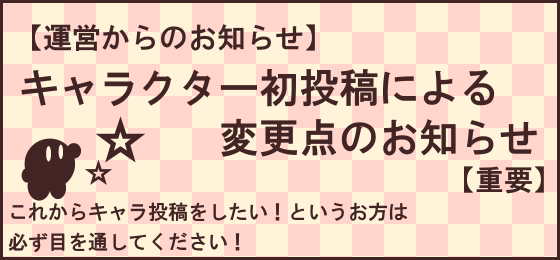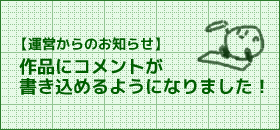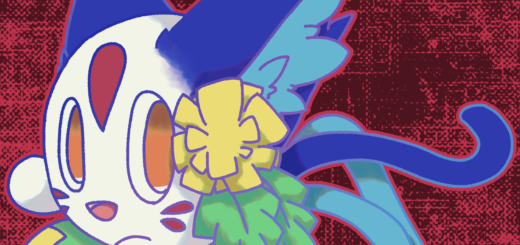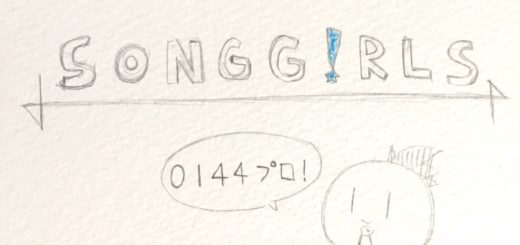ヤガスリでの日常小話。
□01 side詩飴
――ジリリリリ、目覚まし時計が鳴り響く。
「うわ……朝だ」
窓から差し込む日の光に目を細めつつ、ぼくはベルを止めた。
いつもと変わらず、のどかな矢絣の朝。
時計の短針は、数字の八を指している。
駄菓子屋の開店は九時だ、すぐに起きて支度を始めないと間に合わない。
しかし……どうも、布団から起き上がる気が起きない。
何故こんなに体がだるいのだろうと、昨日の記憶を辿ってみた。
「……そういえば昨日、黒鳶の家で、ご飯食べたような……」
一緒に来たトラマルと、水炊きの準備を手伝って……。
そしたら、八重が持ってきた瓶を開けて……。
瞬間、頭の中で八重の声が、彼女の笑顔と共に蘇った。
『え、酒、あんまり飲めないって? 大丈夫大丈夫、そんなに強くないのだから。とりあえず一杯飲みねぇ!』
飲んだ。
しかしそのあとの記憶がない。
「二日酔い……」
ため息を付いて、枕に顔を埋める。
自覚すると、一層頭痛が強まった気がした。
お酒の強さを、八重の基準で考えてはいけなかった……。
「うう、起きたくない……一日中お布団でごろごろしてたい……」
布団を被り直し、現実逃避に浸ろうとする。
今日は臨時休業、じゃだめかな。
いや、けど休んだら、経営が……。
そのとき、ピンポーンと、家のチャイムがなった。
「………………」
二度目のため息をつき、仕方なく布団から起き上がる。
あれ、帽子がない……まあいいや。
ふらふらしながら玄関へ向かい、横開きの扉を開けた。
「これ、表に落ちていたよ」
そう言って、見慣れたぼくの帽子を差し出したのは、かがみだった。
ああ、昨日の夜、家に帰ったときに落としてたんだ……。
「ありがとう、助かったよ」
帽子を受け取って、そのまま被る。
かがみは微笑んだ。……気がした。
なにせ、あまり表情がわからないやつだ。
(……表情、か……)
――そのとき、ある考えが閃いた。
「待って、かがみ!」
去ろうとするかがみを、慌てて引き留める。
不思議そうに見つめてくる彼に、ぼくは言った。
「ぼくの代わりに、今日一日、店番してくれない? ――顔をかすから」
□02 sideかがみ
「はい、お菓子だよ」
「ありがとう!」
袋を渡すと、その女の子は満面の笑みを浮かべ、友達と楽しげに帰っていった。
その子達が去ると、今駄菓子屋にいるのは、おれ一人になる。
一段落、ついたかな。
そう思って、詩飴がいつも座っている木の椅子に腰かけた。
ふと、横に置いてあった冷蔵庫が目に入る。
サイダーとかの飲み物が入った、懐かしい感じのする冷蔵庫だ。
そのガラスの扉に、自分の顔を映す。
そこには、水色の瞳と、黄色いからだがあった。
「店番って……どういうこと?」
帽子を拾って届けたら、突然の頼み事。
おれは思わず聞き返した。
詩飴は眠そうに目を擦りながら、
「ぼくが駄菓子屋やってるの、知ってるでしょ? そこでお菓子を売ってほしいの。お金のやり取りだけだから、難しくないよ」
「いや、別にいいけど……もしかして、病気なのかい? 顔色悪いし……」
「昨日……飲みすぎた……」
「なるほど」
了解して、詩飴の家に上がった。
「――まあ、そんな感じ。それじゃあよろしくね。何かあったら起こして」
「うん」
詩飴は店についての説明を簡単に話すと、布団に潜った。
「賃金はちゃんと払うからね。たぶんしばらく寝れば治る……」
そう言って帽子を取った。
「わかった。ゆっくりやすんでね」
――パシャリ
そうして、開店から二時間が経った。
誰にも怪しまれていないし、経営も上手くいっている。
それにおれは元々、子供が好きだ。
たまにこうやって詩飴の代わりをするのも、いいかもしれない……。
「駄菓子屋さん、お菓子をください」
またお客の声がして、冷蔵庫から目を外した。
「はい、何の……」
言いかけて、その人の姿を見て……おれは固まった。
茶色い帽子から猫の耳が見える、隻眼のその人は、
「甘いものがあると、執筆が捗るんですよ」
そう言いながら、お菓子を見比べていた。
□03 sideトラマル
執筆に行き詰まったので、少し外へ出ることにしました。
今日は晴天、昼時の町は活気づいています。
「お菓子でも買いに行きましょうか」
駄菓子屋さんの様子も、ちょっと気になりますし。
……というのも、昨日は町長さんの家で、ご飯をごちそうになりました。
その際、駄菓子屋さんは副町長さんが持ってきたお酒を飲んで、ずいぶん酔われていたみたいなので……。
家まで送っていきましょうか、と言ったら「大丈夫☆」とウインクされましたし、明らかに大丈夫じゃなさそうだったので、ちゃんと家へ帰ることができたのか少し心配です。
それに、道中にかがみさんがいらっしゃるかもしれません!!
不思議の塊かがみさんにはお聞きしたいことが山ほどあります! 原稿用紙五十枚分はあります。
次に見つけることができたら、絶対に逃がしません……!
しかし道中、かがみさんには会うことはできませんでした。
駄菓子屋店主の彼は相変わらず、ぼーっと宙を見ています。
あら、元気そうじゃないですか。
僕は店に入って、彼に微笑みました。
「駄菓子屋さん、お菓子をください」
□04 sideかがみ
名前は……トラマル、って言っていたかな。
おれの姿を見ると、「ぜひ!! 話を聞かせてください!!」と、目を輝かせて紙とペンを用意し始める、変わった人だ。
確か、伝承作家とかなんとか……なんでもいいけど、取材はお断りだ。
もしトラマルがおれのことを記事にしたら、それを読んだ人が路地裏へ来るかもしれない。
そんなことになったら、今までのような静かにひっそりした暮らしが、できなくなる……。
(けど、今のおれは駄菓子屋だ)
トラマルから代金を受け取りながら、考える。
顔もコピーしている、無駄なことを話さなければ、バレることはないだろう。
そう思い直して、安心した。
「そう言えば、昨日はあのあとどうなりました?」
「………………」
……のも、束の間。
早速、返答に困る話題を振られた。
こんな、本人にしか答えられないような言い方は、卑怯だぞ……!
そう思いながらも冷静を保ち、とぼけたように、トラマルを見つめた。
「昨日って?」
「あれ、記憶がないんですか? まあ、酔われてましたもんね」
「……うん……」
曖昧に答える。
トラマルは特に気にならなかったようで、お菓子に視線を戻した。
ああ、早く帰ってくれないかな……。
それに、このタイミングで詩飴が起きてきたらどうしよう。
気が気でない思いで、ちらりとトラマルの方を見る。
と、いつの間にか彼女は、じっとおれを見つめていた。
「……何か用かい?」
「いえ、何か違和感が……何でしょうか」
うーん、と口に手を当てるトラマルに、どっと冷や汗が流れる。
いや、まさか……おれは完璧に化けているはずだし……。
トラマルは少し考えて、そしてぽんと手をうった。
「あ、そうだ、シャボン玉ですよ。いつもストローをくわえているじゃないですか」
……確かに、詩飴はよくシャボン玉を吹いてた気がする。
「あれ、無くされたんですか?」
「う、うん、そう、無くした。だから今日はできないかな……」
さすがに能力まではコピーできない。
よかった、ストローがなくて……。
「あれ、ここにあるの違うんですか?」
「………………」
なんであるんだ!
トラマルが示した窓際を見て、頭を抱えそうになる。
「いや、あれはその……違う人のだから……」
必死に思考を巡らせ、言い訳を呟いた。
「違う人の?」
「そう、違う人の」
「へぇ、誰のですか?」
「えー、あー、おれの叔父さんの……」
そう答えたら、トラマルは不思議そうに目を瞬かせた。
「ん? 『おれ』?」
「……あ」
しまった。
詩飴は自分のことを、おれとは言わない。
トラマルの目が、疑惑の色に変わる。
このままだと、偽物だとばれるのも、時間の問題だ。
(どうする……どうする?)
考えに考えて……そして答えを導きだした。
唐突に、椅子から立ち上がる。
トラマルが何か言う前に、
「ごめん、用事を思い出した。ちょっと店を開けるから、店番よろしく」
そう言い残し、逃げるように店を出た。
というか、逃げた。
□05 side司
うわああ、遅れるー!
あたしは今、坂道を全速力で走っていた。
向かう場所は、商店街の入り口。
今日は、色葉ちゃんと一緒に遊ぶ約束をしていた。ワクワクしすぎて五時に目が覚めた。
顔を洗って、朝ごはんを食べて……そして、思わぬ問題にぶち当たった。
「こういうときって……どんな服を着ていけばいいんだ?」
たんすの前で固まる。
可愛いお店に行くのに、いつもの動きやすい服装でいいのだろうか?
家には父が勝手に買った豪華な着物があるけど……そういうのを着た方がいいのか?
いや、それもなんか違う気がする……!
……と、悩んでいたら、いつの間にか二時間経っていた。
「ああっ、もういいや、いつもので……!」
そう思って五分で支度し、慌てて家を飛び出したのだった。
坂道をのぼりきると、今度は下り坂。
花の匂いがまざる春の風が心地よい。
転けないように走っていると、突然ある人に声をかけられた。
「あら、司ちゃん、そんなに走ってどうしたの?」
「え? あっ、八重姐さん!」
足を止めて振り返ると、そこには八重姐さんの姿があった。
隣に黒鳶くんと、知らない女の子もいる。
どうして二人がここにいるのか不思議に思い、一瞬、急いでいたことを忘れた。
「何か、あったのか?」
そう聞くと、黒鳶くんが深刻な表情で答えた。
「実は、この子の鞄がスリにとられちゃったみたいで」
黒鳶くんの隣を見ると、猫のような形の緑色の帽子を被った女の子がいた。
女の子は、そのオレンジ色の瞳をうるうるさせて、
「ななはの鞄が、とられちゃったのです……一緒に着てたお姉ちゃんは、男の人を追いかけて、そのままはぐれちゃって……」
そこまで言って、ななはというその女の子は耐えきれず、涙をぽろぽろ流し始めた。
八重姐さんがよしよしと慰め、ハンカチでななはの涙を優しく拭う。
あたしはそんな姿を見て、犯人に対する怒りが、ふつふつと沸き上がっていた。
こんなか弱い女の子を傷つけるなんて、許せない……!
「犯人はどんなやつなんだ?」
聞くと、黒鳶くんが女の子から目を離し、
「黒い帽子を被ってる男だって」
「……黒鳶くん?」
「ち、違うよ……? とにかく、ななはちゃんの黄色いハート型の鞄を持ってる人を探せば、間違いない」
黄色い、ハート型の鞄……。
すると、ななはちゃんは顔をあげ、こちらを見た。
「今日、この街に着て、アクセサリー屋さんで買ったのです……お姉ちゃんとお揃いで……」
そう言って、また顔をハンカチに埋める。
その様子を見て、心に決めた。
あたしが絶対、犯人を捕まえてやる……!
そんなとき、ふと八重姐さんがこちらを振り返った。
「ところで司ちゃん、走っていたけど、急いでいたんじゃないの?」
「へ? ――ああーーっ!!」
そこでやっと、色葉ちゃんとの約束を思い出した。
同時に、街に不審者がいるこの状況で、色葉ちゃんを一人で待たせることがとても不安になる。
「いっけない、約束があったんだった! ごめん、犯人見つけたら、絶対こてんぱんにしとくから!」
そう言い残し、急いで商店街へ向かった。
□06 side色葉
「良い天気やなぁ~」
屋根の陰から、青の眩しい空を見上げる。
今日は喫茶店は定休日、だから仕事もお休み。
せやから司ちゃんと、遊ぶ約束したんよ。
最近できたパフェのお店に、アクセサリーショップに……ふふ、楽しみやなあ。
「……にしても、司ちゃん、来んへんなぁ~」
心を踊らせる反面、約束の時間から既に十五分過ぎた時計を見て、少し心配になる。
何かあったんやろか……司ちゃんは約束を破るような子やないし。
病気になったのかも、家に行ってみよか?
「けど、すれ違いになるかもしれん……」
うーんと、自問自答を繰り返しながら、ただ親友を待つ。
――そうしていると突然、右手側から子供の泣き声が聞こえてきた。
「うわああああん! お兄ちゃんが……お兄ちゃんがああ!」
「お前、何で泣くんだよ! 俺が何かしたか?!」
「ち、違うの、だって顔が……顔が……あれ?」
「…………?」
すると今度は、正面から叫び声が聞こえた。
「ひいいっ?! おおお化けだー!!」
「はあ? あんた、彼女の顔見てそれはないんじゃないの?」
「だ、だって君――あ、あれ? おかしいなあ、確かにさっきは……」
「一体、何が……?」
そのあとも、あちこちで叫び声が聞こえて……なんだか、穏やかやない……。
すると今度は、私の隣に立っていた女の人が、悲鳴をあげた。
「あっ、アナタ! 顔どうしたの?!」
「えっ、何が……」
「のっぺらぼうになっているわよ!」
「……のっぺらぼう?」
少し心当たりを感じて、辺りを見渡す。
そのとき、ある声が耳に飛び込んできた。
「かがみさーん!! どこですかーー!! 逃げないでぜひお話をお聞かせくださいーーー!!!」
そう大声で呼び掛けながら通りを走っているのは、トラマルはんや。
……あ、私、わかったかも。
隣の細い道を覗くとそこには、知らない男の人がいた。
さっき、私の隣で叫んでいた女の人と、一緒にいた人だ。
「かがみはんやろ?」
男の人--もといかがみはんは、びくりとして振り返る。
しかし声の主が私だと分かると、安堵のため息をついた。
「ああ……きみは……」
「どないしたん? トラマルはんに見つかりたくないん?」
「うん……勘づかれて、追いかけられてて……だからやむを得ず、通行人の顔を『かり』ながら、逃げてた」
やっぱり。
せやから、通りがあんな風になってたんやなぁ。
そう納得していると、トラマルさんの「どこですかーーかがみさーーん!!」という声が近づいてくる。
後ずさるかがみさんに、私は微笑んだ。
「いつもの姿で、逃げてええよ。『かりられた』人も困るやろし……トラマルはんには私が上手く言うとくから」
「ほんとに?……ありがとう」
かがみはんはそう言って、元の姿に戻って……ニコッと笑った。
帰り際、かがみはんは思い出したように付け加えた。
「あっ、もしよかったら……駄菓子屋に行って、詩飴を起こしてくれないかい? ほんとは詩飴の代わりをしてたんだ」
「うん、了解」
うなずくと、かがみはんは路地裏の細道を走っていった。
角を曲がったのを確認して、通りの方を向き直る。
すると、走ってきたトラマルさんと、目があった。
「あ、色葉さん。この辺りにかがみさんが来ませんでしたか?」
「ううん、誰も来てへん」
「そうですか……一体どこへ消えたんでしょう」
トラマルはんは独り言を呟きながら、元来た道を歩いていった。
ちょっとの罪悪感を感じながら、彼女の背中を見つめる。
トラマルはんのことは好きやし、協力もしてあげたいけど……やっぱりかがみはんには、ずっとこの街にいてほしい。
ぼんやりとそんなことを考えていると、「色葉ちゃん!」と、突然呼び掛けられた。
「へ? あっ、司ちゃん!」
司ちゃんは息を切らして、
「ごめん、ほんとごめん、遅くなった……!」
「ううん、大丈夫! なにかあったん?」
「ええと、なんていうか……それより、色葉ちゃんはなんともなかった?!」
「え?」
突然手をとった司ちゃんに、私は戸惑う。
「不審者がうろついてるって、さっき聞いてさ。あたし心配で……」
「不審者?」
……かがみはんのことやろか?
「ああ、それなら解決したみたいよ」
「え?そうなの?」
「うん」
微笑むと、司ちゃんもほっとしたように笑った。
「なんだ、よかった。それじゃあ行くか」
「その前に駄菓子屋によってもええ?」
「うん、いいよー」
話しながら、商店街の道を二人で歩いた。
(後半へ続く)