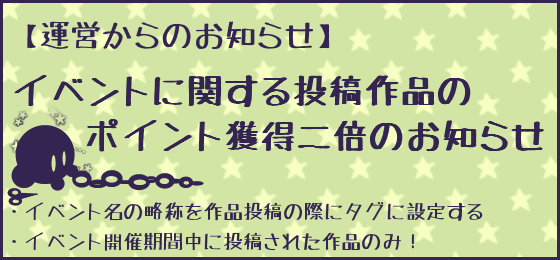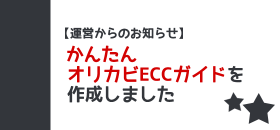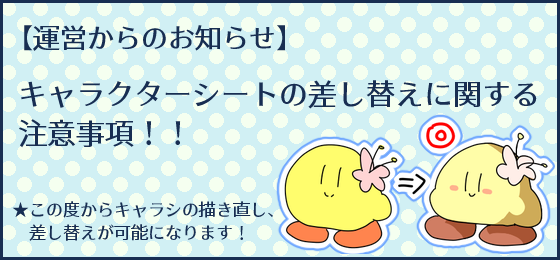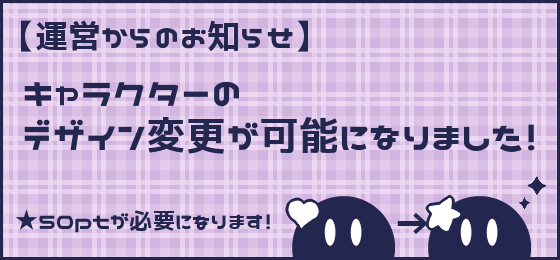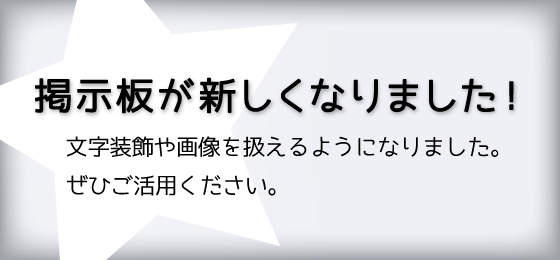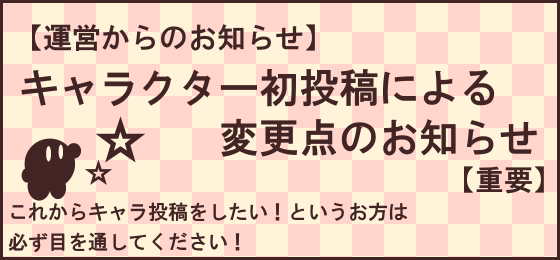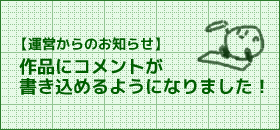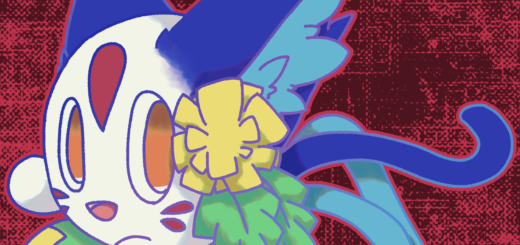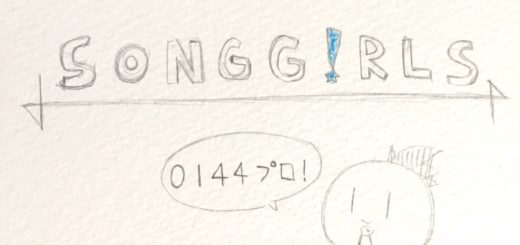「…って事があったんだよ」
「ほほう。それはあんたらも大変だったねえ」
「……まあね」
つぎはぎだらけのおばあちゃんに同情の言葉をかけられたアスタは、軽く相槌をうつ。
話を聞いたおばあちゃんはスクリと立ち上がると、後方に向かって手招きをする。
すると焦げ茶色のニット帽を被った男の人がのそのそと歩いてやってきた。
「なんだよ、何か用か?」
「あんた、この前手に入れたさつまいも残してるだろ?出しな」
「ええ⁈さ、さつまいもなんて知らないなぁ…」
そう言いながらその人は視線を外し口笛を吹き始めるが、その態度を見たおばあちゃんが声を上げる。
「なんだいその態度は!あたしはね、あんたがこの前みんなでさつまいもを取りにいった時に1人だけ余分に取ってたのを知ってるんだよ!!」
「ぐっ⁈み、見間違えじゃねえか…?」
「じゃあなんでそんなに汗だくなんだい?テフラプ…」
「ひいぃ!」
的確に的を射抜かれたテフラプという名前のその人は、空中でバク転をしたのち土下座の体勢で地面へと着地する。
「ゆ、許してくれヒルダ!こっちだってあんなにさつまいもがあったら我慢できな…」
「いいから4人分持ってくる!急ぎな!!」
「わ、分かった!!」
ヒルダと呼ばれたおばあちゃんに喝を入れられたテフラプは、大急ぎで西の方へと駆けていった。
残されたぼくとアスタとヒルダおばあちゃんの3人は、互いに顔を合わせながらテフラプが戻ってくるのを待つ。
しかしいくら経っても姿を現さないので、そのうち痺れを切らしたヒルダおばあちゃんが口を開いた。
「そういえばまだ名前を聞いてなかったねえ。あたしゃヒルダ。ここでのんびり暮らしてるババアだよ」
「ぼくはちひろ。横でジッと見つめて微動だにしないのがアスタ!」
「ちひろちゃんにアスタちゃんだねえ。悪いね、折角寄ってくれたのに出迎えがあたしとテフラプだけで」
「ううん、お構いなく」
「悪いけどもう少しだけ待ってな。今テフラプが戻ってきたら焼きいもをやるからさ。はあ…他の子たちも寝なければ今頃は焼きいも焼きいもってはしゃいでいたんだろうけどねえ……」
ヒルダおばあちゃんは寂しそうな顔で遠くを見つめる。
ぼくもつられて周りの景色を眺めるけど辺りは瓦礫だらけで薄暗く、これといって目を引くような物はない。
唯一気になるものといえば、周りを徘徊しているゾンビ達かな。ここを通るとアスタが言った時は本当に驚いて襲われるんじゃないかと思ったけど、動きも遅いし襲われる前にヒルダおばあちゃんに会えたからなんとか助かった。
そう、ここはフクレセウ。大昔に戦争か何かあって滅んだ国…らしい。ヒルダおばあちゃんの話では、戦争を起こす前は様々な魔法が出回る国家都市で、面白いものもたくさんあったみたい。その反面、あんまり良くない噂も多かったみたいだけど。
今ではその名残なのか、ちらほらと怪しげな液体が水たまりのように溜まっている箇所が目に付いた。
そんな事を考えてテフラプの帰りを待っていたけど、やはりどれだけ待っても姿を現そうとしない。
流石に他の2人もその事に勘付いたのか、互いに険悪な顔を浮かべてただ一点を見つめていた。
もしかして…と思いつつ、ここに来る前に立ち寄ったビルレスト大橋の事を思い返した−
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「…ここがビルレスト大橋か」
「予想してたよりも大きいね」
メカノアートから延々と歩き続けておおよそ3時間。メカノアートを出たのが正午くらいだったから、本当ならおやつを食べている頃だ。
ビルレスト大橋は遠目から見てもあれがそうかな?というくらいにとても分かりやすく、巨大な建造物だった。
実際近くまで来て目の当たりにしてみると、その大きさがよく分かる。高さは10階建ての高層ビルに並び、真っ白なコンクリートには所々黒い汚れのようなものが目立つ。パッと見た風貌はお城のような感じかな。
アスタと共に飲み込まれてしまいそうなほど大きな門を潜り抜け階段を天辺まで上り詰めると、目の前には先が見えないほどの直線的な道がただひたすらに伸びていた。
見たことのない異様な光景に興奮して橋から身を乗り出し下を覗き見ると、日の光をキラキラと反射させながら緩やかに流れる川がこれまた先の見えないほどに続いていた。
「すごいよアスタ!先の見えない川、そして橋に見渡す限りの広がった景色!なんだか自然の一部になったみたいだ!!」
「…そう それよりこれ…どうするんだっけ?」
「あ、その四角いやつかー。えっーと、確かその下のボタンを押すんじゃなかったっけ?」
「…これ?」
疑問符を浮かべたままアスタが丸くくぼんだボタンをカチッと押し込むと、四角い箱の中央部が明るくなり中から青い光と共にポリツィアが現れた。
ポリツィアはすぐさま目を開き周囲を確認すると、ぼく達の目を見て口を開く。
「どうやら無事辿り着けたようですね」
「…まあね」
「では参りましょうか。まずは建物内部のどこかにある無線通信機器を探してください」
「無線通信機器って?」
「…とりあえず入ってください。ここでは電波が拾えないので」
電波?無線通信機器?うーん、よく分からないけど、とにかく中に入れと言われたし戻ろう。
ぼくとアスタはポリツィアに言われた通り建造物の中へ入るため、階段横の通路を進みガラス板が貼られた少し洒落た感じのドアを引き中へと踏み入る。
中は開けた空間となっていって、天井から吊るされたシャンデリアから差す光が辺りを美しく照らし出す。
でも……
「誰もいない…?」
目の前のカウンターには呼び出し用のベルがポツンと置いてあるけど、周囲は静まり返り押してみても誰かが来るような雰囲気は微塵もなかった。
この状況を飲み込んだのか、アスタは苦虫を噛み潰したような顔で口を開く。
「どうやらここの人達も起きてはいないみたいだね…」
「みんな寝てしまっているってこと…かな」
「そういうことだね」
嫌な予感はしてたけど、やっぱりそういうことなんだ…
ぼくは近くにあったソファーに腰掛けると、真っ赤なじゅうたんへと視線を落とす。
もう…この世界には数えられるほどの人しか起きている者がいないのかもしれない。また皆で笑い合える日々は戻ってこないのかもしれない。
そう思うだけで涙を流しそうになる。自分だけが取り残されたような気がして…
「ねえ」
ふいに掛けられた声に反応して顔を上げると、アスタがぼくのことをジッと見つめていた。
何か返事を返さなきゃと思うけど、言葉が詰まって声にならない。
「いや…何も言わなくていい ただこれの返事に困ってね」
「これとは何ですか。随分と失礼な事を言いますね」
「これ…で何か間違った?」
「確かにデバイス自体はそう呼んでも構いませんが…まあいいでしょう。それよりも、電波を無事拾えました」
「それは良かった …それで?」
「ここのデータを参照したところ、どうやら新しく導入したシステムのコントロールは最上階に存在するようです。ですので最上階に向かってください」
「…だそうだ そんなところで悩んでいるくらいなら…動いた方がいいんじゃない?」
そう言うとアスタは背を向け上へと上がる階段を探し始める。
…気づかれちゃったか。
ぼくはゆっくりとソファから離れると、遠ざかっていた背中を追いかける。
「待って!ぼくも行く…!」
「…そう」
アスタは一言だけそう呟くと、真っ直ぐに進み始める。
ぼくはその後を決してはぐれないように追いかける。
そんな光景が今のぼく達の関係なのかなって思っていると、突然耳を裂くような騒がしいサイレンの音が部屋中に響きわたってきた。これは…?
「なに…?」
「分からないよ!ぼくにも何が何だか!!」
「マズイですね…」
「え?」
そう言うとポリツィアは目を閉じ2、3秒沈黙すると、頭上に大きな矢印を表示させる。
「今ここの地図を参照させて貰いました。最上階までは私が案内しますので、急いで上へと向かってください」
「急いで…⁈ なっ…!」
「何、あの煙⁈なんなの⁈」
「消火用の煙…と思いたいですが、あれは恐らく催眠ガスです」
「催眠ガス…? それってマズイんじゃ…」
「ええ。ですから急いで」
淡々と話を続けるポリツィアだったけど、その声は次第に早口になりつつあるのがぼくにも分かった。ということは本当にやばいってことだ…!
ぼくとアスタは互いに頷くと、ポリツィアの差す方向へと走り出す。眠ってしまったらアウトな現状の中、催眠ガスなんて吸ってしまったら最後だ。
エントランスから伸びるじゅうたんを辿り…行き止まりへと差し掛かると、右へと切り返しそのまた行き止まりを左へと切り返す。すると目の前に上へと続く階段が現れた。
ぼくらはその階段を急いで駆け上がり、1つ上の階へと足をつけると予想していなかった光景に目を疑った。
「はあはあ…先へと続く階段が…ない?」
「なんで…⁈」
周囲を見渡しても見つからない階段に、足を止められて焦り始める。でもそうこうしてる間にも催眠ガスは徐々にぼくらの元へと忍び寄ってきている。
するとその様子を見ていたポリツィアが口を開いた。
「このまま真っ直ぐ廊下を進んでください」
「え…⁈」
「この建物はもしも凶悪な人達に乗っ取られてしまった…というような非常時が起こっても大丈夫なように、あえて階段を別々に配置してあるようです。ですから各階ごとに走ることになりますが、それだけでは…」
「ん?今度は何の音⁈」
「来てしまいましたか…」
ガゴンッと何かが外れたような音がしたかと思うと、先へと続く廊下の天井から何やら壁のような物が降りてきた。今度は一体…?
「あれは…?」
「あれが今回試作として新導入したシャッターです。本来は緊急時にのみ閉じるものですが…とにかくあれが閉じ切る前に最上階へと急いでください」
「そういうことか 走るぞ…ちひろ」
「うん!!」
すでに足元へと伸びていた煙を払いのけ、ブザー音の響く廊下を一直線に走り抜ける。
幸いにもシャッターの閉じる速度は遅く、楽に通り抜けることができた。だけど…
「大丈夫アスタ…⁈」
「はあ…はあ……」
次の階へと上り詰めた段階で、アスタが息を切らし始めていた。本人は隠しているつもりかも知れないけど、苦しい顔を見せまいとしているのが見て分かる。
それでも必死に走り続けるが、この階の最後のシャッターを潜り抜けた辺りで、アスタの走る速度は愕然と落ちきってしまっていた。
…このままじゃ最上階までは持ちそうにない。こうなったら…!
「……⁈ ちひろ、何を…」
「いいから掴まって!ここから先はぼくが…最上階まできみを届ける!!」
「無茶だ…ボクを背負って登るなんて…」
「それでもやるんだ!無茶なんかじゃない…それを教えてくれたのはアスタ……きみなんだから」
「……」
ぼくは自分の思いを言い切ると、アスタを背負い全速力で次の階へと足を進める。
自慢じゃないけど、これでも足には自信がある。ただ問題は最上階まで体力が持つかどうか…
「うぐっ…シャッターが!」
ふと前を注視すると、2個先のシャッターがもうすでに閉まりかけていた。
このままでは間に合わない。
仕方ない、これをやるしか…!
「しんそくッ!!!」
そう叫んだ瞬間、視界に映る景色が今まで以上に廻まじく変化してゆく。
しんそくの効果は3分。それまでに最上階へ辿りつけなければ、ぼくらの旅はここでお終い。いや、絶対に終わらせない!!
閉じかけたシャッターをギリギリで通過し、ただただポリツィアに指示された方向へと地を蹴る。
そして疲労で限界が見え始めた頃…最後の一段を上がり最上階へと辿りついた。
「あれだね…‼︎」
コントロール室と書かれたプレートをぶら下げるドアを見つけると、最後の力を振り絞り部屋の中へと飛び込んだ。
「いつッ!!」
「後は任せろ…!」
入った後のことを考えていなかったぼくに代わってアスタが背中から離れると、背後のドアを閉じた。
「はあ、はあ…間に合った…?」
「ああ ちひろのおかけだ」
「そっか…えへへ」
「でもまだ安心は出来ないみたいだね」
「う…?」
アスタの言葉が引っかかり、息を切らしながらも顔を上げると青いサンバイザーを被った人が、虚ろな瞳をこちらに向け立っていた。
何故ここに人がいるのかは分からない。でも思考よりも先に体が嫌な気を感じ取っていた。信じたくはないけど、この感じは…!
「アスタ!」
「分かってる!2撃で終わらせる!!」
アスタは叫びながら相手が動くよりも速く懐へと潜り込むと、軽いアッパーを喰らわせる。するとその人の中から黒いもやのようなもの…つまりダークマターが浮き出てきた。
当然それをアスタが逃すわけもなく、そのまま空中で切り返しながらキツイ回し蹴りを一発お見舞いすると、そのダークマターは音もなく消滅した。
「よし…終わった」
「さ、流石だね」
「これくらいはできて当然… おいアンタ大丈夫か?」
「んん…?ハッ!ここは⁈」
「どうやら気がついたみたいだね」
アスタに殴られたその人は意識を取り戻すと、何が起こったのか分からないといった顔でこちらを見つめていた。
殴っておいて知らんぷりというわけにはいかなかったのか、アスタの方から手を差し伸べると、その人は今だ飲み込めない表情で手を取った。
とりあえず大丈夫そうな事を確認しホッとしていると、いつの間にか姿を見せていたポリツィアが口を開く。
「貴方、確かメカノアートの住民ですね?個体名称はロイド」
「ポリツィア⁈って事は…」
「そうです。予定通りここのシステムのチェックに来ました。ところで何故貴方がここにいるのですか?」
「えっとだな…実は試験運用を頼まれてたハヤトのやつが寝たまま起きなくなってしまってさ…仕方ないからおれが来たんだ。でもいつの間にか気を失ってしまっててな…」
「それはおそらくダークマターに不意を突かれて意識と体を乗っ取られたんだろう そのせいでここに来るまでに妨害を受けて酷い目に遭ったけど」
「そうなのか⁈それはすまない事をしたな…」
「その話はもういいでしょう。それよりも予定通りシステムのチェックを行いますよ。担当者が違いますが、ケースバイケースです」
「分かった。元々おれもそのつもりで来たからな」
そう言うと2人は箱のような形をした機械をせわしなく弄り始めた。機械の事はまるでよく分からないけど、ガチャガチャと内部を弄り回してるのを邪魔するのも悪いだろうし、部屋の隅の方で大人しくしていよう。
それから数十分経ったくらいかな。一段落ついたのかポリツィアがぼくらの方へと振り向いて声をかけてきた。
「お2人とも、ここまで運んでくれたこと、感謝します」
「いやいや、夢の泉へ行くついでだったし、別にお礼なんて…」
「いえ、私1人では来られませんでしたからね。ですが…もう十分です。ここからは私を置いて先に行ってください」
「…え?でも…」
「心配はいりません。私はあくまでもここに用があっただけですし、帰りの事ならロイドがいるので問題ありません」
「という事らしいから、お前たちは外に行きな。ここには緊急脱出用のロープがあるからそれで降りられるしな」
「アスタ…」
「ここはそうさせてもらおう ここにいる意味もない」
アスタは立ち上がりながらそう言うと、緊急脱出用のロープを見つけ出し窓からそれを垂らして1人でそそくさと下へ降りて行ってしまった。
なんともあっさりと行ってしまったなぁ…と思いながらも後に続いて同じようにロープを握ると、手を振ってくれていたロイドに手を振り返し、真っ直ぐ下へと降りていった…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「…ダメだ これ以上は待てない」
「アスタ…?」
ビルレスト大橋での出来事を思い出し終えたのと同時に、アスタが小さく呟いた。
それがどういう意味なのか分からなかったぼくはアスタに問いかける。
「どういうこと…?」
「ボク達には時間がない それに…おそらく彼は…」
うつむいたままのアスタはそう答える。
ぼくだってそんな気はしてた。もしかしたらダークマターに襲われてるんじゃないかって。でもヒルダおばあちゃんがいる前でそんな事、口が裂けても言えないよ…
「じゃあ…ボク達はもう行くから」
「……」
アスタが立ち上がるのに合わせてぼくも足に力を入れようとした…その時だった。
見覚えのあるニット帽が砂埃を巻き上げながら目の前を過ぎ去る。
…いや、違う。今目の前を通り過ぎて行ったのは……!
「テフラプッ!!」
叫んだ先には地面をえぐりながら建物の残骸の一角に突っ込んだテフラプが苦しそうな声を漏らして背もたれていた。
気がつくとぼくが駆けつけるよりも早くテフラプの元へヒルダおばあちゃんが駆け寄っていた。
テフラプの苦しそうな顔を見たヒルダおばあちゃんは大きく口を開く。
「何をしているんだい、あんたは!」
「はは…すまねえ、ヒルダ。焼きいもどころじゃ…なくなっちまった」
「焼きいもなんていいんだよ!誰だい、あんたを吹っ飛ばしたやつは!」
ヒルダおばあちゃんの問いかけにテフラプがスッと腕を突き出すと、ぼくらは一斉にテフラプが指した方角を向く。
すると初めこそ何もないグラデーションのかかった夕暮れの空に、徐々に数十の黒い点がポツポツと映り始めた。
「やっぱりダークマター…‼︎」
とうとうゾンビだらけのこの街にもあいつらの魔の手が…!
ぼくはいつでも戦闘を始められるように構えながらアスタへと声をかける。
「アスタ、あいつらが…!」
「…分かってる 襲われた以上やるしか…」
「待ちな!!!」
「……!!」
背後からの急な怒声に一瞬ビクつきながらも振り向くと、鋭い眼差しで錆びついた剣を強く握りしめたヒルダおばあちゃんがこちらにゆっくりと近づいてきていた。
ヒルダおばあちゃんはぼくとアスタの頭をポンッと叩くと、ぼくらよりも一歩だけ前に出て呟く。
「アスタちゃん、ちひろちゃん。あんた達は戦わなくていい」
「え…⁈何を言って」
「あんた達にはやるべき事があるんじゃないのかい?」
「それは…」
「なら、その上げかけた拳はその時まで取っておきな。この街に無断で入ってきたあいつらには、あたしが喝を入れておくからさ」
「…アンタ1人でか? あの数相手にそれは無謀だ」
「煩いねえ。年寄りの言うことは黙って聞くもんだよ!さ、早く回れ右して夢の泉とやらに行きな!!」
ヒルダおばあちゃんは最後にそう言い残すと、真っ暗な空へと単身乗り込んで行ってしまった。
「……ぐっ!!」
ぼくは自分の頬を固い握りこぶしで思い切り殴ると、もう一度前を見つめることなく踵を返す。
またブレるところだった。でも、決めたんだ。もうブレないって。みんなのために戦うんだって。
足元に薄っすらと伸びる自分の影へと力強く踏み出すと、ただ一点へと視線を向けるテフラプの横を通り過ぎ…走り出す。
「アスタ!!」
「ああ…行こう、夢の泉へ…‼︎」
ぼくはアスタに歩幅を合わせつつ彼の方へ視線を向ける。
一瞬だけ目と目が合うと、目を閉じまた…開く。
アーク、ロイド、ヒルダおばあちゃん、そしてアートアンサンブルを始めとした夢の世界へと囚われてしまったみんな……
待ってて。必ず、ぼくらが目を覚ましてあげるから……!!
つづく。