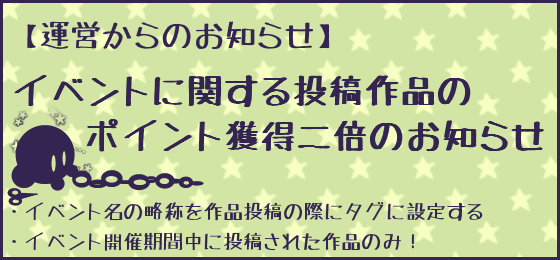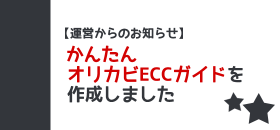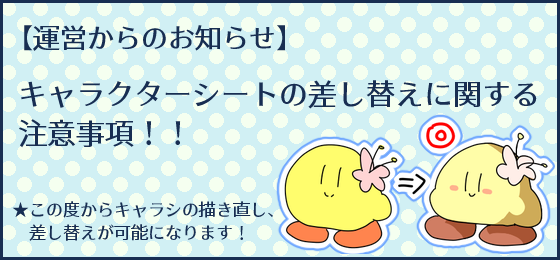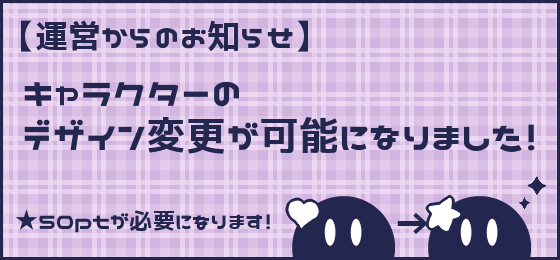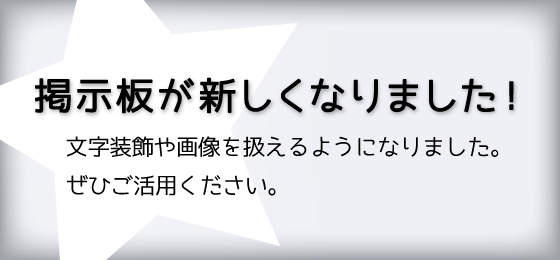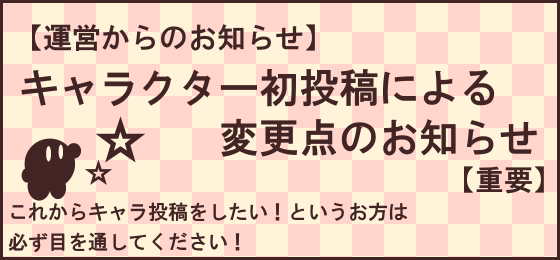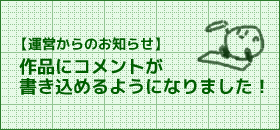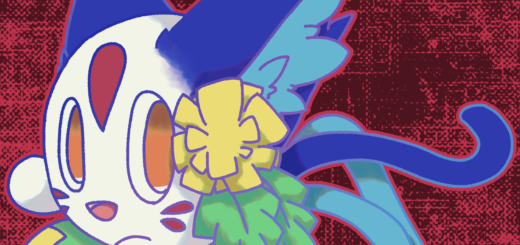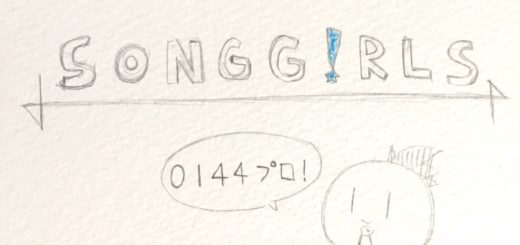「ねえ、ここってビルレスト大橋ってところじゃないよね?一体どこなの?」
「あー?見りゃ分かるだろ。雲の上だよ。雲の上!」
「それは見て分かるけどー、寄り道していいの?」
「構わない。むしろここで一度休んでおくべきだ。特にお前ら2人は気づいてないかもしれないが、暗黒物質の因子に少しながら侵されている」
「あら、そんなことが分かるのですか?」
「……!!あ、あれだ!乙女の勘ってやつだ!」
「リゼさんは乙女って感じには見えませんけど」
「そ、それもそうだな!あは…あはははは……」
あたしはなんとか誤魔化そうと、ぎこちない笑みを浮かべる。
あっぶねぇー!!
危うくテールの事がバレるところだったー!!
テールはダークマターの一種だからな。もしこんな時にバレたりなんかしたら、何を言われるか分かったもんじゃないぜ……
あたしは冷や汗をかきながらもなんとか誤魔化しきると、今晩泊まれるところを探すため下へと降りる階段を探す。
しかし、ざっと辺りを見回しても見つからなかったので広場から飛行船乗り場に戻ろうとすると、横にいたトアが不意に話しかけてきた。
「そういえば、結局ここってどこなの?街……なの?」
「そうだけど?ここはシエルヴィル。雲の上に浮かぶ小さな街だ」
「リゼさんはここに来たことってあるの?」
「知ってはいたが、実際に訪れるのは今回が初めてだ。まず来ようとも思わねえしな」
「そうなんだー」
トアは分かったような顔をすると、うんうんと頷く。
あたしも街の名前こそは知ってるものの、噂に聞く程度で存在するかすらも怪しい街だった。
だがまさか偶然にも飛行船を見つけるとは思ってなかった。
おそらくどの街もダークマターどもに襲われてる事を考えれば、平然と飛行船を出してるこの街はいくらか安全だということだ。
しかし安心はできない。いつここも襲われるか分からないし、場所が場所なだけに移動するなら襲われる前のがいい。何せ逃げ場がないからな、ここは。
「それにしても、ここは下さえ覗かなければ地上とさほど変わらねえな」
「そうですねぇ。あ、あれが階段では?」
「お、なんかそうっぽいな」
ノッテが指す方向に階段らしきものを見つけると、あたし達は下へと降りてゆく。
飛行船内での案内放送で聞いた話によると、シエルヴィルは3階建ての構造で、その1,2階が店舗エリアになっているらしい。
宿屋もその階にあると言っていたから、その辺をうろうろしてれば泊まる場所も決まるだろ。
階段を降り2階に到達すると、あたし達はそこで一旦解散することにした。なんでもトアとノッテはこの街の観光と買い物をしたいらしい。全く、気楽なもんだ。
あたしは2人と別れると、今晩泊まれる所を探し始めた。泊まると言っても、なるべく安い所のがいい。
そして探すこと1時間。
大体の目星を付け泊まる所を決めていると、いつの間にか誰かの足がすぐ目の前で止まっていた。
ふと視線を上へと向けると、全体的に真っ黒で緑色の瞳をした怪しげなやつと、黄色い体に白い羽根を生やしたやつがこちらを見つめていた。
ただ見つめているだけで何も言わないので、こちらから声をかけてみる。
「なんだお前ら。あたしに何か用か?」
「あの、私はここの住民のハノという、者ですが……観光客の方ですか?」
「あ?まあそんなところだけど、それが何か?」
「いえ、その、もしよろしければこの街の御案内をさせて頂こうかと……」
「いらねえ。どっか行ってくれ」
「ええ?そうですか……」
「で、そっちのお前は?」
「あ!おいらはテティって言うんだぁ。きみ、他所の人なんでしょぉ?是非とも外の街の話でも聞かせて欲しいなぁなんて……」
「断る。あたしは忙しいんだ。他を当たれ他を」
「えぇー!!」
と、まあそんな感じで軽く振り払おうとしたが、2人はどこかに行く素振りすら見せない。
むしろ先ほどよりもグイグイと攻め入ってくる。迷惑な話だ。
2人がなんか色々と語りかけてくるのに苛立ってきたあたしは、すっと立ち上がると踵を返して店々が立ち並ぶストリートを歩き始めた。
「あ、待ってください。どこかに行くなら案内を」
「だからいらねえって」
「じゃあ外の世界の話を聞かせ…..」
「だから話さないっての!しつこいなお前ら!!」
噴火寸前だった怒りを抑えつつ、あたしは一直線に走り出した。
この街に1つしかない階段を全速力で駆け上がると、近くにあった小さな茂みの中に隠れる。
必死に息を殺し茂みの隙間から外を見てみると、2人は辺りを見回してあたしを探しているようだった。
「仕方ねえ。トアとノッテがまだ買い物してることを願って、隠れているしかないな」
そう呟きながら息を整えていると、突然視界が暗くなった。いや、暗くなったというよりは、影に覆い被さったという方が正しいな。
全く……
「今度は何だよ。またお前も勧誘か何かか?それならお断りだ」
「……お前、ここの住民じゃないな?」
「だから何だ?同じ事を2度も言うのは嫌なんだけどな」
「安心しろ。勧誘とかじゃない。むしろその逆だ」
「じゃあ何だよ」
「今すぐ連れの2人と共にこの街から出て行け。取り返しのつかないことになるぞ」
「出て行けだって?全く持ってこの街は歓迎したいんだか拒絶したいのか、よく分からねえな」
「忠告はした。それじゃあな」
その男はくるりと背を向けその場を離れようとする。
こいつがどんな考えでそんなことを言ったのかは分からねえが、一目見たときからずっと何かが引っかかる。
あの他人を寄せ付けないような目、そして雰囲気……
まさかあいつ…….
「おい待て!」
あたしが大声で呼び止めると、そいつはピタリと足を止め、こちらに振り返った。
それを確認すると、また口を開く。
「お前、名前は?」
「俺か?俺はキア。別に覚えなくていいぞ」
「いや、その名前覚えておく」
「まあ好きにしたらいいさ」
そう言うと、そのキアという男はこの場を去って行った。
「キア……か」
何者かは知らないが、あいつの忠告は聞いておいた方がいいかもしれない。この街は多少安心だと思っていたが、なんだか嫌な予感がする。
本当は2,3日はここで休み、万全の状態でビルレスト大橋に向かいたかったが仕方ない。とりあえず今晩だけは泊まって、明日の朝には出発しよう。
あたしはそう決め込むと、辺りを見回してさっきの2人組がいないか確認する。
「んー、どうやらいないみたいだな」
それらしき姿が見えないのをきちんと確認すると、茂みから這い出て先ほどの階段を降りて行く。
さっきの2人組が戻っていることに警戒しつつも待ち合わせ場所まで戻ってきたが、未だにトアとノッテの姿はなかった。
「あいつら……まだ買い物なんかしてるのか?全く、女の買い物っていうのは長くて嫌だね。待たされる方の身にもなれってんだ」
そう愚痴を零しつつ、この後どうするかを考えた。
このままここで待っているのもいいが、またさっきのうざったい2人組に見つかるかも知れない。そうなると面倒だ。
まあ、幸いにもこの街はそこまで広くないみたいだし……
「仕方ねえ、探しに行くか」
そう決めると静かなストリートを歩き始めた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
歩き始めて5,6分くらい経った頃。
お腹の空いたあたしは近くにあったポップンキャンディというお菓子を口にほうばりながら歩いていると、通路の隅の方で誰かと談話をしているトアを見つけた。
あたしが手を振りながらトアに近づくと、トアもこちらに気がついたようで手を振り返してきた。
「よお、こんなとこで……んぐ、何してんだ?」
「あ、リゼさん。ちょうどこの人とお喋りしてたとこなの。そういうリゼさんこそ、何を食べてるの?」
「んー?これか。一口食ってみるか?案外うめえぞ」
「じゃあ一口もらうね!」
そう言ってトアが一口パクリとすると、トアは一瞬ビクッと跳ね上がり驚いた顔で硬直する。
が、すぐに我に戻ったのかあたふたしながら口を開いた。
「びぇぇぇ?!!な、何これ⁈今一瞬体がビクッて!ビクッて!!」
「へへ、面白えだろ?なんでもこの街の名物の綿菓子らしいんだけどよ、食べた瞬間にまるで雷に撃たれたかのような衝撃が襲ってくるんだよな。あたしも初めは驚いたぜ」
「びっ、びっくりしたよ……でもこれ、美味しいね」
「まあな。味は悪くねえ。どうだ、隣のお前も食べてみるか?」
あたしはトアの隣で縮こまっていたやつにも分けてやろうと声をかけたが、そいつは震えながら首を横に振っていた。
「なんだ、いらねえのか。ならあたしが食っちまうぞ」
「……あの、その、えっと……」
「おいおい、はっきりしろよ!」
「ひいぃ!!ごめんなさい、ごめんなさい……」
「なんで謝るんだよ」
「だっ、だって……うう……」
「リゼさん!!」
そいつが泣き出しそうになったところで、トアが間に入ってきた。
トアはキッとあたしを睨みつけると、すぐさまそいつの方へ振り向いて慰める。
……何この雰囲気。
あたしが悪いのか?あたしがいけないのか?
「お、おい……トア。もしかして、あたし悪いことでもしたか……?」
「……リゼさん。何も知らなかったとはいえ、震えてる人にそんな威圧的な言葉をかけちゃダメだよ」
「そんな威圧的だったか……?」
「はい。この人の名前はマリンって言って、極度の人見知りなんだって」
「そういうことだったのか……すまねえな、ついいつもの癖で話しかけちまって」
「あ、あの……わたしの方こそごめんなさい……人と、話すのが苦手で……」
「なあに、慣れの問題だ。そのうちお前も人並みに話せるようになるだろ」
「えっと、その……頑張ります」
マリンは未だに震えながらも、精一杯出したであろう声でそう答えた。
やれやれ、あたしが悪かったとはいえ、困ったやつだな。
そういうことなら何かアドバイスでもしてやれればいいんだが……何かあるか?何か……
「あー!見つけました!!」
「みっつけたよぉー!!今度こそ逃がさない!!」
「ゲッ!見つかっちまった!!それじゃあトア、早く集合場所に来いよ!!」
「え、ちょっとリゼさん⁈」
あたしは急いであの2人組とは真反対の方向へとダッシュすると、階段を2段飛ばしで駆け上がり、すぐさま2階の通路近くの茂みに隠れた。
まさか、また茂みの中に隠れることになろうとは。
「はあ、はあ……なんなんだよあいつら……」
「あのー、そんなところで何をやってるんですか?」
「ノッテ……か……」
息を切らし疲労困ぱいで座り込んでいると、どこからか現れたノッテがこちらを見つめていた。
お前を探してたんだよ!!と言いたいところだが、茂みに隠れながらそんな台詞を吐くと何か勘違いされそうなので、ここは素直に今の状況を伝えることにした。
「いや、それが妙な2人組に絡まれてな……あまりにしつこいから逃げてたんだ」
「あら、そういうことだったんですか。それは大変でしたね」
「全くだ。ところでノッテはこんなとこで何してんだ?まだ買い物か?」
「いえ、わたしはここの町長さんとお会いしたので、そのご挨拶をしてたところなんです」
「町長ー?」
ノッテの手を借り起き上がると、ノッテの後ろでニコニコしながら立っている人が見えた。
なるほど、あの人が町長か。
あたしは別に町長同士の交流には興味ないが、とりあえず挨拶だけはしとくか。
「お前が町長だな?あたしはリゼってんだ。よろしく」
「はじめましてリゼさん。私はここのオー•タンブルの管理を任されているエミリー•ヴァンと申します」
「オー•タンブル?それって3階にあった立ち入り禁止の建物の事か?」
「そうです。リゼさんもあそこには入らないようにしてくださいね。あとそれから、お2人とも何か勘違いしてるようですが……」
「ん……?」
「私はこの街の町長ではありませんよ?」
「あ、そうだったんですか⁈わたし、とんだ失礼を……!!」
「いえ、いいんです。この街の住民にも間違われる事がありますから」
依然変わらぬ笑顔のまま、エミリーはそう答える。
町長……じゃなかった。この人も笑顔ではあるけど、なんか色々と苦労してそうな人だな……
その後2人が会話してるのを聞きながらトアを待っていると、後ろから自分の名前を呼ぶ声が聞こえてきた。
いい加減話を聞いてるのも辛くなってきた頃だったが、やっとこれで解放される……
そう思いながら後ろを振り返ると、手を振りながら近づいてくるトアの他に、見たくないやつらの姿が目に飛び込んできた。
「やっほー!ごめんリゼさん、ノッテさん!今戻ったよー!!」
「あら、おかえりなさいトアさん」
「おぉー!こんな所にいたのかぁー!!」
「やっと見つけられましたね」
「お前らまだ諦めてなかったのかよ!!あたしは何がなんでもお前らの要求に答える気はないぞ!!」
早急に諦めさせるためあたしが怒鳴り込むと、横にいたエミリーが「まあまあ」となだめてきた。
「この2人も悪気があってやったわけではないのです。どうか許してあげてくれませんか?」
「許すも何も、別にしつこくしなきゃ怒りはしねえよ。お前らあたしだからいいけどな、これがトアとかにやってみろ?普通にストーカー容疑で捕まってんぞ」
「ひいいー!!」
「それは困っちゃうねぇ」
その言葉を聞いたハノは「ご、ごめんなさい!」と謝罪をしてきた。まあ反省してるならいいよとハノにつぶやく。
だがテティ、未だにヘラヘラと笑っているお前はダメだ。反省する気ゼロかてめーは。
まあ、そんなこんなでやっと3人揃ったあたし達はエミリー達と別れ、目星をつけておいた宿屋へと足を運んだ。
部屋が空いているか心配だったが、どこも空いてるという事でどうやらいらぬ心配だったようだ。
寝床を確保したあたし達は順番に風呂と夕食を済ませると、明日の予定を確認するため一旦部屋に集まった。
だが……
「よし、それじゃあ明日の予定を……」
「ごめんなさい、あの……予定決めは明日の朝ではダメですか……?」
「え?別に早朝に確認してから出発というんでも大丈夫だが、どうかしたのか?」
「いえ、それが少し前から頭が痛くて痛くて……もう起きているのも辛いのです」
「頭痛か?それなら早く寝たほうが……」
「ごめんリゼさん。あたしも……」
「トアもか?本当に大丈夫か2人とも。って、大丈夫そうには見えないな……」
頭が痛いと訴えた2人の顔は蒼白していて、とてもこの後予定決めを行えるような状態ではなかった。
2人の事が心配になったあたしは、今日はもう寝る事に決め、2人がベットに入ったのを確認したのち部屋の明かりを消した。
あたしもそのまま寝ようと思ったが、なんとも眠れない気分だったので外の風を浴びてから寝る事にした。
宿屋を抜け3階広場のベンチで座り込んでいると、日付も変わったこんな夜遅い時間に歩いてくる人影が視界に入った。
こんな時間に何をしているのかと気になって観察していると、そいつは辺りをキョロキョロと見回しながらとある建物の扉を開き、中へと入って行った。
おいおい、まじかよ……
「あいつ、オー•タンブルの中に入って行きやがったぞ。幸いにもこちらには気がついてないみたいだったが……」
気になって仕方がなかったあたしは、音を立てないようにゆっくりと建物の扉の前まで近づくと、静かに扉を開く。
狭い隙間から目を凝らし中を覗いてみると、目を疑うような光景がそこにあった。
寝ているはずの住民達が頭を下げ、結晶のような物の前ではエミリーが祈りを捧げており、そしてそのエミリーが祈る先にはダークマターの銅像が……あった。
どういうことなのか、見た瞬間には理解できなかったが、ほんの数秒で何をしているのかが理解できた。
でもそんな、まさか……
「ダークマターを信仰してる……?!なん……」
と言いかけた途端、突然背後から口を抑えられそのまま後ろへと引きずられる。
「ん、んぐ!」
「うるさい、静かにしろ。あいつらに見つかっちまう」
「んん⁈」
「とにかく騒ぐな。解放はするから」
そう言われた途端、抑えられていた口が解放され、あたしは反射的に息を吸い込む。
ふと後ろを振り返ると、そこには鋭い目をしたキアが、前だけを見つめ立っていた。
あたしは息を整え終わると、口を開いた。
「キア……やっぱりお前だったのか」
「やっぱりって事は、なんとなく察しはつけられてたみたいだな」
「ああ……お前、ダークマターと何かしらの共存関係にあるだろ?あたしもそうだから分かる」
「共存関係ってのは少し違うが……ま、そんなようなもんだ」
「……?いや、それよりもあれはどういう事だ?なぜこの街の住民がダークマターなんかを……」
「うーん、当然そう質問してくるよな…..」
キアは周囲を見回し誰もいない事を確認すると、話を続ける。
「実は2,3日前から住民達が頭痛を訴え始めてな。初めは感染病か何かだと思って医者に任せてたんだが、その次の日には住民達の様子がおかしくなっててな」
「それはどんな?」
「見た目はいつも通りだったんだが、陰でダークマターの事を讃えるような事を口にするやつが増えたんだ」
「ダークマターを讃える……?」
「ああ。そんでその晩には今みたいにオー•タンブルに集まって、皆でダークマターを信仰するなんて事になっちまった」
「キア、お前はなんともないのか?」
「俺は問題ない。いやむしろ、ダークマターとの因果がある俺だからこそ効かないんだろう。そしておそらくそれはお前も同じだ」
「そういうことか……でも何故皆は……ん?」
そう言いかけた時、キアの後ろからフラフラと歩いてくる人影が視界に入った。
最初は周りが暗くこの街の住民だと思ったが、あれは……
「トア、それにノッテ……⁈」
「何?まずい、もうおかしくなり始めてるんじゃないか⁈」
「っ……!!トア、ノッテ!おい大丈夫か⁈今そっちに!!」
「おい馬鹿!そんな大声を出したら……!!」
あたしが2人の側へと近寄ろうとした瞬間、背後からバタンッ!!とドアを開ける音が聞こえてきた。
しまった……あたしが大声を出したせいで……!!
「不審者です!貴方達、今すぐ4人全員捕らえるのです!!ダークマター様のために!!!」
「くっ!トア、ノッテ!おいしっかりしろ!!」
「んん……ダークマターは……あたしの……」
「偉大な……えっと……」
「おい、目を覚ませ!!キア、なんとかならねえのか!!」
「これは俺の推測だが、おそらくこの街自体が皆をおかしくしてるはずだ」
「ならこの街から出ろってか⁈でも飛行船の操作なんてあたしには無理だ!!!」
「……こうなったら仕方ない。俺が食い止めてる間にお前はその2人と共に、この街から飛び降りろ」
「はあ?!!自殺しろってか!!」
「それしかない!いいから俺を信じて飛べ!!」
飛べっつっても、ここは雲の上だ。落ちてしまえば間違いなくそのまま遥か上へとUターンするのは目に見えてる。馬鹿なんじゃないかあいつ!!
だが、他に方法が思いつかないのも事実。こうなったらやるしかないのか……!!
あたしは鳴り響く衝撃音をバックに2人を抱えて崖っぷちまで走ると、大きく深呼吸をする。
もしも何も起こらなければ天国行き。だが……
「あたしはお前を信じるぜ、キア……!!」
2人をしっかり抱え込むと、あたしは強く地を蹴り空中へと身を放り出した。
ただただ落下してゆく恐怖感だけが襲ってくるが、あたしは目を閉じもう1度2人を強く抱き抱えた。
トア、ノッテ……すまねえ‼︎
そう考えた時だった。
突然落ちてゆく感覚から解放され、同時に何者かに背中を掴まれているような感覚が伝わってきた。
恐る恐る目を開け頭上を見上げてみると、少し辛そうな顔をしたキアが空中を浮いていた。
驚きのあまり思わず声を上げる。
「お、お前!空中を浮けるのか⁈」
「言ってなかったか?というか、お前は浮けないのか」
「浮けるわけねえだろ!浮けたら自殺行為なんて言わねえよ!!」
「それもそうか」
キアはうっすらと笑いながら、そう答える。
全く……ふざけた顔して笑いやがって。蹴りの1つでも入れてやりたいぜ。
「ところで、まだお前の名前を聞いてなかったな」
「あ?あたしの名前か?」
「そうそう」
「あたしはリゼっていうんだ」
「リゼだな。それじゃ、このまま俺もお前達について行くからよろしく」
「え!なに、お前ついてくんの⁈」
「旅は道連れ世はなんちゃらって言うだろ?それにもうあの街には戻れないし……」
「仕方ねえな……でもいらぬ真似したら許さねえからな?」
「分かってるよ」
こうして新しい仲間を加えたあたし達は、静かに闇夜の中を突き進むのだった……
つづく。