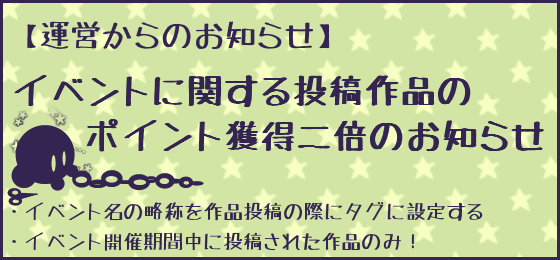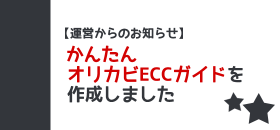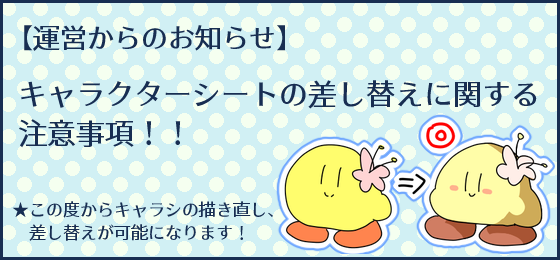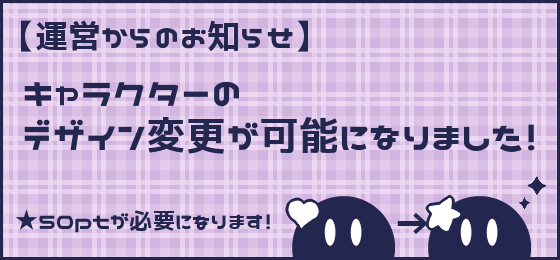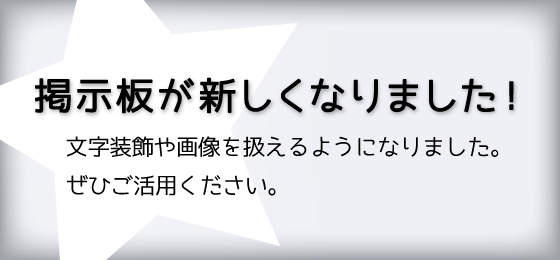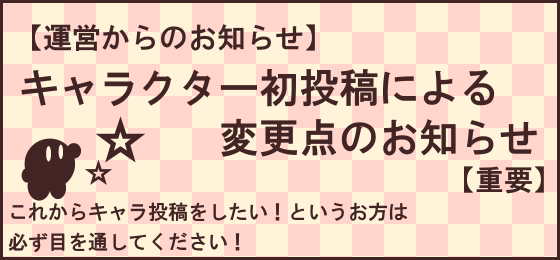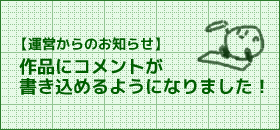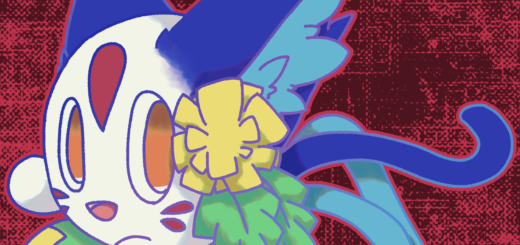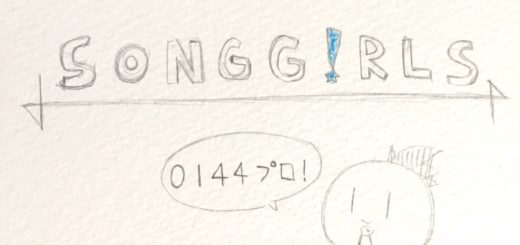「どこだろう…..ここ」
勢いよく町を飛び出して何日か経ち、順調に目的地に向かっていたはずの僕はいつの間にか知らない場所に立っていた。
あたりを見渡すと高そうな本や使いかけの薬品、さらには薄汚れた実験機材?などが散乱していた。
「研究室…..?でも誰の……」
「何をしているんだい?そこの御嬢さん」
「え…?!」
突然背後から声をかけられ、恐る恐る後ろを振り向いて見ると……そこには無表情な顔でこちらを見つめる緑色の体の人が立っていた。
その人は軽くため息を吐くと、やれやれといった感じで口を開いた。
「御嬢さん……ここがどこだか分かっているのかい?」
「いえ……僕はただ偶然にもここに迷いついただけで……あ、立ち入ってはいけないところならすぐ出て行きますので……!!」
「いや、すぐに出て行く必要はないが……つまり迷子というわけか」
「うっ」
ズバリと今の自分の状況を当てられてしまい思わず息詰まる。それと同時にやっぱりまた迷子になってしまったんだということを認識させられた。
「ここは今や関係者以外立ち入り禁止だが、迷子なら仕方ない」
「あの……ここはどこなんですか?」
「ここか?ここはイゼルシュタット。そしてこの研究室はアルブスラボラトリーという会社の一室なんだ」
「アルラト….リ?」
「そうだ。少し前まではここでは有名な社長が仕切っていたのだが、その社長が突然やめてしまってね。今この会社は社長がおらず、どうなるかも分からない状況なのだよ」
「え、えっと……そうですか」
そう話してくれたのはいいけど、話が長くてもう半分くらい忘れてちゃった…..
と、とりあえず社長さんがいなくなったという事…..かな?
僕が頭を押さえて頭の整理をしていると、あちら側が思い出したかのように口を開いた。
「そうだ、自己紹介がまだだったね。私の名前はヴェルナーだ。失礼ながら、御嬢さんの名前を聞いてもよいかな?」
「は、はい!僕はユウスっていいます!あとその……僕は男なんですけど……」
「……え⁈む、むう…..どうやら何か訳ありのようだね。ここで長話もあれだ、とりあえず外に出ようか」
「分かりました」
そう言ったヴェルナーさんが静かに歩き始めると、僕はその後におとなしくついて行った…….
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「なるほど、そういうことか……」
「何か少しでも心あたりはありませんか?」
「いや、そのような症状は全く聞いたことがないな…..すまん」
あの会社を出て数十分。僕とヴェルナーさんはとある飲食店に入り、軽くお茶を飲んでいた。
そこでダメ元に何か知っているか聞いてみたんだけど……やっぱり知らなかったようで、先ほどから頭を傾けたままこちらを見つめていた。
「それにしても、本当に変わった現象だな。なかなかに興味をそそられる……」
「は、はあ…..」
「おっと失礼。医者をやっているせいかつい……」
「え?ヴェルナーさんは医者をやってるんですか⁈」
「ああ。まあ今は端くれ者だがね」
ヴェルナーさんはお茶をすすりながらそう答えた。ダメ元で聞いたとはいえ、何も情報が得られないとなると、少し気を落としてしまう。
僕がこの後どうしようかと考えていると、ヴェルナーさんがふいに「何やら後ろの席が騒がしいな」と言って席を立った。どうやら少し注意をしに行くらしい。
何もすることがない僕は、ただぼうっとその様子を眺めていた。
「突然失礼。君たち、ここは飲食店だ。会話が盛り上がるのは結構だが、もう少しおとなしめにしてくれないか?」
「あー申し訳ない!今後は気をつけ……って、ヴェルナー殿ではないですか!」
「む、なんだ君か。こんなところでも君は騒がしいのかい?」
「やや、面目無い……」
「無理もないよー!こんなのを見たら誰だって興奮するよ!」
「そうだね ピエもおどろいた」
「ですよねですよね!」
「ミー……少し落ち着こうか」
「全く……またいつものメンバーか」
「いつもの……メンバー?」
僕が会話のやりとりを聞いて疑問に思っていると、席に座っていた5人がこちらに気がつき、1人を除いた4人がこちらの席に乗り込んできた。
「むー?見かけない顔ですね。私はブンタと言います。どうぞよろしく!」
「可愛いー!あ、アタシはクローバーっていうの!よろしくね!」
「ピエよ 貴女 ふしぎなかんじがする」
「ハローハロー!ミーはミーっていいます!そしてあちらで座っているのがミーのご主人様のライク様です!」
「……よろしく」
「えーと…..僕はユウスっていいます……あの、すみませんがもう少し離れてくれると助かるんですけど…..」
「え⁈ごめんごめん!」
そう言いながら顔をギリギリまで近づけていたクローバー?さんは後ろに下がり、なんとか圧迫感から抜け出せた。
ふうっと一息ついたものの、今の一瞬の自己紹介で覚えられるわけがなく、誰が誰だったかもう忘れてかけている。
「ところで、何をそんなに騒いでいたんだい?」
「それはですねヴェルナー殿。見てくださいこれ!」
黄色のヘルメットを被った人はコップを持ち上げると、そこに何かを落とし入れた。
すると何かが入った飲み物はブクブクと泡立ち始め、後ろにいた3人は目を輝かせながらその様子を見つめていた。けど……
「ん……?これ、何か凄いんですか?」
「私も御嬢さんと同意見だ。別に騒ぐほどのものでは……」
「何を言っているんですか!炭酸飲料の中に飴を入れたら突然泡立ち始めたんですよ⁈これは革命的な発想です!!」
「そうです!そしてこれを発見したのはライク様!やっぱりライク様は凄いです!!」
「別に…..なんてことはないのに、皆さんが勝手によってきて騒いだんじゃないですか」
「あ、アタシまだ飴持ってるよ?ヴェルナーさんも貴方も一緒にっ」
「いや、結構だ」
「僕も遠慮しときます……」
僕とヴェルナーさんが断ると、クローバーさんは一瞬ガクッと肩を落としたが、すぐさま気を取り直して飴を取り出した。
「じゃあ飴だけでも貰ってください!」
「そうかい?それなら有難く貰っておこう」
「ありがとうございます!」
そう言って飴を一つ受け取ると、口の中に放り込んだ。
口の中で無心に飴を転がしていると、すぐさま異様な味覚に襲われた。な、なんだこれ……
前を向くとヴェルナーさんもこの異様な味に気づいたようで、すぐさまゴリゴリと噛み砕き始めた。
堪え切れなくなった僕は思い切って聞いてみようと必死に口を開いた。
「あの……これ……何の味なんですか?」
「あーこれ?これつい最近見つけた黒糖飴なの!甘くて美味しいでしょ!」
「いや……なんというかその…..」
「んー?あれ、それよりも貴方その姿は⁈」
「え?……あっ⁈」
〝その姿は?〟という言葉と先ほどからの違和感で嫌な予感はしていた。でもきっと気のせいという可能性も……
「お?なんですかその服は!」
「すごく かわいい」
「まるで魔法少女みたいですね!そう思いませんかライク様!!」
「ん、そうじゃない?」
「……」
うん、気のせいじゃなかった。
この後、向けられた好奇の眼差しと迫り来る人々の中に埋もれるのは言うまでもなかった……
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「結局、あれだけ苦労したのに誰も知ってませんでした…..うう…..」
「そういうこともある。まあそう気を落とすな御嬢さん」
「だから僕は御嬢さんじゃないですってば!!」
「ああ……そうだったね、すまん」
あの後、あの店での混沌をなんとか生き延びた僕だったけど、結局誰一人この現象について知る人はいなかった。
代わりに知ったことと言えば、あの魔法少女の姿になるとろくな事が起きないということだけだった。
「さて、そろそろのはずだが…..」
「あの、どこに向かってるんですか?」
「それはすぐに分かるさ。ほら、もう着いたぞ」
「ここは…..」
ふと足を止め前を向くと、そこには赤錆びた外壁に薄汚れたパイプが張り巡らされた建物が静かに立っていた。
そういえばここに来る前も似たような建物がたくさんあった。
少し黒みがかった煙がもくもくと立ち込め、精一杯働く多くの人達が交差していた。
でも、みんなとても生き生きとした笑顔で挨拶をかわし、談話をしていた。
今思えば僕が住んでいる町もみんな笑顔だった。僕は時々迷子になってしまい、その度に先生たちが見つけてくれているけれど、迷惑じゃないだろうか……?
「….さん。御嬢さん!」
「は、はい!」
「大丈夫かい?すごい顔をしていたが……」
「だ、大丈夫です。それよりもここは?」
「入れば分かる。行くぞ」
ヴェルナーさんに言われるがままについて行き中に入ると、目の前には大きな飛行機と、整備中と思われる人が何かごそごそといじっていた。
僕たちが近づいていくと、整備中の人がこちらに気がつき振り向いた。
「あら、ヴェルナーさん〜!こんにちは〜!」
「こんにちは、キーラ。今日の仕事は休みかい?」
「うん、そうなのー!だからこうして飛行機の整備してるの〜!」
「そうか。だがその飛行機、いつも見ているものとは違うような…..」
「これはつい先日廃棄するとされていたものをもらってきたものなの〜!少しダメージがあったけど、今ならもう近いところになら飛べるよー」
「そうか…..」
ヴェルナーさんは話を聞きすぐに何かを考え始めたかと思うと、何かを考えついたという顔つきで口を開いた。
「キーラ……頼みがある」
「はい、なんでしょうー?」
「ここにいる御嬢さんをヒネモストバリまで届けて欲しい。頼まれてくれるか?」
「ヒネモストバリー?うーん」
キーラと呼ばれたその人は、少し考える素振りをして答えた。
「いいよ〜。ちょうどこの子の試運転もしたかったしー……届けてあげる〜!」
「本当ですか⁈ありがとうございます!!」
「いいのいいの〜。あ、それからそんな堅苦しい喋り方しなくていいからね〜」
「え?そういうことなら…..よろしく、キーラさん!」
「こちらこそよろしく〜!じゃあさっそく行きましょうか〜」
「うん!」
キーラさんに手助けしてもらいながらなんとか飛行機に乗り込むと、操縦席の後ろの席に座り安全ベルトをつけた。
ふうっ……と一息つくと下の方から名前を呼ぶ声が聞こえてきたので、身を乗り出して見てみると、ヴェルナーさんがこちらをじっと見つめていた。
僕は忘れないうちにと思っていたことを口に出した。
「ヴェルナーさん!色々とありがとうございましたー!」
「別に私は何もしていないさ!それよりも原因が見つけられるよう応援しているぞ、少年!」
「はい!!」
そう叫ぶと同時に飛行機のドアが閉まり、キーラさんの「離陸しまーす」という掛け声と共に飛行機は大空へと羽ばたいていった……
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
その頃とある町で−
「遅いなー!何してんだあいつ!きちんと上手くやったんだろーな?全く……」
声の主は石ころを蹴り上げながら、1人そう呟いた。
つづく。