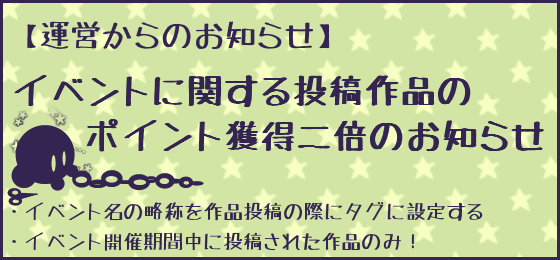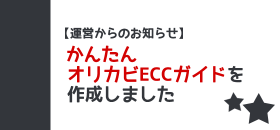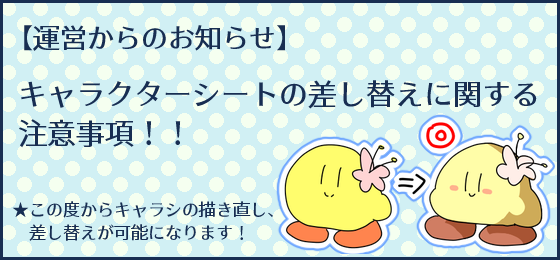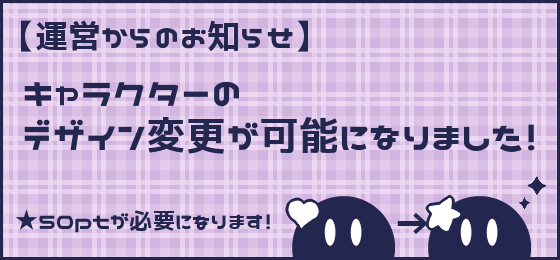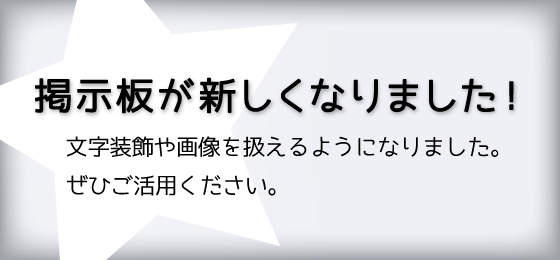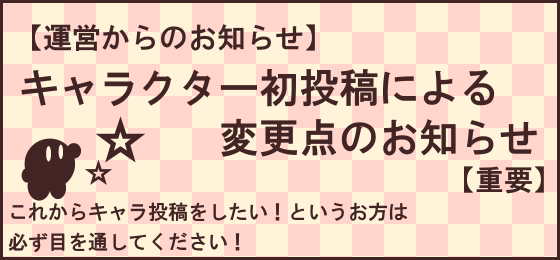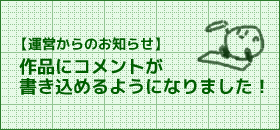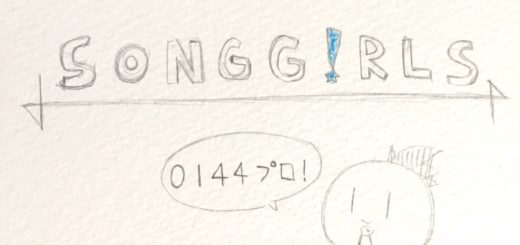「じゃあわたしはこれで〜!」
といって去ったオレンジを目で追ってから、その場にいた者全員が顔を見合わせる。
バレンタインのチョコレートをもらった。それはいい、それはいいのだが、チョコを渡した当のオレンジは、皆に配られたのとは明らかにラッピングの気合が違う小箱を持っていたのだ!
その一つだけ箱が違うチョコは誰の?!!
気になる。調べる? ザワザワする皆の前でヴァニラが鷹揚にふんぞり返る。
「オレンジにもオレンジなりの事情があるんだろう。他人のプライベートを詮索するのは関心しないな。
でも気になるから僕は調べる」
「調べるのかよ」
タルトにツッコミを入れられようとヴァニラは全く気にしない様子で、チョコレートを懐にしまいつつ言う。
「朝になれば人格が入れ替わってしまう。突き止めるなら今日の夜のうちだな」
ふうん、とコフレラがまばたきをする。タルトに流し目。
「タルトさん情報屋でしょう? なにか知らないの」
「……そんな情報ねえよ」
もともと半眼ぎみの目をゴーグルの奥でさらに細めて、タルトはため息をついた。
「俺らの勘違いなんじゃないか?」
「タルトさんが知らないだけかもしれないでしょう」
「貴様の情報網も大したことないな」
「夜暗を知り尽くした情報屋といえどその程度か」
コフレラ、ヴァニラ、クロの順に好き勝手に言われ、タルトが顔をしかめる。
「馬鹿にするなよ、1時間で調べ上げてきてやる。手伝えコフレラ」
「まあ、いいけれど」
「フ、では僕とクロとサリヴァンはオレンジの尾行につこうか」
「ワタシハ行クトハ言ッテナイ」
「昼のサリーだったら多分ついてきていたぞ」
「……」
サリヴァンが無言で立ち上がる。ふん、と鼻を鳴らし、ヴァニラも立ち上がった。とっとと調査を開始する気だ。
ため息をついて、タルトも席を立った。
かちり、かちりと歯車の回る音がする。水蒸気の立ち込める町並みもこの歯車の音も、他の街の者から見ればさぞや不思議な光景だろうが、この街から出られない住民達にとっては改めて気にすることもない日常の一部だ。
今は夜なので、二人が歩いている〝基本街〟はとても暗い。コフレラがタルトの顔を覗き込むようにして問う。
「私は何を手伝えばいいの?」
「夜のオレンジと昼のコフレラって性格が割と似てるだろ。あいつが好きになりそうな場所とか相手とか考えてくれ」
「あら、ほんとうに何も手掛かりがないのね」
「あのな。オレンジってこの町の管理者の一人だろ? 情報なんてほぼほぼ出尽くしてるんだよ」
タルトは頭が痛そうな顔で遠くを見やる。
「俺は絶対になにかの勘違いだと思うんだよなあ」
「そう」
すい、とタルトに視線をやったコフレラは
「でも、手伝ってくれるのね」
よく通る声で呟いた。それは少し歌うみたいな調子で、それを聞いたタルトはまた難しい顔をする。
コフレラがするりと前に出る。
「夜のあの子が好きそうなアクセサリーショップが通りにオープンしていたから、まずはそこで聞き込みでもしてみましょうか」
タルトを振り返って、優しい笑みを浮かべた。
コフレラの読みどおり、オレンジはアクセサリーショップに寄ったようだった。
ただ、ひとつ予想外だったのが。
「男性用のアクセサリーを買っていったらしいのよね」
頬に手を当てて、コフレラが少し首を傾げる。
男の子向けのアクセサリーを買ったオレンジは、購入時に「チョコレートと一緒に渡すの!」と言っていたらしい。
オレンジが持っていた小箱と同じ箱も、バレンタイン用としてスイーツショップで見つけてしまっている。まさか本当に好きな相手がいるのだろうか……? と、コフレラとタルトは顔を見合わせた。
ふと、タルトの懐が光る。タルトは服の中から、ごつごつした拳大の繊細な金属塊を引っ張り出す。タルトが仕事用に持っていた通信機である。
特定のパターンで表面を叩くと、光の明滅にあわせてヴァニラの声がする。
「もしもしこちら尾行組。オーバー」
「トランシーバーでもないんだからオーバーはいらないんじゃないか。オーバー」
「ああ。いちど言ってみたかった」
「切るぞ???」
「まあ待て、首尾よくオレンジを見つけた」
ヴァニラの声に加え、クロの声も入ってくる。
「いま私達は〝銀の世界〟のほうの商店街にいるのだが、そこでなにかを探しているようだ」
「なにかって?」
「遠すぎて不明だ。蒸気で煙っていてオレンジの姿を見失わないので精一杯だ」
「それほど大きなものではなさそうだけどな。どう思うサリヴァン」
「話カケルナ」
「なんだ貴様。まあいい。報告は以上だ」
ふつり、と光が途切れて通信が途絶えた。
次の連絡は、タルトとコフレラが基本街の1階層をずいぶん歩き回ったころに届いた。
「こちら3階、〝銀の世界〟の天文台。今日も良い星空だ」
「御託はいいから何があった?」
「感性の乏しいやつめ。
オレンジは文房具店に寄ったようだ。中くらいの包みをひとつ抱えていた。そのまままっすぐ天文台に来たが、周囲には誰もいない」
「これから来るかもしれないので私達はしばらく様子を見る。
そちらの首尾はどうだ?」
「……アクセサリー店で男の子用のアクセサリーを買っていたらしい。あと、例の小箱はバレンタインの商品で間違いないようだ」
「ふん、これはいよいよ怪しくなってきたな」
「いや、でも」
「おい待て。動きがあったぞ!」
緊張感をともなったヴァニラの声。タルトもコフレラも黙って通信機の向こうに耳を済ませる。
歯車のカチコチいう音に混ざり、なんだかトタトタとかパタパタとか、そんな音が聞こえるような気がする。
「……何をやってるんだ?」
「なんというか。そこら中を歩き回ってるようだが。たまに何かを掲げて止まる」
通信機の向こうで、なおも様子を伺っている気配はあるが、何をしているのかは一向にわからないらしい。
「近づいて様子を見ることはできないのか?」
「少しは自分の頭で考えろ貴様。できるのだったらやっている。人が全くいないから近づいたら目立つんだ」
ヴァニラの刺々しい声に対してタルトが言い返す前に、クロの声が割り込んでくる。
「私が”影煙”で近づいてみようか?」
「影に潜れるんだったか。よしやれ」
「おい軽率に動くな」
「残念だったなもう行った」
「お前ら……」
「ふん、指図は受けないぞ」
「ただいま」
「早い」
「どうだった?」
「しきりに写真をとっているようだが?」
「……何がしたいのかは未だ謎のままだ。報告は以上だ」
それだけ言って、ふつりと光が途切れた。
写真と天文台というキーワードから、カメラ屋を探したらあっさり情報が見つかった。
オレンジがよく喋ることと、女の子がカメラを借りるのは珍しいということで、店主はオレンジのことをよく覚えていた。
「わたしが一番キレイだと思った星空を見せたい人がいるの! と、ずいぶん嬉しそうに話していたねえ」
カメラ屋を出たところで、通信機が光る。
通話を繋げて聞こえてきた声は、予想を裏切りヴァニラではなかった。
「コチラ サリヴァン」
「なんだどうした」
「管理区画ニ入ッタ オレンジヲ ヴァニラガ追ヲウトシタガ管理者ニ見ツカリ、クロ ガ ヴァニラヲ影ニ隠シテヤリスゴシテイル」
「なぜ止めなかった……?!」
「ワタシには関係ナイ」
タルトがこめかみを押さえる。
「……管理者に捕まらないようにだけ気をつけてやってくれ……」
「私ノ邪魔ニナラナイ範囲ナラ」
なんだかどっと疲れた気分になったタルトは、通信を切ってため息をついた。
コフレラが少し困ったように微笑み、「そろそろ休憩しましょうか」と言った。
落ち着けそうなカフェがあるから、と、最初の住居エリアまで戻り、そこでお茶をすることにした。
「これまでの話を整理するとだ」
「ええ」
「まずバレンタイン用のお菓子を買って」
「アクセサリーショップでは、男のかた向けのアクセサリーを買って」
「俺達にチョコレートを渡したあと」
「文房具店でなにかを買って」
「カメラ屋ではカメラを借りて」
「天文台で写真を撮った理由が」
「一番キレイだと思った星空を見せたい人がいる、から……」
タルトがカフェの机に突っ伏す。
「……なんだか非常に下世話なことをしている気がする」
「そうね、ちょっと優雅ではないかもしれないわ」
コフレラは涼やかにそう言って、カップに口をつける。
カランカラン、と入り口の鐘が来店者を告げる。タルトとコフレラは入り口の方を見て、固まった。
白い体に狼を思わせる耳と尾。少しネオヴィクトリアンを感じさせる服装と帽子につけたゴーグル。なによりも店員さんとの止む気配のない元気なお喋り。
そこに居たのはオレンジだった。
手には文房具店のロゴが入った包みと綺麗な包装の小箱、天文台で撮ったものを現像したらしい写真を持っている。オレンジはそれらを、ぜったい落とさないように、とでもいいたげに、大切そうにぎゅっと抱えている。店員さんとのお喋りを上機嫌で切り上げた彼女は、コフレラとタルトには気づかずにテラス席へ向かった。汚れないようにハンカチを敷いてから小箱を丁寧に置いて、椅子に腰掛ける。そうしてプレゼントの包みをつついて、にこにこと笑っている。
タルトの手元で通信機が光る。
「こちら尾行組。管理者は無事撒いた」
「……無事って言えるか?」
「首尾よくオレンジも見つけたぞ。いつの間にか最初の住居エリアに戻ってきているな。貴様らは……ああ見えた。だが通信機で話すのが楽しいからこのまま話すぞ」
「もう好きにしろ」
ツッコミを入れる気力もないタルトはなげやりにそう答え、オレンジの座るテラス席へと視線を向ける。
カフェのテラス席に座るオレンジは文房具店の包みを開けたところだった。中から取り出したのは、かわいい柄の便箋と封筒のセットだ。さらにペンを取り出し、便箋に文章を綴り始める。いつも絶えず喋り、笑い、楽しそうにはしゃいでいる姿からは想像できないような真剣な表情をしている。ひとつひとつの言葉を確かめるようにペンを動かし、少しだけ書いたかと思うと口元に手を当て、じっ、と悩み、また真剣に書き始める。
――あんなに悩むオレンジは初めて見た。
そこまで思い詰めるほど。……熱の籠もった表情を見せるほどに、好きな相手がいるのだろうか……?
なんだか見てはいけないような気分になって、タルトはオレンジからそろりと目を逸らす。
そらした目線の先で影が2つ、飛び出した。
「オレンジ! 思いを伝えるなら手紙よりも直接会って伝えるのがベストだ。ラブレターよりも直接の告白のほうが成功率が高い。眼と眼を合わせて勇気を出せば想いは必ず伝わる!」
「羞恥に打ち勝ち告白すればオレンジの真剣な想いは必ず届く……! この街の影を護る執行者…私がそれを保証する」
ヴァニラとクロがばっちりポーズをキメてアドバイス(おせっかい)を放つ。タルトは頭を抱えた。「中二病コンビどもめ!」
急に飛び出してきたヴァニラとクロを見て、ぽかん、とした顔をしたオレンジは、状況を理解すると同時に吹き出し、ケラケラと笑いだした。
「やだなあ! これは昼のわたしにあげるんだよ!」
――トランスギアに住まう住人達は、昼と夜とで姿を変える。
生まれた時に押された刻印が原因であるそれは、性別・性格・はたまた種族。何がどれだけ変わるかは様々ではあるが、昼夜で街がくるりと180度回転するのに合わせて、すべての住民に効果が及ぶ。
自覚のある無し、意思疎通の可否はあるが、確かであることは「昼と夜の自分が出会うことは絶対にない」ということ。だってそれは、自分自身なのだから。
「だから手紙を書こう! と思ったの。ついでにバレンタインのチョコレートと、ちょっとしたプレゼントもね!」
昼の自分はきっと、夜空なんて見たことないもんね! 天文台から見た星空の写真を手に、オレンジはウインクした。
それを聞いて、ヴァニラもタルトもコフレラも、クロもサリヴァンも静まり返る。ここにいるみんな、思うところがあったから。
「……そうだな。僕もこのチョコレート、ショコラにやろうと思っていた」
ヴァニラにしては珍しく、優しい声音でそう言った。オレンジにもらったチョコレートを取り出し、少し微笑んで眺める。
そして照れ隠しをするように、鷹揚にふんぞり返った。
「動き回って喉が乾いた! 僕もなにか飲むぞ」
くすり、と笑うコフレラが「私もご一緒しようかしら」と言い、クロもメニューを開き、サリヴァンはオレンジが頼んだ菓子を勝手につまみ始めており、オレンジはとっとと全員分の飲み物を注文してしまっていた。ため息をつくタルトも実はそれほど嫌な気分ではなく、テーブルにつく。
夜はまだまだ長い! 空には満点の星が輝いていた。
ヴァニラがキザったらしくカップを掲げる。
「夜の僕らに乾杯を」
おしまい