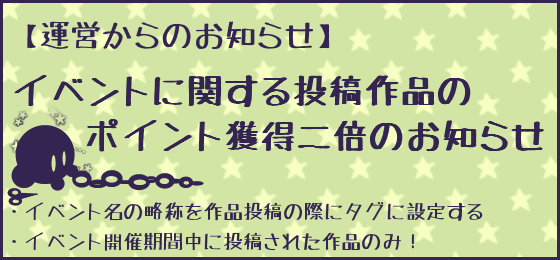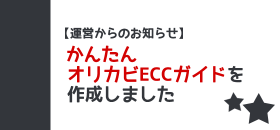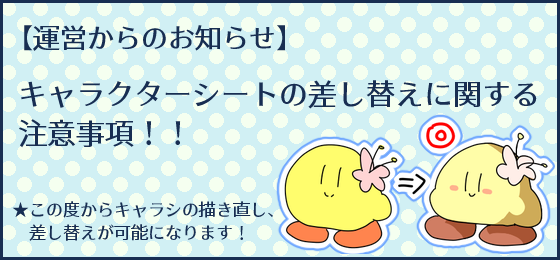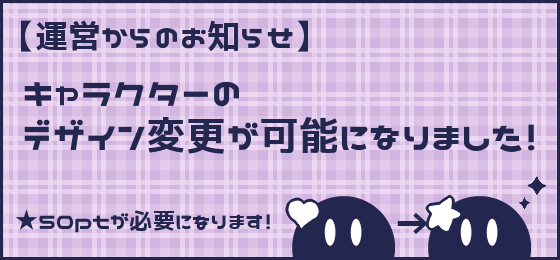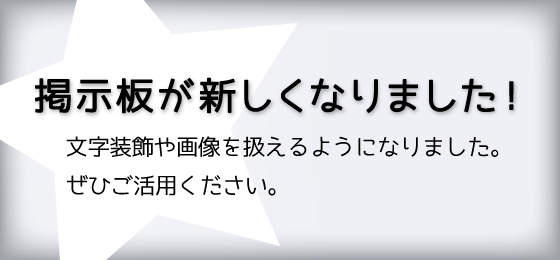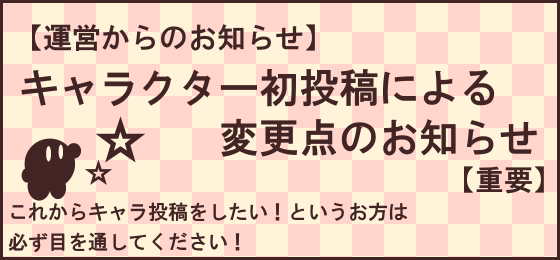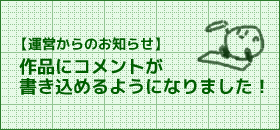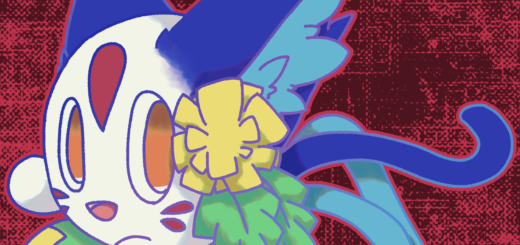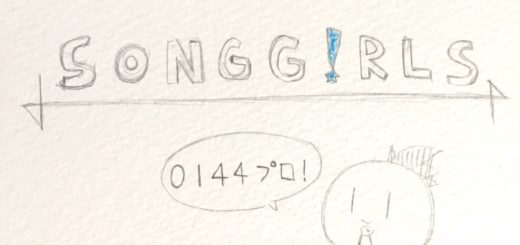-
目を開くと暗く鈍った空に古い西洋を思わせる街並みが広がり、それなりに豊かな生活を営んでいそうな人々が行き交う広場の隅に僕は立っていた。
一見どこにでもあるようなお伽噺の街のようだ。
ただひとつ、全てが真っ黒なことを除いて。
目の動く限り見回しても色彩があるのは自分の体ひとつでひとり隔離されているような疎外感を覚える。
またおかしな場所に来てしまった。
先程刃を突き付けた勇者だった彼がどうなってしまったのか心に引っかかったが、この一瞬で全てが変わり、今目の前に居ないということはもう姿を見ることはできないのだろうとどこか直感的に悟った。
本当にどうなっているんだろうか。
考えたところで「本の中に入ってしまって話が変わった」なんて非現実的なこと以外は思い付かない。このおかしな現象はあの絵本を手に取ってから始まったのだから。
無理にでも気持ちを切り替えるために胸がキリリと痛むほど息を吸い込み、全てを吐き出すように空気を肺から追い出した。
捨てた暗い気持ちは周りの黒に混ざり、まるで消えたかのように錯覚をさせてくれた。
不思議なことに身体の傷は消えていたが疲労感は重くのしかかったままで、とりあえずはどこかに休める所を求めた。
幸い街は栄えている。なんとかなるだろう。
普段旅をしているだけあってこういう時に慌てずに済むのは救いだ。宿と食糧、それだけあれば今はいい。
兎にも角にも情報があまりに無さすぎる。
どこか飲食店、特にこの地域によく馴染んでいそうなところがいいだろう。そう思い大きな通りを眺めながら店を探し歩く。
しかし本当にどこを見ても黒一色だな、どうしてなんだろう。気のいい店主がいたら聞いてみよう。そんなことを頭にふわふわと浮かべていると、こぢんまりとしたカフェのような店を見つけた。
こういう場所には住民が集まりやすいだろうし情報収集にはうってつけだ。
軽く軋む音を立ててドアを開け、ぐるりと見渡してから端のカウンター席に座る。
その時、ほんの少しだけ周りから訝しげな目線を投げられたような気がした。
黒いメニューを眺め、しばらくアイスを食べていないことに気付いたのでデザートの項を見る。
バニラアイスが食べたかったのだが、どういうわけか黒ごまアイスやチョコアイスのようなアイスしか置いていない。仕方ないしチョコアイスでいいか。
「すみませーん」
店主と思しき人に手を挙げて声をかける。
『いらっしゃい……注文の前にひとついいか?アンタは黒と白、どっちだ?』
間抜けな声を出しそうになりながら店主を見ると、明らかに警戒した目がそこにはあった。
「え?んー…黒のほうが好きですけど…どういうことですか?」
突然の変な質問に首を傾げながら適当に答える。
『そうか!黒か!いやぁすまないね。ここでは白は黒を乱す悪なんだ。アンタちょっと薄いからさ。それで、注文は?無礼なこと聞いたからサービスするよ』
そう言いながら店主は表情を崩し、注文したチョコアイスのメモを取り持ち場へ戻っていった。
…白は黒を乱す悪?どういうことなんだろうか。ここの以外の白い国と争いが起きているとか、そんなところだろうか。
道理でどこにも白いものが無いはずだと不思議ながらも納得して、ここでは黒いほうがいいだろうと思い右半身で薄く全身を包み込み黒く染め上げた。
周りの客より少し多めに盛られたアイスを食べ、店主に宿があるか聞いて店を出た。
さっきより黒くなっていたことに驚いていたが、黒いことはいい事だとよくわからない賞賛をされた。
店から出ると裏路地から騒がしい声が聞こえてきた。
こういうものは関わるとあまりいいことはない。素通りしよう。
そう思って横目に通りすがろうとした時、真っ白な人が地面に座り込み、数人がそれを囲んでいるのが見えた。
『ここでは白は黒を乱す悪なんだ』
先程の店主の言葉が脳裏を過ぎる。
この辺りに住んでいればああなることはわかっていたはずだ。なのになぜこんな街中に白がいるんだ?もしかして僕と同じで迷い込んだのか?
突然の混乱に足は止まり、行われる乱暴を凝視してしまう。
『うぅ…っ!やめてよ…!ぼくはなにも悪いことしてないじゃないか…!』
口元から紅いであろう液体を流す白が顔を歪ませて呻く。
そんな悲痛をものともしない黒が『白は黒を乱す悪だ』と一蹴して更に拳を入れる。
あぁ、差別とはきっとこういう事なんだろうな。
軽く掠れた音を喉奥に下し声をかけるべきか脳内で審議する。
勇気がない、と浮かびひとりの青年の顔が浮かんだ。そういえば彼もそうだっけ。でも彼には勇気を与える力があったな。
…僕にも少しならできるものだろうか。
単に流されやすい性格なだけなのかもしれない。それでもその一瞬動き出すには充分な動機だった。
「ねぇ、ちょっと話聞いてあげるくらいはいいんじゃない?悪いことしてないってよ?」
突発的に動いたはいいが直後にやってしまったと思った。たぶん袋叩きにされる。
『なんだ?お前も黒を乱す白の仲間なのか?』
鋭く睨みつけられ一瞬怯む。
「……いや僕も黒だよ。ただ説得でなんとかなるならそれがいいと思ってさ。暴力は流石に、ね?この白には僕から言っておくから」
苦し紛れな言葉をごちゃごちゃに並べそれっぽく言おうと試みる。
どうするよ、とか言いながら顔を見合わせる黒に冷や汗をかいているとリーダーらしきひとりが『興が冷めた。行こうぜ』と大通りとは反対へ向かいそれに仲間も続いて行った。
助かった、と息が零れる。柄でもないことするものじゃないな。
『あ、あの、ありがとう…ございます…』
口元を拭いながら白いのがぺこりと頭を下げた。
「あー…いや、うん、大丈夫?色々されてたけど…」
『はい…ここじゃこれが普通みたいなので…ぼくは仲良くしたいんですけどね…』
俯く白になんとなく目を向けられずに言葉を呑む。普通って、なんだろうか。
『あ!そうだ。あの、よかったら、ほんとによかったらでいいんですけど、うちに来ませんか?助けて頂いたお礼をしたいので…』
突然僕の深慮を吹き飛ばすようにそんな言葉が飛び出してくる。この子こんなで大丈夫なのかなぁ?
「あー、それなら一晩くらい泊めてくれると助かるんだけど…お礼っていうの、それじゃダメかな…?宿まだ決めてなかったんだ」
それを聞くと白いのはぱっと顔を明るくして、是非!と手を取ってきた。
どうやら今日は空の下で一晩を越すことなく済みそうだ。
空は黒に呑まれ始め、街を照らしていたものは地平線に溶け始めていた。
手入れのされた小さな窓からそれを眺め少しの間感傷に浸る。
「それにしても」
先程まで前を歩いていた白いのに振り返る。
「想像はしてたけど…思ったより辺境に住んでるねぇ…」
あの栄えた街からどれだけ歩いたことだろう。遠くにごま粒のような街並みが見えるかどうか、そんなところに彼は住んでいた。
彼はなにやら照れながら嬉しそうにしているがなにひとつとして褒めているわけではない。
『あ、そういえば…助けて頂いてなんですが…キミは…黒…?』
ふと思い出したように不思議そうな顔をする。
「あぁ…そのことなんだけど、白とか黒とかなんのことなのかわかってないんだ」
『へ…?わかってないでぼくを助けてくれたの…?』
こくりと頷くと、でもたしかにそうかぁ。と呟いて仄かに表情を暗くした。
彼はここでは黒が絶対であり白は悪であると信じ込まれていること、そのせいで真っ白な自分は差別を受けていることを説明してくれた。
そして、そんな中でも自分は黒いみんなと仲良くしたいとも言っていた。
『ぼくはみんなと仲良くしたいから街には行くけど、ここじゃ白いと差別対象だから、街に行く時はぼくから離れていたほうがいいよ』
そう笑った彼は潰れそうな程に苦しく見えた。
僕は白でも黒でもないよ、と言うことしかできなかった。
翌朝、瞼を刺すような光で目が覚めてしまった。
質素な窓から覗く太陽は眩しく、怠惰な睡眠を良しとしない非道い存在に思えたが、家の主が記憶を掠めて思考を放棄した。
起き出してみるとテーブルには硬いが綺麗なパンが置かれていて、先程浮かんだ彼はもう家には居なかった。手に入れるのも難しいだろうに。しっかりとしたものを食べれているのだろうか。
そんなことを思いながら締まったような喉にパンを半分押し込んだ。残りは彼に食べてもらおう。
彼は街に行っているのだろう。あんな仕打ちを受けてまで、なおも彼はひとと仲良くしたいのだろうか。僕にはわからない。右側が、揺らめいた。
暗い感情に覆われながら彼を探した。また虐げられているのだろうか。そんなことならもうやめてしまえばいいのに。どうして諦めずにいられるのだろう。
胸に広がる空虚を埋めるように白い体が目に入った。同時に、それを取り囲む黒い塊も。
『これ以上黒を乱す白を放っておけるか!!』
そんな怒声が所々から飛んでいる。
歪んだ白い顔から流れる液体を黒いなにかが隠してゆく。哀しい声が少しずつ潜もる。
無意識だった。右手が彼の手を掴み、足は黒の少ない方向へ地面を蹴っていた。
どれほど走っただろう。肺は上手く空気を取り込まず、心臓は破裂するほど胸を叩いていた。
もう街は小さくなり陽は高く昇っていた。
動かなくなった足を放り出し地面に背中を預ける。
後ろにいる白いのは半分くらい振り回されていただけだったからか、少し目を回しているくらいでフラフラとしていた。
荒くなった呼吸が少しずつ静かになる音だけがしばらく続いた。
「…こんな差別、きっと、無くならないよ。それでも君は…みんなと仲良くなりたいの?」
返事は無かった。代わりに俯いていた顔がこくりと肯定を示した。
「……そっか。君がそうしたいなら、止めないよ」
きっと僕には、どうにもできない。彼の物語にハッピーエンドはないんだ。
『きみはさ』
ふっと彼が口を開く。
『白と黒、どっちなの?』
「…僕は」
僕は。
「どっちでも、ないんだ。自分がわからないんだ。たぶん、何色でもないんだ」
他のひとに合わせ続けたツケだ、と無理に笑った。
『ぼくはさ、黒がよかったよ。野蛮だし、酷い黒だけどさ、それでもみんなと同じ色がよかった。きみは味方かもしれないと思ってたけど、やっぱりひとりぼっちなんだ』
「…今日は帰ろうよ。泊めてくれると助かるな」
僕は鼓膜を揺らしたその言葉を聞こえなかったことにした。
渡そうと思っていたパンの片割れはどこかに無くしてしまったようだった。
居心地の悪さを誤魔化すように食事を断って早くに眠りに就いた。陽はまだ沈み切っていなかったかもしれない。それでも眠ってしまいたかった。体の色に反して暗い顔の彼を見ることができなかった。
深くは眠れなかった。酷い夢を見た気がする。
目が乾いてまだ眠気が残っているように錯覚する。
朝日が昇ってきた頃だろうか、外はまだ薄暗い。
起き上がるのがつらい。なにも考えたくない。嫌な虚脱感に全身が襲われる。
押し潰してくるような黒い何かから逃げるように目を閉じた。次に目を覚ましたら世界中が優しさに包まれていると信じて。
思っていたよりも夢の中をさ迷っていたらしい。朦朧とする意識が緩やかに現実へ引き戻される。
ふと白い体が脳裏に浮かんだ。そうだ、彼は。
家の中を見て回ると誰も居なかった。
窓の外から、とても遠い所からなんだか潜もった悲鳴が聞こえた気がしたが、きっと気の所為だろう。
聞こえていたような錯覚をしていた音を掻き消すように紙を捲るような音が体を包み視界がなにかに遮られた。
〜To be continued〜