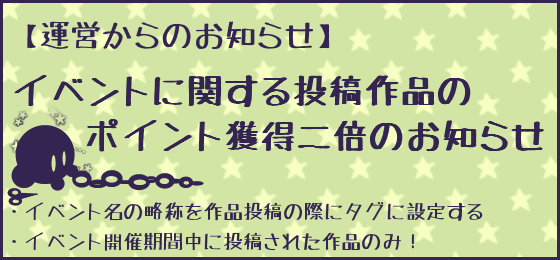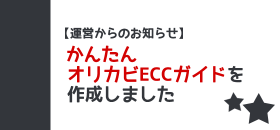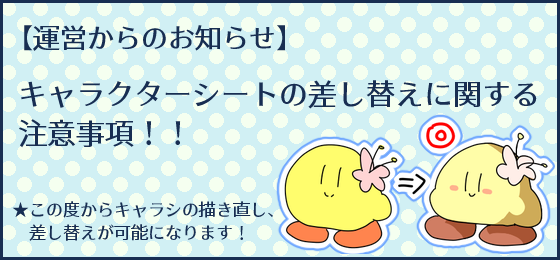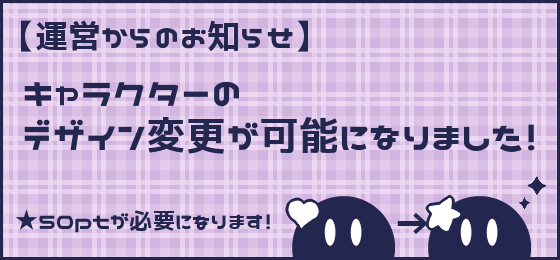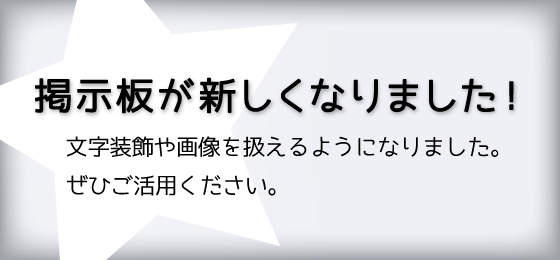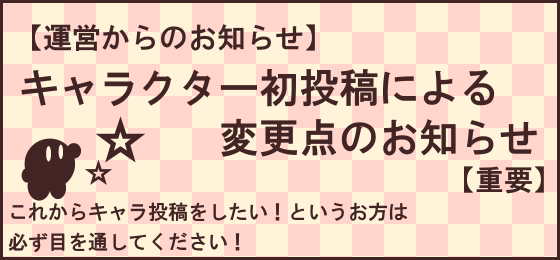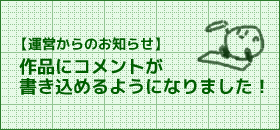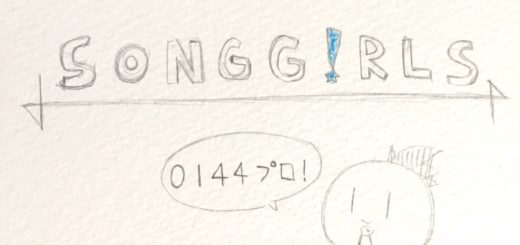湿っぽい空気の中、少し埃っぽい本の背表紙を何を探すわけでもなく眺めながら歩いていた。
踏み出すごとに深緋の絨毯に足が沈み、舞い上がった塵がやわく光った。
しんとした図書館に遠くから雨の音が静かに響き、柔らかく木霊する絹のような水音にふと気持ちが緩んで深く息を吐き出す。
こんな穏やかな優しい時間が永遠に続けばいいのに、なんてどうしようもないちっぽけな願いを胸の奥にしまい込みまた背表紙を物色する。ふと目に飛び込んできた薄花色にやけに胸が高鳴った。零れかけた息を飲み込み、ゆっくりと右手を伸ばし割れ物を触れるように優しくその本を棚から抜き出した。
《月に恋した少女》
この本のタイトルと思しき文字の下には月に微笑みを向ける少女の絵が描かれていた。
パラパラと紙を捲ってみるとどこか陰鬱な雰囲気の挿絵が何枚も続いていて、しばらくすると真っ白なページで残りが埋まっていた。
なにかの仕掛けだろうかと最後のページまで飛ばしてみたが結局なにも描かれていないページしか無く、ため息を吐いて本を戻そうと棚に目を向けると本来そこにぽっかり空いているはずのスペースが所狭しと他の本で埋められていた。
おかしいな、と思い絵本に目を落とすと月に微笑んでいた少女がこちらに怪しい笑顔を浮かべていた。
『シゥイト・エセ・ヴォート』
少女の口に合わせてそんな音が聞こえた瞬間全ての色が眩んで視界が明色に包まれ思わず目を閉じてしまった。
瞼の向こうの光が緩み、細く目を開けると異様に影の濃い緑が茂る森の中に立っていた。
一瞬思考が停止する。ここは一体どこだ?
不意に脳裏によぎった「本の中に迷い込んだ」という考えにそんな非現実的なと言葉をぶつけ相殺した。
どこを見渡しても今まで居た図書館は面影すらない。とにかくおかしな場所へ迷い込んだことだけは確かなようだ。
困ったな、と顔をしかめていると背後から鈍色のイヌのような生き物が右半身の中をすり抜けて行った。
「いっ…!?!?!えっ?!」
間抜けな叫びにワンテンポ遅れその生き物の着地音が聞こえる。
砂埃をあげながら再びこちらに狙いを定めたソレは牙を剥き出し四つの目玉をギョロギョロとさせ地面を蹴った。
「う、わぁあ!!」
叫びながら右側を変形させ飛んできたものを強く押していなす。と同時に地面を蹴り込みなるべく距離を取った。
なんだアイツは、ここはどこだ、誰か助けは、様々な思考が頭を這い回り頭が鈍く痛んだ。
鈍色のソレは唸り声をあげながら再度こちらに狙いを定めたようだった。
参ったな、と思いながら次の襲撃に備え右半身を変形させる。なんとか見逃して貰えれば、なんて思ったが生憎なことにヤツには理性なんてものがあるようには到底思えなかった。
そんなことを思っているうちに向こうは蹴り出しを終え一直線に迫って来ていた。
息を整え、タイミングを合わせ…飛び上がる瞬間目の前に右半身の壁を作…ろうとした刹那鈍色の横線が見えそいつは木に叩きつけられていた。
『キミ、大丈夫?』
そう言って彼は眩しい笑顔を向けてきた。
「え、あぁ、大丈夫です。えーと、ありがとう…」
歯切れ悪く答えると彼はよかったよかったとまた笑顔を向けてきた。
「ええと、ところであなたは?」
『あぁ、そうだな、ちょっと待ってくれるか?』
そう言った彼は茂みの向こうに声をかけ、大きく手を振り、仲間のようなひとたちを呼んだ。
『俺らは勇者一行でな。俺はその仲間だ』
いかにも誇らしそうに彼は胸を張り白い歯を見せた。
『ちょ、ちょっと勇者一行なんて…ボクはそんな…勇気もないし…』
そう言った青年が恥ずかしそうにこちらを見て、一応勇者と呼ばれています、とお辞儀をしてきた。
それを見た仲間もからかうように笑いながら挨拶をくれた。
『ところでキミはこんなところでなにをしてるんだ?こんな魔物だらけの森で危ないだろう』
そう言われて少し戸惑った。
「いや…なにをしてると言われても…気付いたらここに来てしまっていたみたいで…」
『ふむ…じゃあ俺達が安全なところまで案内しよう。な、みんないいだろ?』
少し不思議そうな顔をされたが彼はすぐに笑顔に戻りそう言った。
「あー…すごくありがたいんだけど…なんかちょっと申し訳ないというか…」
『む…そうか…じゃあ少しの間俺達の魔物退治に付き合ってくれないか?それでおあいこだ』
相変わらずの眩しい表情で彼は述べた。
「魔物退治…まぁ、やれる範囲なら…」
『決まりだ。少しの間だけどよろしくな』
魔物と呼ばれたもの、それでも生き物を殺めることは少し気が引けたが己が生きるためには仕方ないと割り切って彼らについて行くことにした。
始めの日は魔物を倒していく姿を見ることしかできなかった。そもそも僕は戦闘向きではないから戦う術をあまり知らないのだ。
遠くで荷物を預かり右手を伸ばして武器を渡すこと、どんな戦いをするのかを見ることに徹した。
その日はなんとなく思い切り相手を殴ればなんとかなるという結論に達したので、明日からは右半身を上手く使って相手をぶん殴ろうと決めた。
生き物の死を目の当たりにしながらどこか冷めていてあまり感慨がない自分にに少し嫌気がさした。
その日の夕飯はみんな疲れてるだろうからと僕が担当した。可もなく不可もなくといった味で、あまり多くは食べる気になれなかった。というかアイスが食べたかった。
それでもみんなは美味しいと言ってくれ、色々な話を聞かせてくれた。きっといい仲間とはこういう人達のことなんだろうな、なんてどこか淋しさを覚えながら頭の中で呟いた。
食事を終え各々が床に入り始める頃、夜はあまり寝付けないからと見張りをすることにした。ひとりでは流石に心配だからと勇者と呼ばれた人も一緒に見張ってくれることになった。
一瞬断ろうかと思ったがひとりで魔物に勝てる自信がなかったので言葉に甘えておくことにした。
『キミはさ、勇者ってどんな人のことだと思う?』
小さくなった焚き火を突きながら零れるようにそんな問いが投げられた。
「うーん…勇者、ねぇ…」
考えながら空を見上げた。木々の隙間から煌めく星が僕の目に落ち込み少しぼやけた。
「みんなが勇者って言えば勇者なんじゃない?僕にはよくわかんないや」
そう言って欠伸を噛み殺し冷たい夜を吸い込んだ。
『みんなには勇者なんて言われるけどさ、ボクはこれっぽちも勇気がないし…勇者の資格なんてないんだけどなぁ…』
そう言った炎の映りこんだ目から一滴の雫が落ちた。
きっと彼の焦燥はあの程度の涙では潤わないんだろう、だからといって僕にはなにもできない。
そう思って風に囁く木を見つめていると後からそろそろ交代の時間だ、と声が聞こえた。
『交代だって。おやすみ』
そう僕に言い残した彼は少しのつらさを残して微笑んでいた。きっと彼は勇気がないなんて言うけれどとても強い人なんだろう。
「…おやすみ」
彼のいなくなった場所に声を残し僕も床へと向かった。
『ほら起きろ!勇者御一行の朝は早いぜ!』
朝になり笑顔の眩しい彼に叩き起された。うーん…あと5年寝かせて…
そんな願いも虚しく布団を剥がされてしまい欠伸をしながら朝食を摂った。
「ふぁ…今日も昨日と同じ感じ?」
『そうだな、でも今日は少し親玉に近づくから魔物が少し強くなるかもしれんな』
今日は戦うのやめて明日から本気を出そう。
『昨日俺達の戦いっぷりバッチリ見てたよな!今日からは戦力として頼むぜ!』
「アッ、ハイ」
どうやら今日は僕の命日になるかもしれない。
遺書の内容を考えながら支度を済ませ旅は再開された。
進むにつれてどんどん濃くなる緑を掻き分け、魔物が出てきたらそれを退け、だいぶ進んだところで休憩をすることになった。
ここまで来ると魔物の動きが今までとはまるで違う。親玉の魔力に触れて知能レベルが上がっているとは聞いていたけれどそれだけでみんなの疲労度がここまで高まってしまうとは思っていなかった。
今までは単純に突っ込んでくるだけだった魔物が連携を組みフェイントもかけてくるようになった。そのせいで苦戦し、スタミナがどんどん奪われていくのだ。
今日はもうここで休んで明日からまた出れば良くない?ダメ?そっか。
そう思っているとふと勇者と呼ばれた人が目に入った。みんなクタクタに疲れている中でひとりだけ疲労がそこまで見られなかった。
それなのにどこか酷く疲れ切ってしまったような顔をしていて今にも消えてしまいそうにも見えた。
僕はそれを見なかったことにした。
休憩を終えて再び出発し、魔物と対峙し、倒しまた進んだ。それを繰り返す中で戦う勇者と呼ばれた人を見ていたが昨日と同じく向かってきた敵だけを斬る、それだけではあるものの、昨日とは違い振り下ろす手に迷いが無くなっていたことに僕は気付けなかった。
そうしてまた夜が来て夕飯をみんなで囲んだ。
今日は勇者と呼ばれた人が作ったらしいが、なんとなく塩味が足りない気がした。でもきっと今日は汗をかいたからだろう、そう思った。
夕飯を終え、また交代で見張りをして星を眺めた。
勇者と呼ばれた人は一度も話しかけてくることがなかった。
また朝が来て豪快に布団を剥がされた。
『勇者御一行の朝は早ぁーい!!』
「あと500年寝かせて…」
『そんなに寝たら骨も残らんだろうが!!そんなことより今日は親玉を叩く!朝から豪華な飯が出来てるから早く来い!』
そう言われ渋々起き上がり朝食を取りに向かう。
「……あの、これは?」
『昨日倒した魔物だな!コイツは脂がのってて旨いんだ!』
僕の目の前にはそれは大きな肉の塊が香ばしい香りを漂わせて鎮座していた。
「いや、こんなに食べられませんって」
肉の乗った皿を彼の前に置き、首を横に振る。
『でも今日は親玉と戦うんだから体力付けておかないと死ぬぞ?』
そんな笑顔で言われても困る。
「いやほんと、半分でいいので…」
『そうか…じゃあ半分は俺が食うぞ?いいんだな?本当にいいんだな??』
いいんだなといいながら少し嬉しそうにしているのは気にしないことにして、半分になった肉をなんとか胃に押し込んだ。これでも多いくらいだ…
サクッと片付けをして魔物の親玉を倒すために出発することになった。勇者と呼ばれた人がなんだかいつもより笑っているように見えた。そしてどこか小さな不安感を覚えたけれど、なんでもないだろうと思った。
早々に発ち、茂みの中を進みなるべく戦闘を避けながら親玉の目星を付けた場所へと向かっていた。途中に出てくる魔物が独自の言語のようなものを口から漏らし、刃を向けると助けを乞うような言葉を発する者も出てきたことが親玉の近くに来たのだと実感させられる。
昨日までは向かってくる敵だけを捌いていた勇者と呼ばれた人が咽び泣く魔物を一番に斬り捨てたことには驚いた。彼の中でなにかが変わってしまったのだろうか。
そうして魔物を倒し、時には迂回をし親玉の棲むと言われている洞窟に辿り着いた。
『いよいよ最後の魔物だ。これまでのヤツらとは格が違うぞ、気を引き締めていけ!』
その叱咤激励にパーティにピリッと緊張が走る。
ゆっくりと洞窟に足を踏み入れ奥へと進む。
ひやりと湿った空気に吐き気を催す生臭さが加わり気分が悪くなる。
チカチカする頭をなんとか現世に留めながら更に奥へ進むと松明に飾られた石の祭壇のようなものがあり、その上に巨大な魔物が荒い鼻息を立てぐっすりと眠っていた。
松明の灯を浴びてテラテラと光を反射する体表に締め付けられるような恐怖を感じた。
不意に足元の石を蹴ってしまいその音に敏感に反応した魔物がギョロリと黄色い眼を見開いた。
『寝首を掻ければ…とも思ってたがこれで起きるようじゃハナから無理だったな…!お前ら!行くぞ!』
誰よりも元気な彼が先陣を切って魔物に飛びかかった。
それに続きひとり、ふたりと魔物に攻撃を与えていく。
僕も少し遠くから魔物の隙を突いて着実にダメージを稼ぐ。
そんな中勇者と呼ばれた彼ひとりは積極的に飛びかかれずただ剣を握り攻撃を躱し続けていた。
戦いは長引き、誰もが火傷に裂傷に打撲、様々な傷を負い不利な状況に追い込まれていることは誰の目にも明らかだった。
魔物は未だに多くの体力を残しているようで疲れ切ったガードは容易く破られるようになっていた。このままではきっと全員殺されてしまう、そう思った時勇者と呼ばれていた彼の動きが止まった。
『ハァ…おい…っ!勇者!なにやってんだ!…ッグ!!……止まんな…!』
激戦の中に飛ぶそんな声を彼には届かないようで腕をだらりと下げて焦点の合わない目で虚空を見つめていた。
『これじゃあ勇者とは、名乗れない…』
そう呟いた彼はギラリと鋭い目を仲間に向け大きく剣を振った。
『なんで?』と口だけが告げた仲間がひとり紅い液体に沈んだ。
『おい、勇者…?なにしてるんだ?おい!勇者!!』
そう叫んで彼は勇者だった彼の胸倉に掴みかかった。直後、背中から飛び出した剣から、口から血を流しその場に倒れ込んだ。
彼は勇者と呼ばれていただけあり、誰よりも強かった。
危険を察知して隅の方で右半身の色を変え身を隠していたし彼は頭に血が上っているのか僕が居たなんて忘れているようだったので僕は助かったけれど、そこには無惨にも血の海が広がっていた。
そこに佇む彼はもはや〝勇者〟と呼ぶよりも〝魔王〟と呼んだほうがしっくりくるかもしれない。
動かなくなった仲間だった塊と辺りに漂う錆び臭さと生臭さで吐き気がしてきた。
『魔物の王。人の言葉を理解していると聞く。わかるんだろう?』
『……あぁ。人の子よ、何が目的だ?』
地を這うような低い声が響いた。
『ボクの魂を売る。だから、ボクを魔物にしてくれ』
『ほう…数多の我が同胞を殺めておいて…随分と図々しいな』
『だからボクは今仲間を皆殺しにしたんじゃないか。さぁ、ボクを魂を喰らってくれ』
そう言った彼の目は既に人とは言えないほどにギラギラと光っていて心すら失ってしまったように見えた。
『そうか…では貴様の魂、我が貰い受けよう。そして貴様は今から我々魔物として生きるがいい』
魔物は溢れる笑いを堪えられないように目を細め、彼の胸から仄めく何かを取り出し大口に呑み込んだ。
瞬間、魔物の傷はみるみる癒えて満足げな顔をして祭壇に戻り、もう行けと言い再び眠りについた。
彼が洞窟から出るところにこっそりついて行きやっとの思いで洞窟から出られた。
まだ姿を見せたら殺されてしまうかもしれないと思っていたが、彼からは殺気を感じないどころか深い悲哀が辺りに広がっていた。
「……どうしてあんなことを?」
彼の隣に座りなるべく優しく聞く。
『あ…キミ、生きてたんだ…』
振り向くと同時に彼の目から大粒の涙がボロボロ零れた。
『…ボクは…勇気がないからっ…魔物になってしまえば…勇気がでると思って…』
「きみは僕に勇者がどんな人だと思うか聞いてきたね」
彼から目を逸らし前を向く。
「僕はきみたちを見て人に勇気を与えられる人が勇者だと思ったよ」
空を仰ぎなるべく軽く声を吐く。
「君の思う勇気なんてさ、無くてもいいんじゃない?きみはたとえ勇気がなくても人に勇気を与えられる勇者だったんだと思うよ?それだけでもよかったんじゃないかと思ったよ僕は」
空から目を落とし抑揚を抑える。
「まぁ、もう手遅れなんだろうけど」
そう吐き捨てて彼に微笑みかける。
その瞬間、彼は抑えきれなくなったのか嗚咽を漏らし始めた。仲間の名前を呼び、ごめんなさいと叫んだ。
そして最後にもう勇者ではないボクを殺してくれと懇願してきた。
「あぁ、きみはもう勇者じゃない。ただの人殺しだ…だから、それでいいのかもしれないね」
そうして彼から受け取った剣を彼に向ける。
「きみは間違った選択をした。でも気持ちはわかる…だって、僕も…」
その言葉が続くより先に目の前がまた光に包まれた。手の中にある剣の感覚が薄れてゆくのを感じた。遠くから風で紙が捲れるような音がした。
明色が消え目を開けると、先程とは打って変わって真っ黒に染まった世界に来ていた。
〜To be continued〜