「また落ち込んでる」
雨音に紛れた感情の篭っていないような声。
この声を聞くのは二度目だった。
大量の水の粒が地面を打つ音の中、木の下で雨宿りをしながら体が汚れるのは嫌だから『休みたい』という気持ちを形にしてその上に寝転んだ。
気を抜くと消えてしまうがこの右半身はとても便利だ。別になりたくてなったわけでもない自分の体質に感謝しながら雨の音を聞いていた。
「雨っていいねぇ…綺麗で、それなのに憂鬱で…周りの音なんかかき消しちゃう。この雨の中歩いてたらいつの間にか雨と混ざって溶けて、消えてしまえたらいいのにな…」
誰にも聞かれないだろうと思ってそんなことを呟いていると見慣れない人影を見つけた。
「あれ…あの人…こんな大雨の中なにしてんだ…?ていうか誰だろ…」
不思議に思いつい凝視していると相手が見られていることに気付いたらしく、するすると滑るように近づいてきた。
「憂鬱な感情を察知…落ち込んでる?」
いきなり話しかけられ他に人などいるはずもないのにきょろきょろとしてようやく自分に話しかけられたのだと理解した。
「あー…僕はえっと、うん、大丈夫、です。あ、ところで…えーと…どなたでしょう…?」
驚きと緊張と、初対面だから少しは礼儀正しくとの思いでしどろもどろとしながら返事をした。
「僕は雨冷…」
「憂い?あ、僕の名前にも憂いって入ってるんですよ!幽憂って名前なんです。」
名前に同じ文字があると親近感が湧くな、なんて思いながら地面に幽憂と書いてみせた。
「字、違う。」
彼はそう言いながら空中に雨冷と書いた。
「えっ…違うの…そういう字なんだ…雨冷くんね、覚えた」
完全に憂だと思っていたので少しショックを受けて僕の右側が深い青にぼんやりと光った。
そういえば挨拶に必死で彼のことをよく見てなかったな、と思い近くに来てよくピントが合うようになった彼を見つめた。
澄んだ目をした…いや、片目だけ澄んでいてもう片方は濁っている。表情が読めない人だな。彼にもなにかあったんだろう、僕と似た目をしている。そんなことをぼんやり考えながら見ているとあることに気がついた。
「あれ…?雨冷くん、君浮いてない?いやこの世界じゃそんな珍しいことでもないか…」
珍しいことではないと思いながらもどこか違和感を覚え、つい口にしてしまった。
「僕、幽霊だから。生前になにがあったのか思い出せないけど」
「へぇ…幽霊なん…えっ…!?あぁ、幽霊ね。そうなんだ〜」
一瞬驚いた。でもそんなに驚くことではないな、ただの幽霊じゃないか。悪い人でもなさそうだし。なんて呑気なことを思いながら彼のことをもう一度よく見た。
「そういえば雨冷くんはなんでここに?」
なるべく明るく、嫌な印象を持たせないように。そう気を付けながら笑顔を向けた。
「憂鬱な気持ちを察知したから。君、落ち込んでるでしょう?」
彼の言葉に目を見張った。どうして?なぜ?そんなに顔に出てたか?いや笑いかけたはずだ。じゃあなんで?僕は混乱のあまり下に敷いていたものの形が崩れ、地面に尻をついてしまった。
「え…と、わかる…?の…?顔に出てる…?バレちゃってる…?」
雨に溶けてしまいそうなほどか細い声が出た。
なるべく隠していたい気持ちを初対面の人に感づかれてしまい、そんな自分が見られるのが嫌で目をそらしてしまった。
「何か話したいことがあれば聞くよ…力になれないかもしれないけど…」
どこか慣れたような風にそんなことを言う。
おかしいだろう。死んでしまって、濁ったどこか優しい目をして。どう見たって雨冷くんのほうがつらいことが多そうじゃないか…それなのにどうして僕の思いまで背負ってくれようとしているんだ。
自分の片割れを更に深く染めながらそんな伝わらない想いを心で呟く。
「話したかったらでいいよ…」
気持ちを察してなのか、控えめで抑揚のない声が僕に届いた。
自分の気持ちをわかってくれる、それを聞いてくれる。相手はただの暇つぶしか気まぐれかもしれないがその言葉に少し目が潤む。
つらいことが多いぶんわかってくれることもあるのかもしれない。僕のように他の人の話でひとりじゃないと救われているのかもしれない。広い世界だ、そんな人がいたって不思議じゃない。そんなことを考えたら少し話してみようという気になった。
「ちょっと恥ずかしいけど…色々と聞いてくれる…かな…」
僕は俯きながら、いつもは心の内に閉じ込めている言葉を拙く紡ぎ、口から吐き出し始めた。
「どこから話そう。そうだな、僕がまだちゃんとした球体だった頃の話からかな…」
照れ隠しに水たまりに広がる波紋を見ながら言う。しかし右半身は嘘を吐けずにうっすらと桃色に染まる。
「僕は昔…何年前だったかな、もう忘れちゃったけど何年か前までは普通の球体だったんだ。まぁ、今が異常なのかって言われたらそうじゃない……とは言いきれないな。うん」
やはりどうも恥ずかしくてつまらない冗談を吐く。しかし彼は無言のまま僕から少し離れた所を見ていたので冗談は無かったことにして話を続ける。
「昔っから憂鬱なことは結構考える方でね、生きる意味とかそういうの見失ってこれからどうしようかって思ってる時に…ある人に出逢ったんだ」
彼女の名前を彼に伝えることも自分が口に出すことも抵抗があったので僕は名前は出さないことにした。
「僕ってどうも他人を見るとバケモノを見てるような気分になっちゃって苦手なんだけど、その人だけはなんだか綺麗に見えてね。その人のこと気に入っちゃったんだよ」
右半身に藍色と黒を渦巻かせ目を伏せた。彼女の顔を思い出そうとしたが、記憶に霧がかっていて思い出せない。
「しばらくしてその人と仲良くなって、毎日話て、暇な日は遊んで、ふたりで笑って。一年くらいだったかな?そんな毎日を送っていたんだけどね、ある日突然連絡が取れなくなったんだ。返事忘れたのかなってしばらくは思ってて、ずっと返事を待ってたんだ。たしか半年くらい待ったよ」
「…疑わなかったの?」
もっともな疑問が僕に投げられる。当たり前だ、半年も疑わず待ってる人は普通じゃないだろう。
「もちろんもう連絡は取れないし会うこともできないと思ったよ。まぁそれも4ヵ月くらいしてからなんだけどね」
無表情の彼の顔が少しだけ歪んだ気がした。
やはり変なやつだと思われたのだろうと思ったその時、頬にひんやりとした水気を感じた。
「あれ?雨漏り…じゃない…な、ちょっと待ってね…」
なぜか一粒だけ溢れてしまったその液体をぐっと堪え、顔をごしごしと擦る。
「…その頃、毎日泣いてたの?」
唐突に彼の口からそんな言葉が発せられるものだから驚いて彼の顔を見た。
フードの奥でぼんやりと右目を光らせた彼は言葉を続けた。
「相当つらかったんだろうね…」
言葉を選んでくれてよかった。『つらかったね』と言われていたら雨が降る場所が増えていた。
「まぁ、あの頃はね。で、続きなんだけど連絡が途絶えてからだいたい半年くらいで突然連絡が来たんだ。久しぶり、覚えてる?ってね。そりゃ覚えてるだろ…待ってたんだから…」
顔では笑うように努めたが、右側はどうしても藍色のままだった。
「そっからは楽しかったよ。また毎日話したり遊んだり。でも途中から、なんでかな、喧嘩することが増えてさ。僕は怒ってないんだけどあの人がめちゃくちゃに怒ってくるんだよ。それに僕だって悪いことしてないんだよ?全部あの人のわがまま」
おどけて見せようとしたけれど、僕の片割れはどんどん深い色に染まっていく。
「そこからさ、どんどんエスカレートして、僕の人格っていうか性格?そういうの全否定されてさ。真逆の性格の人になれって言うんだよ。ま、元々僕の中身なんてからっぽ同然だったからその時はなんとかなったんだ」
「…そっか…そんなに…たくさんのことを…」
目から燐光を発しながら彼が呟く。
「あのー…その目って…ずっと光ってるけど……なにかの能力?」
さっきまではただ目が光る体質なんだと思っていたが『そんなにたくさん』という言葉に引っかかりを覚え、尋ねてみる。
「これはパスト・アイ…おおまかにだけど、これで見た人の過去の記憶が見えるんだ…」
彼は右目の下瞼あたりを優しく撫でながらそう教えてくれた。
なるほど。それで結構飛ばしてる僕の話でもこんなに理解してくれてるのか。
そこでふと疑問に思う。
「ん?でも見えるなら僕話さなくてもよくない?」
「話した方が…軽くなるでしょ…」
たしかにごもっともだ。
「そうだね…じゃあ続きを。どこまで話したかな?」
気を取り直し、また水面に目を落とし記憶を辿って当時のことを思い返す。
「僕が変わってきたところまで話したかな?その頃から僕はどんどん変わっていったよ。あの人がそれを望んだからね。一番変わったところと言ったらそうだな、怒るようになった。あの人にだけは。怒ってほしいってさ、なかなか変な要求だよね」
そう言って軽快にハハハと笑ってみたものの、僕の気持ちは晴れないようで深い海の底のような色をしていた。
「それで怒るようになってからさ、どんどん調子乗ってさ。あ、あの人がね?僕の嫌がる事をやりたい放題。お願いだからやめてって言ってもやめない。絶対にしないで、約束だよ。そう約束したのにやめない。むしろエスカレートしたよ」
僕の心に赤味が刺した。
僕はされたこと、してしまったことを覚えてる限り、話せる内容のものを選んで彼に話した。本当は言うべきではないのかもしれないが吐き出したかった。
「わがままはエスカレートしていって、僕も無理して全部聞けるようにしてさ、そしたらいつの間にか僕の半分から右側がこんなになってたんだ。感情が溢れた、とでも言うのかな」
朱に染まり、黒みを帯びてきた右手を軽く振ってみせた。
「嫌だから絶対にやめてって何度も言ったんだ。それなのにやめないし、やる回数もどんどん増えた。こんな身体になったけど僕はまだ注意するだけで留めたんだ」
声が震えた。思い出しただけで怒りが全身を駆け巡るのを感じた。右半身は既に燃え上がり、どす黒い感情をうねらせていた。
「何度も何度も何度も何度も何度も…やめろって言ったのに……!!!殺意だって湧くだろ…っ!」
行き場のない怒りは形となり、どうしようもなく自分に向けられ、今にも握り潰そうととしていた。
「お、おちついて…」
その声にハッとなり頭を潰えようとしていたものは湿った空気に溶けた。
「ごめん…つい…」
落ち着きを取り戻し、一度座り直してから話を続行する。
「えーと、それでね、そこから殺意も湧くわけでして、怪我させちゃったんだよ。その人のこと」
笑おうとしたけれど、乾いた笑いしか出なかったので強がるのは今日はやめておこう。そう思った。
「というかこのあたりは…見てくれる?ちょっと言うのもつらくて…」
もう情けない声しか出てこない。一度気を抜くとダメだ。守る手段も攻撃の手段も無くなったような無気力感に襲われる。
彼は無言で僕を見据え、蛍火のような目を瞬かせた。
今、彼には僕の過去が筒抜けなのか。しかし綺麗な目をしているな。ぼんやりとしているけれど、優しさが詰まっているような。そんな目だな。なんてことを考えていると彼が口を開いた。
「だいたいのことはわかったよ…君も色々あったんだね…」
僕から目を背けながら無表情でそんなことを言う。言葉にも抑揚がないからどう思っているのかはまるでわからない。
「それで…今はその人のことどう思ってるの…?」
彼の口からそういう質問が来るとは思っていなかったので一瞬言葉に詰まる。
「あー…えーと…んー…そうだね、また会えるなら会いたいかなぁ」
「…あんなに色々あったのに?」
「まぁ色々あったけどさ、それでも綺麗なもんは綺麗だし」
彼はよくわからないと言いたげな顔をしている…気がした。あくまでも無表情だ。
「暗い話聞かせちゃってごめんね、初対面なのに。あと途中ちょっと荒れてごめん」
そう言って伸びをすると座り続けで凝った背中によく効いた。
ひとつあくびをして雨音がしなくなっている事に気が付いた。
「お、雨上がったね。見てあれ、雲間から光差してるよ。フェイス様降臨〜なんてね」
朗らかに笑って今までの内容を吹き飛ばしてしまおうなんて思い、冗談混じりの言葉と共に振り向くとそこにいたはずの彼の姿が無くなっていた。
「あれ…?どこ行ったんだ?…あー、幽霊だから陽の光に弱いのかな?雨冷って名前も雨の日にしか出ないからとかそんな感じでつけられたのかなー」
独り言をぼやきながらまたひとつあくびをする。
「まぁ、すっきりしたよ。ありがとう」
まだそこに居るんじゃないかなと思いさっきまで彼が居た場所に話しかける。
返事が無いことを確認して、言葉を零す。
「また雨の日に会えるかなー」
落ち込むことも多々あるけれど僕は朗らかなんだ。そう自分に言い聞かせ淡い黄緑色の片身と共に帰路についた。
「また雨か…結構降ってるよー…僕もこの中に溶けて消えたいなー」
こんな考え何回目だと思いながらひとり呟く。
「雨にも溶けたいし夜にも溶けたいしそのまま消えて人々の記憶からも僕が消えたいよ〜」
ベッドの代わりに作り出した右半身の上を転がりながら虚空に駄々をこねる。
「また落ち込んでる」
雨音に紛れた感情の篭っていないような声。
この声を聞くのは二度目だった。
「あ、その声…また会えたね」
僕は少し微笑んで彼を隣に招く。
「また僕の気持ちを察知して来たの?」
「まぁ…そんなかんじ…」
僕はあははと軽く笑って彼に告げる。
「あ、そうだ。この前はありがとうね、ちょっとすっきりしたよ」
「そう…ならよかった」
相変わらず抑揚のない声が僕に届く。
「今日も話聞いてくれるの?」
「…話したいなら聞くよ…」
無表情のまま彼はそう答える。
「そっか、ありがとう。じゃあ今日はそうだな…いつの話をしようかな」
僕は右手をくるくると遊ばせながら思考を巡らせる。
「僕が最近嬉しかったことでも話そうか。明るい話題は元気になれるしね。あれは雨が降っている日だったな。僕はある幽霊と出逢ったんだ…」
〜Fin〜


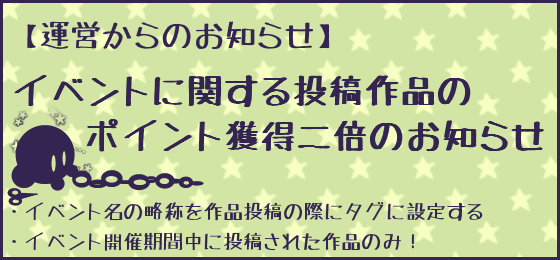
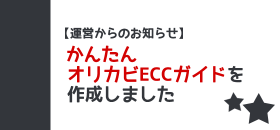
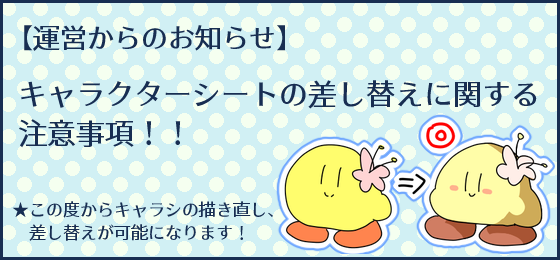
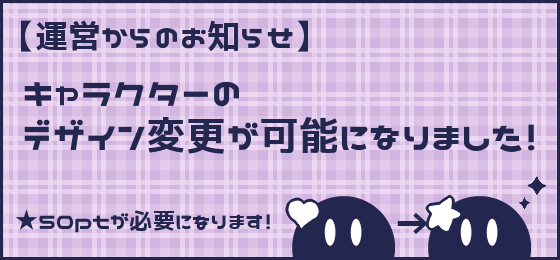
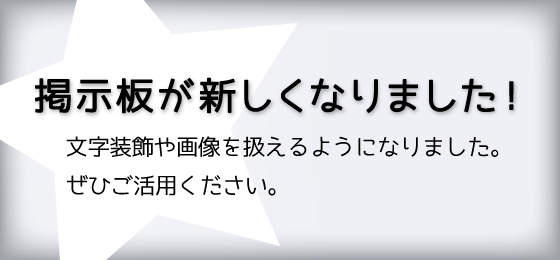
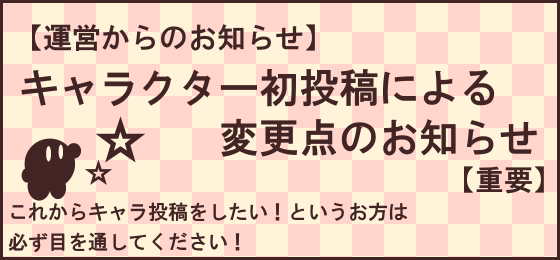
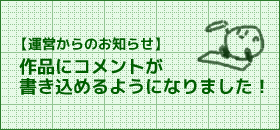



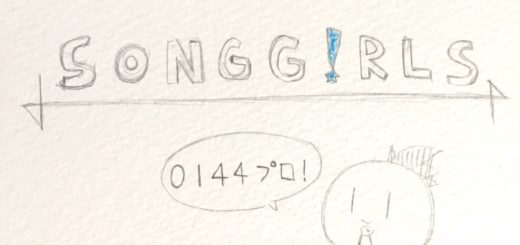




しっとりと心に染み入るようなお話でした。けして明るい話ではないけれど、読み終わった後になんだかほっとするような、不思議な魅力を感じます。雨冷さんの、さりげなく寄り添うような優しさが素敵です。
ありがとうございます〜!!
雨冷くんはきっと優しく聞いてくれるだろうなという願いのもと書いてました…幽憂くんは自己紹介しただけです。