「集まってもらって早々だが、ここで1つ言いたいことがある」
「何かな、ラレイヴ君」
「次のダンジョンなのだけど、場所が深海との事で侵入方法がない」
「…というと?」
「入りようがないのでこのパーティはここでお別れとする。ということでお疲れ様!解散ー!」
「ちょっと待ったァァァ!!!」
ボクの意見に不満があったのか、ミアティスは突然大声で叫び出す。
横からトア君がまあまあと落ち着かせるが、ミアティスは御構い無しに叫び続ける。
「非常時だから集まれって言ったのはそっちだよ⁈」
「そうだね」
「それなのに集まって即解散はないだろう!!」
「確かに」
ミアティスから出されたもっともな意見に首を縦に振る。あちら側からしてみればごもっともな意見だ。
だけど無理なものは無理だ。どこにあるのか分かっていても厳しいのに、場所が分からないのでは潜りようがない。ピレドアテッジといい、ターンオーバータワーといい、どうしてこうも場所が特定不可能なダンジョンが多いのか。探すこっちの身にもなって欲しいものだ。
「とにかく、まずは行くための方法を考えないと」
「方法かぁ〜」
「ヴァブは何かあるかい?」
「お腹が空きました」
「……ツバキは?」
「…ん?何か言ったかい?」
「いっそのことその本を燃やしてやろうか」
ボクが低い声で脅しかけるが、ツバキはチラリとこちらを見た後読書へと戻る。
仕方なく何か方法はないかと頭を抱えこんでいると、本をパタリと閉じたツバキが突拍子もなく口を開いた。
「行きたいのか?ダンジョン」
「え…?いや、そうだけど。むしろそれをみんなで考えているんだけど?」
「ふーん。じゃあ行くか」
「…は?」
突然何を言い出すのかと思った瞬間、視界が突然暗転し全く別の空間に足をつけていた。
わけも分からず他のメンバーの顔を確認してみると、ツバキを除いた全員が驚きのあまり固まっている。
どういうことなのかさっぱり分からないけど、とりあえず言えることは1つ。
「ツバキ…君は一体何をしたんだい?ここは一体どこで……⁈」
「どこって…ダンジョン。来たかったんだろ?」
「いや、確かにそうだけども!そもそも本当にここは目的のダンジョンなのか⁈」
「ああ。正真正銘…ナイトメアウィッチという者から連れて行くよう頼まれたンガ•イェ•ルゥだ」
「んなっ⁈」
ウィッチに連れて行くように頼まれただって⁈ボクにはそんな事言ってなかったのにあいつ……!
だけどよくよく考えてみれば、今まで的確にダンジョン攻略をしてこれたのはウィッチの人選のおかげでもある。だからここに来るために必要な人を呼んでないわけがないんだ。
「だけど、どうやってここに…?」
「俺には数字を操る能力がある。その能力を使って先程までいた場所とダンジョンまでの距離を0にしたのさ」
「距離を0に⁈すごいすごーい!」
「まるで手品だね」
「お腹空いたなー」
「なるほど…」
ツバキの回答に各々が感想を漏らしている中、自分も首を縦に振りながら納得の素振りを見せる。
ボクはこれまで色々な能力を見てきたけど、まだまだ知らない能力もあるんだね。数字を操るっていうのはチートのような気もするけど。
「それじゃあ奥へと進もうか」
「おっけー!みんな行くよー!」
「あ!あんまり前に出過ぎは…もう」
軽快な足取りでウキウキと前を行くトア君を追いかけるようにボクらも歩みを前へと進める。
あたりにはどこを見ても苔だらけの岩肌が露出しており、足を地面へと着ける度にピチャピチャと水を弾く音が反響する。
ダンジョン内は一本道とシンプルで、妙な薄暗さはあるが今のところ灯りは必要なさそうだ。
これだけの条件だと楽そうに見えるけど、油断だけはしてはいけない。それに入った当初からずっと匂ってくる磯臭はかなりキツイものがある。この匂いに慣れるのは時間がかかりそうだし、一刻も早くここから抜け出すのがベストだろう。
「あー、ここの匂いは結構堪えるね…」
「そうですか?ぼくは好きですけどね」
「ヴァブさんの嗅覚はどうなってるんだ…」
「さあ?」
「見てみてよ。ツバキ君なんて露骨に嫌そうな顔してるよ?もはや引きつり過ぎて見るに堪えない顔になってるよ」
「そんなに嫌ですか?分からないですねー。それよりもお腹が空きすぎて気持ち悪いです。マジックで何か出せませんか?」
「いや、出せないから。そんなマジックをなんでも出せる四次元◯ケットみたいに言うのはやめてくれないかな?」
「えー…残念」
ヴァブはお腹をさすりながら嘆きの声を上げると、もの哀しそうに歩き続ける。この匂いを何とも思わないどころかご飯を要求してくるのには驚きだ。
だけどそれよりも衝撃的なのは、その隣で一言も発さずただただ耐えるように足を運んでいるツバキの顔だ。本当になんて顔をしているんだ、彼は。そんな、我慢できないほど嫌なのか。それとも体が拒否反応を起こして自然とあの顔になっているのか。どちらにせよ記憶に残る顔だということには違いない。
「そろそろ奥地に着いてもいいと思うんだけど…」
「きゃああぁぁぁぁ!!!!」
「トア君⁈」
突然聞こえてきたトア君の悲鳴に急いで駆けつけると、そこには後ろに手をついて倒れているトア君の姿があった。
「どうした⁈大丈夫かトア君!」
「ら、らら、ラレイヴ…あれ」
「一体何を見て…うおおあ?!」
トア君に指差された方向へと顔を向けると、視界に入りきらないほどの巨大な影に思わず驚きの声が漏れる。
なんだと思いつつよく目を凝らしてその姿を見てみると、目の前には少し黒みがかった深緑色の巨大なスクイッシーがこちらを見つめてそびえ立っていた。
攻撃されることを考えそっと身構えると、巨大なスクイッシーは背を向け何やらガチャガチャと用意をし始めた。
依然警戒心は解かぬままでその場に立ち尽くしていると、巨大なスクイッシーは腕に何かを抱えながらこちらに振り返ってきた。その物の正体に気がついたのと同時に、ヴァブが真っ先にスクイッシーへと飛び込んで行く。
「マキシムトマトォォォォ!!!」
「待つんだヴァブ!どう考えても怪し…」
と言いかけてる間にヴァブはすでにスクイッシーの腕へと着地し、真っ赤な果実へと手を伸ばしていた。
これはまずいと戦闘態勢へ入ろうとした瞬間、背後から「待った!」という声が耳に入ってきた。
「なんだいミアティス!早くしないとヴァブがッ」
「いやいや、よく見てよ!」
「え…?あっ」
言われた通りにヴァブの方を見つめてみると、ボクが危惧したような事態は起こっておらずヴァブは平然とした態度でマキシムトマトを幸せそうに口へと運んでいた。
やがて手を合わせ食べ終わったことを告げると、ヴァブは両手いっぱいにマキシムトマトを抱えてゆっくりと下へと降りてきた。
ヴァブはボクらの元へと近寄ってくると、抱え込んだマキシムトマトを一人一人に配り始める。
差し出されたマキシムトマトを受け取ると、ヴァブがゆっくりと口を開く。
「どうぞ。1人1つだそうです。美味しいですよ」
「美味しいって…よく警戒もなしにこれを食べに行けたね?」
「どんな相手であっても、食べ物を差し出されたら感謝を込めて頂く。それがぼくの流儀なんですよ」
「はあー…やれやれ」
ボクはため息を吐きながらも周りを見回してみると、みんな受け取ったマキシムトマトを美味しそうに食べていた。
仕方なく流れに身を任せ恐る恐る一口かじると、口の中で濃厚な果汁が溢れて思わず口元が緩む。どうやら普通のマキシムトマトのようだ。
最後の一口を口へと放り込みしっかりと味わうと、ボクは疑問に思ったことを口に出す。
「あのさ…1つ疑問なんだけど、何故マキシムトマトを…?」
「なんかよく分からないですけど、歓迎されてるみたいですよ?」
「歓迎…そんなこと分かるのかい?」
「なんというか、そんな気がするんですよ」
「それなら目的の夢のかけらがあるかどうか聞いてくれないかい?もうそろそろ俺は限界で……」
「大丈夫ー?ヴァブさん、ツバキさんが本当に具合悪そうなのでお願いしてもいいかな?」
「分かりました。聞いてみますね。トアはその人をお願いします」
「任せて!」
トア君は元気よく返事を返すと、顔色の悪そうなツバキを横に寝かせ介抱をし始める。
一方ヴァブはスクイッシーとジェスチャーでやり取りを交わすと、頭を下げこちらに戻ってきた。
「どうだった?」
「えーと、それらしい物をここ最近見つけたらしく、持ってきてくれるそうです」
「本当かい⁈運がいいな僕たち」
「ただし、条件があるそうです」
「条件…?」
ミアティスが首をかしげて難しそうな顔をしていると、目的の物を見つけたらしいスクイッシーがボクらの元へと戻ってきた。
スクイッシーが丸めていた太い腕を広げると、途端に七色の光が腕の上から溢れ出した。間違いない、この光は夢のかけらだ。
「うん、間違いないね」
「じゃあこれが夢のかけらなんだ…なんて美しい……!」
「食べられるんですか?」
「食べ物じゃないよ、ヴァブ。それで、条件って?」
「ああ…なんでも笑わせて欲しいらしいですよ」
「「笑い?!」」
ボクとミアティスが一斉に驚きの声を上げると、スクイッシーは目を輝かせながら何本もある腕をバタバタとさせる。
困ったな…まさかここに来て笑わせてくれなんてお題が出るなんて…誰かとコントでもやるか…?
突如課せられた課題に頭を悩ませていると、隣にいたミアティスが突然笑い出す。
「ふふふ…笑いを取れとは何とも簡単な課題だね」
「お、何か秘策でも?」
「僕は元マジシャンだよ?誰かを笑わせるくらい朝飯前さ」
「さっすがー!じゃあここは君に任せたよミアティス」
「ふふ、大船に乗った気で待っていたまえ。今魅せてあげるよ…摩訶不思議なファンタジックショーを!!」
そう言うと彼は紙吹雪を散らし独特なマジックショーを始めるのであった…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10分後−
「なんか…ショー自体は凄いんだけど……」
「スクイッシーが見てませんね」
確認のためにスクイッシーの方へと振り返ると、彼は興味を失ってしまったのか、キラキラと輝く夢のかけらを見つめていた。
そのことに気がついているのかいないのか、今だにショーを続けるミアティスの背中をポンと叩く。
「あの…とても言いにくいんだけど…」
「えっと…な、何かな…?」
あ、これはもう気がついてるけど続けてるパターンだ。すぐにでも泣きそうな顔をしているのが見て分かる。
だけど、ここは彼のためにもはっきりと言っておかなくては。
「すごく言いづらいんだけど…」
「待って!言わないでお願い!!」
「笑い…取れてないよ」
「ア”ア”ア”ア”ア”ア”ア”ア”!!!!!」
ボクの発した言葉を聞いた瞬間、奇声を上げながらミアティスは崩れ落ちてゆく。
ごめんね…でもこれ、現実なんだよね……
あまりに悔しかったのか、呻き声を漏らしながらゴツゴツとした岩肌の上でゴロゴロと転がったり飛び跳ねてる彼を見つめながら、そう思った。
その様子を見ていたヴァブが口を開く。
「どうします?これでは他の人が別のことをするしか…」
「うぐぐ…」
あんまり考えたくなかった事態に直面し、また頭を抱え始める。
今日だけで一体何回頭を抱えてるんだ、ボクは。そろそろ爆発でもするんじゃないだろうか。
そんな考えが頭をよぎった時だった。先ほどまで無音だった背後から、聞いたことのない声が聞こえてきた。
慌てて振り返ってみると、スクイッシーが目元を緩ませて腕を上下にばたつかせていた。
まさか……
「今のミアティスの動きがウケた…?」
「え、これですか⁈」
「たぶん…だってどう見ても笑ってるように見えるし」
そう言うとスクイッシーは頭全体でイエスを表そうとしたのか頭を縦に振り、腕を伸ばして目の前まで近づけると、七色に輝く結晶を差し出してきてくれた。
ボクはその結晶をありがたく受け取ると、触れた瞬間に小さな破裂を起こし残った光がボクの手元に残った。
「やった…夢のかけらゲットだ」
「お、無事受け取れたみたいですね」
「ああ。ミアティスのおかげだよ。ありがとね、ミアティス」
「ミアティス…?」
「なんか…嬉しくない……」
「まあ…そんな事もあるよ。次頑張ればいいのさ」
「ぐうう…〝元〟マジシャンとはいえ悔しい……」
今だ悔しがってるミアティスをなだめつつなんとか落ち着かせようとするが、相当ショックだったのかすぐには立ち直りそうになかった。
そんな様子を見かねたスクイッシーは気を利かせてくれたのか、またまたどこからか持ってきた赤い果実を腕いっぱいに抱えてボクらの前に立っていた。
ふと横を見ると目を輝かせたヴァブがただ一点を見つめて口をポカンと開けていた。
はああ…仕方ない。こうなったら…
「それじゃあスクイッシーの親切を無駄にしないためにも、一旦ここで宴でも始めようか!ほら、ミアティスも挽回のチャンスだよ、元気だして!」
「挽回…?そ、そういうことなら今度こそ笑わせてやる…‼︎」
「宴ですか!うおお…それは心踊りますね!今色々と用意しますよ!!」
ボクの宴という言葉に反応して、各々が意気揚々と準備に取り掛かる。
ここまで頑張って来たんだ。ここで宴の1つくらい開いてもいいよね。
それに、次のダンジョンに向かってしまえば、もう…
そんな複雑な気持ちをそっと胸にしまいつつ、ボクも準備の手伝いを始めるのだった……
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「あー、あれ完全にあたし達の事忘れてるよー!ねえ、ツバキもそう思うでしょ?」
「……」
「あれ?ツバキ⁈ちょっと、なんて顔してるの⁈その全てを悟ったような顔やめて⁈」
「……」
「やめてー!どっか行かないで戻ってきて!ツバキー!!」
その後、ツバキはヴァブの悪意なきビンタによって悟りの境地から無事に戻ってきたらしい。
つづく。


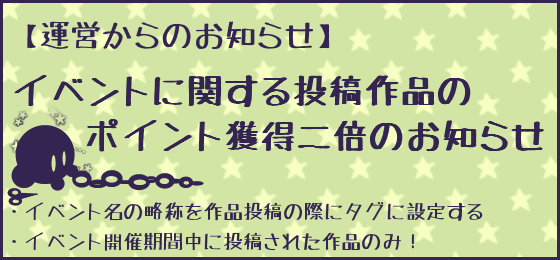
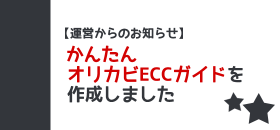
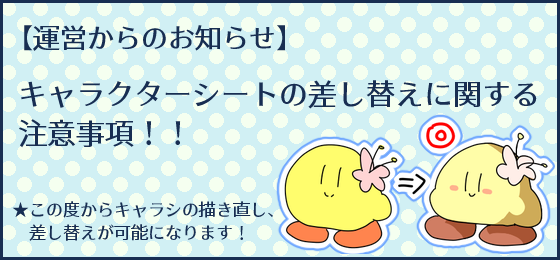
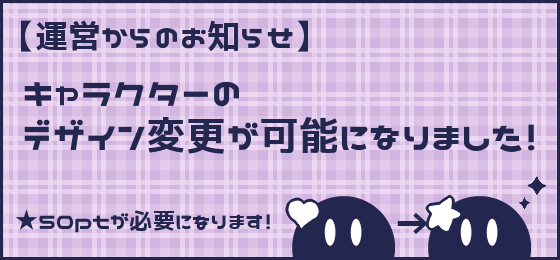
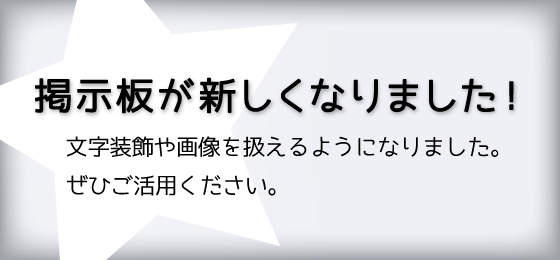
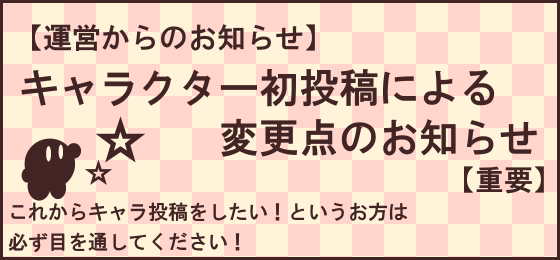
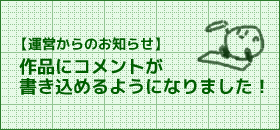

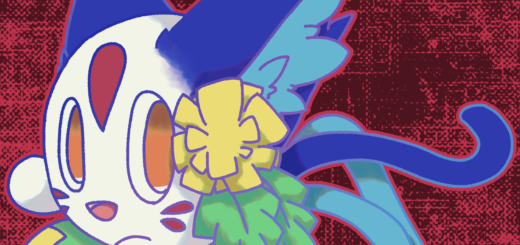



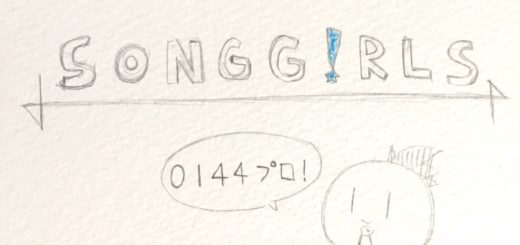


ツバキ君…とんだ災難だったな…w
全く持ってその通りですね()
ミアティスさんを応援したい…
きっと彼は相手が悪かっただけなんです…!