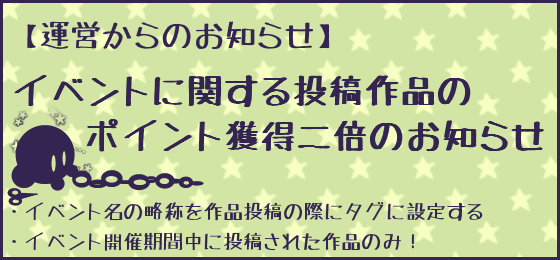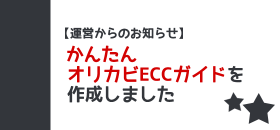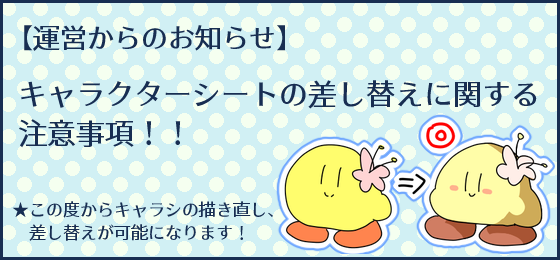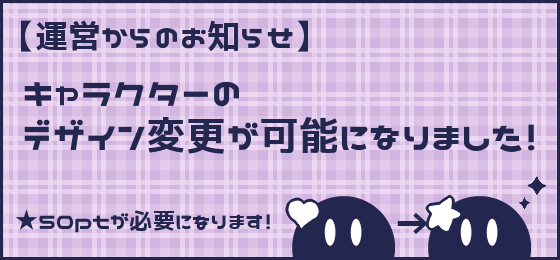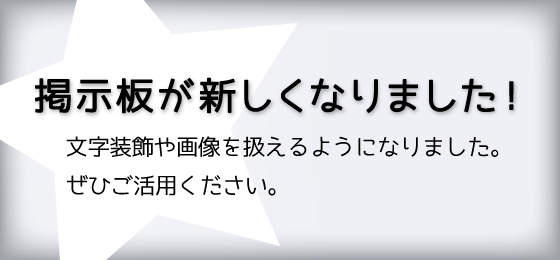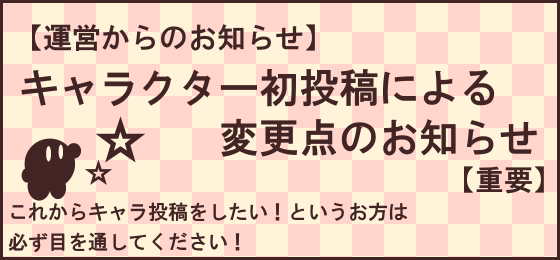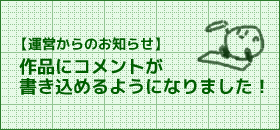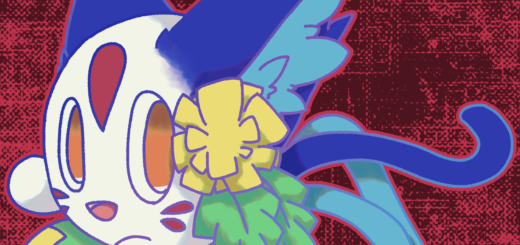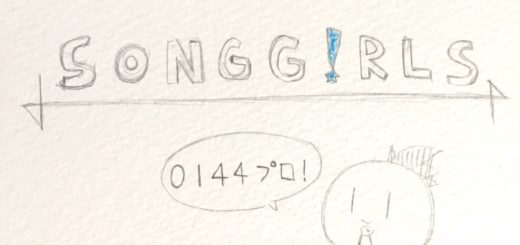わたしは神様。
人々を陰から支える、そんな存在。
今まで幾重もの時を過ごしてきた。
楽しいこと、辛いこと、嬉しいこと、悲しいこと…そんな感情を一般の方々と同じように感じながら生きてきた。
わたしはそんな風に感情を抱くことをとても喜ばしく思う。だって神様が人々と同じものを持つことは、理解へと繋がるとも思うもの。
だけど……
「こんなに胸が痛くて辛いなんて…思いもしなかった」
ふと顔を上げれば、真っさらなシーツの上で目を閉じたまま眠り続けるリゼさんの姿があった。
その姿はとても痛々しくて、見るに堪えない姿で…わたしは何度もリゼさんを見つめては俯くというループを繰り返していた。
なんでこうなってしまったのだろう。何故わたしは無事で、リゼさんがこんな目に…
「よう、どうだ容態は?」
「……」
「そうか…まだ目が覚めないか」
声の主は立てかけてあった椅子に腰掛けると、包帯をぐるぐる巻きにされた腕で飲み物を差し出してきてくれた。
わたしは礼を言って受け取ると、硝子のコップに口を当て一口飲み込む。
「まあ俺も今さっき起きたばかりだし、リゼのやつもすぐに起きるだろ」
「今さっきって…もうわたしが気づいてから1日は経っているんですよ?流石に心配です…」
「なに、心配するなって。こいつはそう簡単にくたばりはしないよ。あ、そうそう俺はキアっていうんだ。よろしく」
「ノッテです。あの…わたしはあなたが何者なのかということも、ここがどこなのかも分かりません。もし何か知っているのなら教えて頂けませんか…?」
「ああ、あの時お前は正気ではなかったからな。よし、なら俺がシエルヴィルで起こったこと、そして何故このような状況に陥ったのか説明してやる」
そう言うとキアさんは自分が知っていることを次々と語り始めた。
シエルヴィルでリゼさんに出会ったこと、町の住民がおかしくなっていたこと、リゼさんと共に町から脱出したこと……
そして…
「落ちた…?」
「ああ。空中をゆっくり下降していたんだが、まさかダークマター共に襲われるとは思わなくてな…」
「襲…撃」
「その時俺もリゼも両手が塞がっているせいで反撃ができなかった。それでも諦めずに避けていたんだが…限界だった」
「そんな…」
「ついには被弾をもらい、バランスを崩した俺たちはバラバラにされてしまった。その際リゼはお前と抱えていたもう1人を庇い負傷…今のような状態になってしまったということだ」
「……」
庇って…?わたしを、トアさんを庇ったからリゼさんはこんなに傷だらけだというの?
わたしはがくりと崩れ落ち、地べたに手をつく。
きっと…きっと同じ状況に自分が置かれていたら、わたしだってリゼさんと同じことをしたと思う。だけど頭ではそう分かっていても、気持ちが抑えられない。
「おいおい、大丈夫か?」
「大丈夫…です」
「そうは見えないが…」
「ご心配ありがとうございます。でも本当に大丈夫ですから」
わたしは差し出された手を掴みゆっくりと立ち上がると、大きく深呼吸をする。
心配そうなキアさんを横目に周囲を確認すると、あることに気がつき口を開く。
「そういえば…トアさんはどこですか?」
「あいつか?あいつは…」
「どうか…したんですか?」
「いないんだ、どこにも」
「いない?」
なんだか嫌な予感がして、ギュッと手を握りしめる。
「さっきここから飲み物を買いに行った時、他の病室や看護師に尋ねてみたんだがそんな人はいないんだと」
「ま、まさか…」
「どうやら、バラバラにされた時にはぐれてしまったらしい。そんな遠くまでは飛ばされてないだろうから、この町か、あるいは近くにはいると思うが…」
「……‼︎」
「おい、どこ行くんだ!まッ…痛つつ…!」
わたしはすぐさま椅子から立ち上がると、キアさんの声には聞く耳も持たずドアを開き廊下を駆け出す。
やってしまった…トアさんだけは何があっても守るって、町を出る時に誓ったのに……‼︎
色とりどりのチラシやポスターで溢れる廊下を歩く人々を避けながら移動し出入口まで向かうと、透明なガラスで貼られた自動ドアをくぐり抜け外に出る。
そうして我を失いかけてまで外に出たわたしだったが、町の外に広がる景色を見て一気に現実に引き戻された。
いや、引き戻されたのとは少し違う。これは……
「ああ…どういうことなの…?」
見渡す景色は間違いなくラ•メルセントロだった。石畳みでできた床、少し黒っぽいけどそれに負けないくらい真っ白なレンガで積まれた家々、ところどころに張り巡らされている水路……
この町には同じ水が有名な町同士として何度も足を運んでいるから、一目見れば間違いようがない。
…はずなのだけど、一点だけ記憶の中の景色から姿を変えているところがあった。
「水路が…」
以前はあれほど輝いて見えた水路の水が、光を通さないほどに真っ黒な泥水へと変貌していた。
近づいて下を覗き込んで見ても、やっぱり何も映らない。
「何かあったのかな…?なんだか少し気味も悪いですし…」
「あ!その水に触れてはダメ!!」
「?!」
突然の叫び声に驚き身を引くと、息を切らしながら走ってくる水兵さんの姿が見えた。
その水兵さんは目の前でブレーキをかけ息を整えると、急いで顔を上げる。
わたしは見覚えのあるその顔を見て少し驚きつつも、口を開く。
「あなた…トカゼさん?」
「もう、危な…ノッテさん⁈お久しぶりです!」
「随分とお久しぶりですね。お元気でしたか?」
「そりゃあもう!って、そんな話をしてる場合じゃなかった!!ノッテさん、アンタがいるなら心強い!一緒に来てくれ!」
「え?ちょっと…!」
わたしは訳が分からないまま、トカゼさんに手を引かれ奇怪な水路道を後にした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ここ、喫茶店ですよね?どうしてここに…?」
「みんなが集まってるんだ。さ、行こう」
トカゼさんに連れられて来たのはまだ外装も新しいお洒落な雰囲気の喫茶店だった。お店の前には今日のオススメのメニューを記したボードが凛として立っている。
こんな事をしてる場合ではないのだけど…と思いながらも店内に入ると、中は驚くほどに静かで空席ばかりが目についた。
周りを見渡しながらトカゼさんの後についてゆくと、一番奥の席で話し合いをしている3人の男の人が目に入った。
その顔はどれも見た事があるもので、わたしは席の側まで寄ると軽く一礼する。
その人達はそんなわたしの挙動に気がつくと、慌てて席を立ち口を開く。
「おいおい、誰かと思ったらノッテさんじゃねえか!久しぶりだな!」
「ちょっとトレントさん… 同じ水の町の町長さんに失礼ですよ…」
「別にいいじゃねえか。もう何度も会ってるんだし」
「それはそうかもしれませんけど…」
「ヴィルヘルムの言う通りだぜ?俺はバカだけどそれくらいの礼儀は分かる」
「なーんかリズに言われると釈然としねえな」
「まあまあ…わたしはそれで構いませんよ。皆さんもお元気そうで何よりです」
わたしは3人にそう返すと、トカゼさんに勧められたのでご厚意に甘えて椅子へと腰掛ける。
トカゼさんはわたしが落ち着くのを確認すると、真剣な眼差しで話を切り出す。
「みんな集まったね。それじゃあ早速本題に入ろうか」
「トカゼさんがボク達を集めるくらいです。となると、やはり例の話ですか?」
「その通り。今日集まってもらったのは他でもない、あの水路を汚した犯人をとっちめるためだよ」
「やっぱりその話か…」
ヴィルヘルムさんとトレントさんは自分の予想が当たっていたようで、途端に目つきが鋭くなる。
一方でフローリズさんは話が未だに理解できていないのか、飲み物をストローですすりながらきょとんとしていた。
「それで、犯人は分かったのか?」
「うん。どうやら水路の水が流れてくる上流の方で泣いているダークマターの涙が原因らしい」
「ダークマター…?涙……⁈」
予想もしていなかった話に思わず声が漏れる。
「アタシも最初は目を疑ったよ…まさか泣いているダークマターがいるなんてさ」
「それで…そのダークマターは何体いたんですか?」
「数はたったの一体さ。でも少々厄介でね…」
「たった一匹なら楽勝だろ⁈何をそんなにッ」
「そうはいかないんだよ。あいつは感知に優れているらしくて、200mも離れた場所に隠れて見ていたアタシに熱光線を正確に撃ってきたんだ。死ぬかと思ったよ」
「つまり近づけないってことか…」
トカゼさんの言葉にトレントさんはますます頭を抱える。そんなトレントさんにつられるようにわたし達もどうすればいいのか考え始める。
しばらくこんな沈黙が続くと思っていたけど、思わぬ人物が手を挙げたことでみんなの視線が一気にその人に集中する。
誰だろうと確認してみると、なんと手を挙げていたのは今までぼーっとジュースを飲んでいたフローリズさんだった。
「なーんか難しい話でよく分からなかったけど、要するにあれだろ?そのダークマターに気づかれずに攻撃すればいいんだろ?」
「まあそうなる…かな。でもそんなことできるわけが……」
「できるできる。これだけメンバーがいるんだ。なんとかなるだろ」
「なんとかって…そんな適当な」
「そうと決まれば早速準備しようぜ!ノッテ、知恵を貸してくれ」
「わ、分かりました…やってみましょう」
フローリズさんの言葉に二つ返事で了解を出すと、すぐさま2人きりの作戦会議に移る。
こうなってしまった以上はこの流れに乗ってダークマターを倒すしかない。わたしだって水路を元の美しい姿に戻せるなら力になりたいしね。
こうして先に店から退出した3人の事を気にしつつも、わたしはいい作戦を出すために全力を尽くした…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ターゲット捕捉!どうやらまだこちらには気がつかずに、呑気に水の上で夕日を見ているみたいだぜ?」
「分かった。トレントはそのままその望遠鏡でダークマターを見張ってて。アタシ達もそろそろ準備できるから」
「了解了解ーっと」
トレントさんがあくびをしながら返事をするのを横で聞きながら、わたしはジッと前だけを見つめてサラーキアを構える。
あたりの真っ白な家々は夕焼け色に染まり足元には深い影が落ち始めていた。
フローリズさんは全員の様子を確認すると、声を上げる。
「よし、最後にもう一度だけ作戦を確認するぞ。まずはトレントのサーフボードに乗った俺以外の全員が俺の出す流星に乗って敵へと突っ込む」
「おうよ!」
「その後トレントの水で更に勢いを加速させ敵の懐へと潜り込む。その際俺はここから敵の光線を流星で遊撃する。だがそれでも避けきれない場合はトカゼがウィングでノッテを運べ」
「うん!」
「その時にはもう敵の目の前まで近づけてるはずだ。そしたら後はノッテがその槍で敵を貫け」
「ええ…分かりました」
「問題はこの状態で上手くいくかだ…」
フローリズさんは自分の右手を握り締めて深く呟く。それもそのはず。わたしを含めた全員が、普段の力を全く出せないという状況にいるのだから。
わたしは先ほど全員の確認を取るまでカンパニュラで力が出せなかったのは思い違いだと思っていた。でもそうではなくみんながみんな、この町の住民ですら力の1割ほどしか出せないみたい。
ここまでの大人数が同じ状況に置かれているとなると、何か原因があるに違いないとは思うけど、リゼさんは何ともないって言ってたし…
でも今はそんな事を言ってる場合じゃない。集中しないと!集中集中!
「それじゃあ準備できたみたいだしいくぞ!」
「え、待って…! ボクはどうすれば……」
「シューティングスター!!発射!!!」
「だからボクはどうすれ…あばばば!!!!」
フローリズさんの合図と共にわたし達を乗せたサーフボードは爆音を響かせながら勢いよく飛び出す。
廻まじく過ぎてゆく景色と風を切る音だけが目に、耳に、体全体に伝わってゆく。
「おおおおーー!!!!こんなスピードで波に乗るなんてそうそうないぜぇ!!!」
「そんなこと言ってる場合⁈早速きたよ!!」
「おっと!」
前方からチラリと紅い光が見えたかと思うと、目の前で何事もなかったかのように消え去る。
それと同時に視界が右に左にと揺れ動く。
「よっ、おっとと!」
「トレントさん、まさか今の全部見えてるんですか⁈」
「まあな!いくらリズのやつが遊撃してくれると言っても、ある程度は避けねえとな!」
「凄いですね…!」
「褒めたって何も出ねえぞ?」
「浮かれてるところ悪いけど、飛ばさせてもらうよ!」
「え、え⁈」
トカゼさんが何を言っているのか確認しようとした瞬間、突如体が引き上げられ地面が遠ざかってゆく。
わたしが何故飛んだのかを聞くよりも早く、トカゼさんの声が頭上から響く。
「だいぶ近づけたね…このまま敵に向かって急降下するよ!」
「ええ⁈このまま乗っていても良かったのでは!」
「そうはいかないんだよ。見てみな」
トカゼさんに言われるがまま下を見下ろすと、ボンッという爆破音と共に砂煙が巻き上がる。
「トレントさん!ヴィルヘルムさん!!」
「あいつは調子に乗るといつもああだからね。早めに飛んでおいて良かったよ」
「お二人とも……‼︎」
「さあ行くよ!あとはお願い!!」
その言葉と同時に空中へと放り込まれるが、迫り来る真っ赤な光線を紙一重で避けながら狙いを定めると、槍に力を込め目玉へと深く深く突き刺した。
突き刺した箇所からはドス黒い液体がドクドクと流れ落ち真下の水路水をより一層汚してゆく。
「な、なんで消えないの⁈やっぱり威力不足で……‼︎」
このままではまずいと必死に力を入れるが状況は一片も変わろうとはしない。
「も、もう力が…」
徐々にサラーキアに掴まっている力すらも抜け始め自分はこのまま水の中へと沈むんだ…と思った瞬間、背中に暖かな熱が広がってゆく。
ぐったりとしながらも目を見開くと、傷だらけのトレントさんの姿が映った。
「トレントさん…?」
「おー、危なかったな!後はヴィルヘルムのやつに任せとけば大丈夫だ!」
揺れる視界でトレントさんがにっと笑った直後、背後から「爆裂ハンマー投げ!!!」という声と何かが破裂する音が鳴り響いた。
トレントさんは「やりい!」と叫ぶと、わたしの方を振り向いて
「へへ、お疲れ様!」
と爽やかな笑顔で言った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「結局ダークマターは倒しても水路の水はそのまま…か」
「でも原因は片付けたんだし、後は綺麗にするだけだね!」
「だがよ、どうするんだよこれ。オレには無理だぞ?」
「まあ今は無事に倒せた喜びに浸かりませんか」
「そうですね」
わたし達はお互いの顔を見合わせながらホッとした表情で笑いあう。これでもう水路が汚れることはなくなった。けど…
チラリと覗いた水路は最初に見たときと何一つ変わってなかった。これでは解決した内には入らない。
……わたしは自分の町を救うためにリゼさんと旅を始めた。だからここに踏みとどまってはいられない。進まないといけない。
だけど今のわたしの心は何をすべきか、すでに決まっていた。伝えなきゃ、あの人たちに。
「あ、やっと見つけた。探したぜノッテ」
「リゼさん…」
ふと聞こえてきた声に振り向くと、包帯で身体中を巻かれたリゼさんがこちらを見つめて立っていた。
「悪いな、心配させちまって」
「いえ、大丈夫です。リゼさんが無事ならそれで…」
「そうか。じゃあ行こうぜ、向こうでキアが待ってる」
「あの、リゼさん!」
心を落ち着かせて、はっきり言わなきゃ。みんなのために…
「わたし、この町に残ります!!」
「……え?」
一瞬固まったリゼさんを一心に見つめながら言葉を続ける。
「今、この町の水路は以前の輝きを失っています。でも同じ水の町に住む者としてこの事態を放ってはおけません!」
「…お前は本当にそれでいいのか?自分の町を救いたいんじゃなかったのか?トアだって…」
「もちろんカンパニュラを救いたい気持ちは今でも変わりません。でも今は目の前のこの町を救いたいんです!それにトアさんもまだこの町の近くにいる可能性もありますし……‼︎」
「……」
「自分勝手な事は百も承知です!ですがお願いします、残らせてください!!」
心の限り叫び、深く頭を下げる。
一時の時が微かな風の音と共に流れると「分かったよ」という声が頭の中に響いた。
わたしは嬉しさと申し訳なさでいっぱいになりつつも顔を上げると、リゼさんは背中を見せながら呟く。
「ただし、やるからにはキッチリとこなせ。あたしはビルレストに向かうからな」
「…はい!!」
リゼさんはそう言葉を残すと、しっかりとした足取りで一歩、また一歩と離れてゆく。
そんな離れて小さくなってゆく背中を見えなくなるまで見つめていた。
ずっと…ずっと……
「ノッテさーん?何してるのー?」
「あ、ごめんなさい。今行きます!」
あとはよろしくお願いします、リゼさん……
つづく。