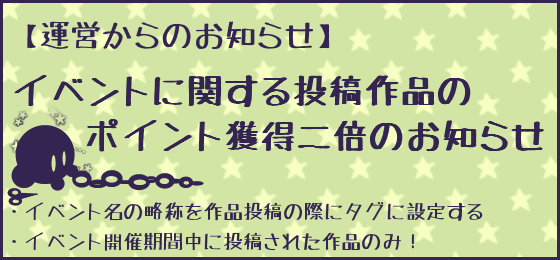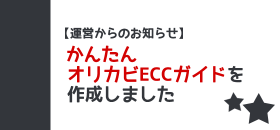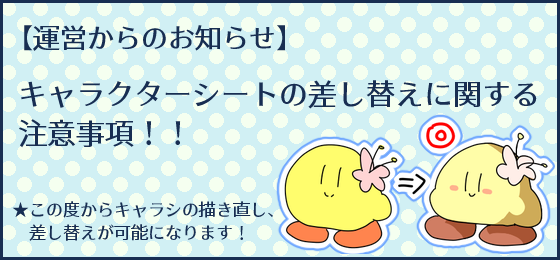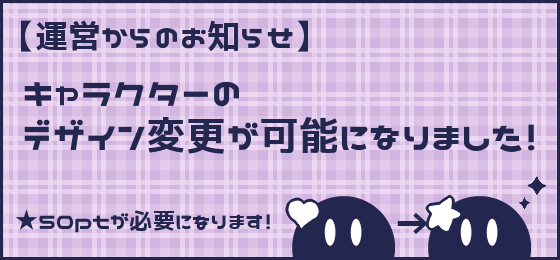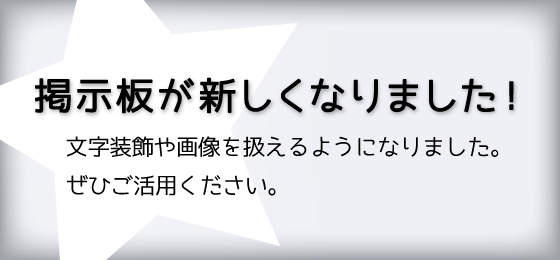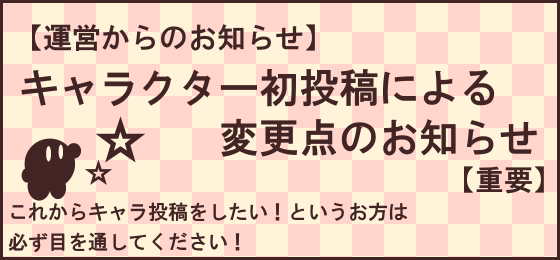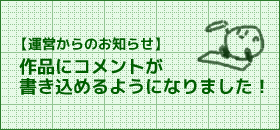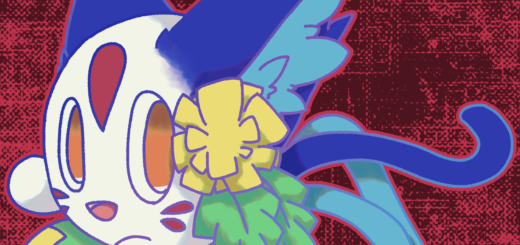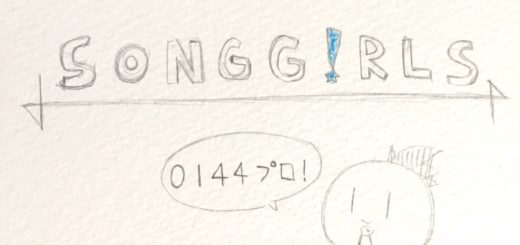俺の名前はヴィオ。メカノアートに店を構える料理人だが、オレ自身は専ら自前のキッチンカーで移動販売をしている。
今日も柊のやつに注文を受けて、キッチンカーに乗り込みメカノアートからムーンホールまで向かう途中、だったのだが…
「…なんだ、ありゃ。」
ふと目の前を見やると、道の真ん中に黒い人影が見えた。
「行き倒れ…か?」
近づいてよく見てみると、ソイツは黒い体に頭に角を二本、背中に虫の翅のようなものと尻尾を生やしており、いわゆるオーソドックスな”悪魔”のような格好をしていた。
「…おい、オマエ」
大丈夫か、そう声をかける前にギュルル、という腹の虫が返事を返してきた。成る程、まだ生きてはいるらしい。急ぎ車に行き、ジャーキーを持って戻ってくる。
こいつはオレが移動中に食べる為に持ち歩いてるものだが、一度口に入れると飲み込むのが勿体なくなるような代物だ。
普段ならまず他人にはやらない、が、ソイツの口に水と一緒に無理矢理ねじこむ。
「んむ…っ!?」
そんなことをされれば流石に目を覚ましたようだが、そんなことはどうでもいい。そのジャーキーはただの前座だ。香辛料の辛味で目を覚まし、咀嚼で唾液を分泌させて、オレの料理を喰う準備をさせる為の食べる側の下ごしらえ。
「今からテメェに料理を作ってやるからそれ喰ってそこで大人しくまってろ。あと手は洗って、うがいもしとけ。」
口は動かしながらもぽかんとした表現のソイツに構わず、それだけ言って踵を返す。
腹を減らしてるやつがいて、食材があり、オレがいる。とすれば、やることは一つ。
さっきまで行き倒れてたやつを長々と放置しておく訳にはいかない。となれば、手早く作れ、かつ、腹に貯まるモンーつまり炭水化物なのだがーとなれば、結論はもう出ている。
キッチンカーに掛け戻り、手を洗い、特注品の消毒液を刷り込んで、先ずは球体一人なら軽く収まるほどの大きさの中華鍋を火にかける。
…このキッチンカーはメカノアートの技術を駆使して、オレの店の厨房にも負けず劣らずの設備を詰め込んである。
だが、それでも俺が満足できないものがひとつだけある。ーー火力だ。
中華は火力が命…オレは特殊は人並みだが、火の取り扱いに関してだけなら、特殊5連中にも負けないと自負している。
ファイアの能力を発動し、中華鍋を火にかける、と同時に秘伝の中華ダシを溶いた玉子に混ぜる、溶き卵を鍋に入れ、そこへ直ぐ様厳選した脂と、真珠色に炊き上がった米を鍋に入れ、炒める。お玉が鍋を走る度、黄金色に衣替えした米が踊る。炒める。一口救って、味を慣れた手つきで整え、火を止める。
ここまで20秒弱。
「レストラン・ヴァイオレット特製黄金炒飯完成ィ…と。」
球体は、人によって食う量にかなり個人差があるが、仮にアイツが人より食う体質でも、ざっと見積もって二人前。恐らくこれだけあれば足りるだろう。
鍋に収まった黄金色の炒飯を、大皿に素早く盛り付け、アイツの元へ向かう。
キッチンカーを降りると、意外にもアイツは行儀良く居直して、何処から取り出したのかナプキンを首もとに巻いて待っていた。ただひとつ、口許から溢れる涎を堪えきれていないのはまあ、許してやろう。
行儀の良いやつは嫌いじゃない。
テーブルと椅子をひとつずつ並べ、まだ熱々の炒飯を差し出す。
「本日のメニューは……いや、まあ、いい。食え。」
ニイ、と笑ってテーブルに大皿を乗せる。客がオレの料理と対峙する瞬間。この瞬間がオレは好きだ。
「…いただき、ます。」
ここに来て初めてコイツの声をまともに聞いた。会って最初の言葉がいただきますとは奇妙だが、今思うとオレとコイツの間ではそれが一番しっくりくるような気がする。
何故か?
その理由は直ぐに分かる。
ソイツが行儀良く手を合わせたかと思った次の瞬間、目の前で山盛りになっていた炒飯が、信じられない早さで消えていったからだ。
球体には食う量に個人差があるといったが、そこにはあまり食べないヤツ、そこそこ食うヤツ、良く食うヤツ、そして驚くほど食うヤツがいるのだ。
つまり、コイツは「食う側」の球体だったってことだ。
料理人としての経験上、こういう底なしのヤロウは滅多に見ない。実際、コイツが炒飯を米粒ひとつ残らず腹に収め、料理に対する賛辞やらなんやらを言い終わるまで、オレは唖然としていた。
だが、同時にオレのなかで料理人としての何かに火がついたらしい。
「助かりました、うっかり朝の食事で手持ちの食糧を食べ尽くしてしまって…」
アイツが何やら言ってた気もするが、オレにはもはや聞こえない。
「…食えるんだろ?」
「えっ?」
「オマエ、…まだ食えるんだろ?」
「…」
アイツは答えなかったが、俺は再びキッチンカーに戻っていった。正直聞くのも馬鹿馬鹿しいほど、アイツが食べ足りていないことは明らかだった。
幸運なことに、今日は”たまたま”材料がたんまりとある…これだけ使えば流石にアイツも満足するだろう。
オレは晩餐会のメニューを考えながら、お気に入りの包丁を手に取った。
ーーーーーーーーー
ーーーーー
ーーー
それから小一時間、料理を作っては出し、作っては出ししていたが、遂に材料が底を尽きた。
…が、丁度頃合いだったようだ。キッチンカーの外の椅子には、先ほどより幾分かまるくなったアイツが、満足げに腹を擦っていた。
最後の料理を持ち、コトリとテーブルに置く。
「本日最後のデセール、アマレットプディング…芳醇な香りと、仄かな苦味をお楽しみ下さい。」
あまり柄ではないが、敢えて口上を述べてみる。どうやらコイツはやたらテーブルマナーに厳格らしい。此方としてもそれに答えてやろうという気になっただけだ。
これまで通り、ただ行儀良く匙ですくい、口へと運ぶ。淡々と食事をしてちるようだが、口に含んだ瞬間の僅かな動揺と微妙な表情の変化を見るのはやはり楽しかった。
「ご馳走さまでした。」
それから、ソイツがどうしても借りを作ったままにはしたくないなどと言うので、店の場所と、オレの名前だけ教えてやったらもう一度礼を述べて歩いて行った。
結局、材料はすべて使い果たしてしまったし、柊に連絡したらこっぴどく怒られたが、充足感に満ちていたオレには全く響かなかった。
今日は楽しかった。明日は何処に行こうか。仕込みをしながら考えることにする。